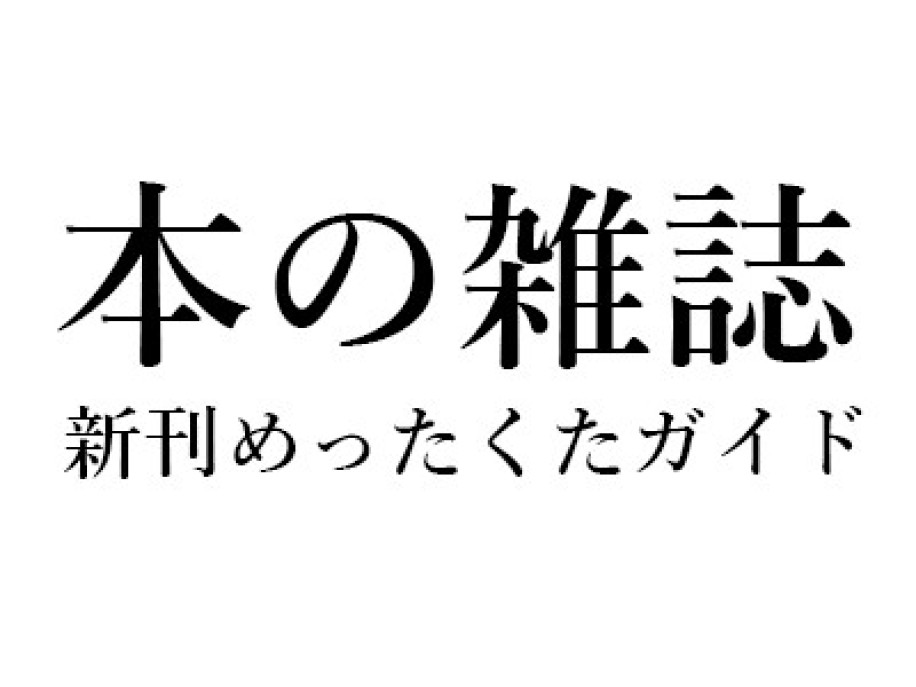読書日記
キム・スタンリー・ロビンスン『グリーン・マーズ』(東京創元社)、ニール・スティーヴンスン『ダイヤモンド・エイジ』(早川書房)、古川日出男『アラビアの夜の種族』(角川書店)ほか
優勝候補同士が大激突。五つ星の日米大傑作対決だあ!
なんの因果か、昨年末は年間ベスト級の大作がどさどさ登場(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2002年3月)、SF読者は至福の寝正月を過ごしたはずだが、おかげで今月号当欄は〇二年W杯一次リーグ〝死のF組〟的状況。なにしろ緒戦から、九四年と九六年のヒューゴー賞/ローカス賞をそれぞれW受賞した優勝候補同士が激突しちゃうのである。キム・スタンリー・ロビンスン『グリーン・マーズ』上下(大島豊訳/創元SF文庫)★★★☆は、評判の『レッド・マーズ』に続く《火星》三部作の第二部。どうもオレはこの三部作と相性が悪いらしく、今度も(前作ほどではないが)読み進むのに苦労した。〝惑星改造を描きつくす、途方もないリアリティ〟(下巻オビより)はその通りだけど、客観的な(科学的・工学的・社会学的な)リアリティにこだわるあまり、主観的リアリティというか、小説のダイナミズムを失っている。そりゃたしかにハインライン『月は無慈悲な夜の女王』の単純さが愛された頃とは時代が違う。でも、それを言うなら、特定個人たち(〈最初の百人〉の生き残り組)にここまで特権的な役割を与えるのはどうよ。火星独立革命の背後にはアメリカ独立革命が透けて見え、そのせいか白熱する議論や感動の大演説にも妙な居心地悪さを感じてしまう。実力は認めるにしても、オレは好きになれないチームだな。
対するニール・スティーヴンスン『ダイヤモンド・エイジ』(日暮雅通訳/早川書房)★★★★★は、文句なしに応援したいオレ好みの個性的な傑作。
時は二一世紀半ば。国民国家の時代は終わり、それにかわって種族(ファイリー・phyle)や族部(トライブ)と呼ばれる集団が各地に国家都市(クレイブ)を形成している。ヴィクトリア朝的な価値観を復活させて経済貴
族制を敷く欧州系種族の《新アトランティス》(および日系の《ニッポニーズ》)がナノテク革命のトップランナー種族。彼らにライフラインを握られた《漢(ハン)》(内戦を経て共産主義中国は崩壊している)の民衆は、この金剛石時代(ダイヤモンド・エイジ)にも不遇をかこち、義和拳団の他種族排斥運動が吹き荒れる。
──と要約すれば、清朝末期の大陸情勢が下敷きになっているのは明白だし、事実、階層的なナノテク支配体制を打破すべく《漢》の一部が極秘裏に進める「革命」の策謀が本書全体の縦軸をなす。とはいえ、そうした政治情勢は物語の背景に押しやられ、貧困家庭に育った少女ネルの成長譚が前景化される。焦点となるのは、新アトランティス人の貴族が娘の教育用につくらせた対話型ナノテク絵本、《若き淑女のための絵入り初等読本(プリマー)》。その不正コピーを偶然手に入れたネルは、プリマーが語るプリンセス・ネルの冒険譚(現実と微妙にシンクロしつつ変化するRPG的なおとぎ話)に没入することで世界を発見してゆく。
カスタムメイドのナノテク新製品が偶然にも貧困階級の少女の手に落ち、それを複数の勢力が追いはじめる──というプロット構造は、リンダ・ナガタ『極微機械(ナノマシン)ボーア・メイカー』とそっくりなんだけど、本書のウリは、問題のナノテク新製品が、〝物語を語りながらユーザーを教育する装置〟だという点にある。早い話、ゲームボーイと「RPGツクール」と「どこでもいっしょ」を合体させた一体型端末がものすごく進化し、なおかつオンラインで匿名のゲームマスターとリアルタイム接続されてるみたいなもんですね。その結果、プリマーが語るプリンセス・ネルの物語は、現実のネルの境遇を微妙に反映し、なおかつ教育的なデータを盛り込みつつ、外側のストーリー進行に合わせて千変万化してゆく。
なんでもありのナノテクは、魔法と区別がつかない。スティーヴンスンはこの構造的欠陥を逆手にとり、魔法のようなナノテク(現実)とおとぎ話の魔法(作中作)をアクロバティックに重ね合わせる。「まさかアレがコレになりますか?」的な離れ業が次々に炸裂する後半はまさに圧巻(ただし、大人になってからのネルがキャラ的にやや弱いのが難)。
メタフィクショナルな仕掛けも魅力的だが、ナノテクで変貌した異形の未来描写がまたすごい。五隻の船に乗って洋上を漂う二十五万人の幼女、乱交によって情報を伝達しながら膨大な計算作業を実行する海底の人々、儒者のように孔子を引用する《漢》の裁判官……。
スティーヴンスンの未来では、科学的・工学的・社会学的リアリティよりも審美性が(というか面白さが)重視されている。なにしろ、今から半世紀後の話だというのに、ヴィクトリア朝復古主義と儒教社会が対立し、義和拳団の暴動が上海周辺を席巻するのだから、これは明らかに確信犯。アメリカ人読者がどう読むのかはよくわからないが、日本の読者にはけっこう身近なネタが多く、野阿梓『バベルの薫り』を思い出させる部分もある。真面目に語るふりをしつつ全篇にギャグがちりばめられているので油断できない。
その一方、グローバリズムが進展した豊かな世界で持てる者と持たざる者が対立するという基本構造は、捏造された未来史とは関係なく、強い同時代性とアクチュアリティを感じさせる。異形の未来を語りながら、いま、ここにある問題が否応なくクローズアップされるところがスティーヴンスンのしたたかさ。どのページを開いても魅惑的なアイデアがあふれ、読み出したら止まらない。スピード感では前作『スノウ・クラッシュ』に劣るものの、二読
三読に耐える密度がある。てなわけでこの両雄対決、オレ判定ではスティーヴンスンの圧勝です。
これで優勝決定か──と思いきや、ホームの日本から超弩級の秘密兵器が登場した。ジャンルSFじゃないから同列には評価しにくいが、古川日出男『アラビアの夜の種族』(角川書店)★★★★★は、米国代表の顔色をなからしめる大傑作。オビの文句をもじって、〝世界文学に忽然と登場した稀代の書!〟と呼びたい。英題The Arabian Nightbreeds が示す通り(原著者不詳の小説をこの英訳版から〝翻訳〟したという体裁をとっている)、構成は「千夜一夜物語」風。世界文学としては、ジョン・バース「ドニヤーザード姫物語」、ロバート・アーウィン『アラビアン・ナイトメア』、ジクリト・ホイク『砂漠の宝』なんかの系譜ですが、それら世界的な傑作群と比べてもまるで遜色がない。日本なら、泉鏡花賞と三島賞と直木賞とこのミス一位をまとめて進呈したいほど。
時は聖遷(ヒジユラ)暦一二一三年(西暦一七九八年)、ところはマムルークが実権を握る、オスマン帝国支配下のカイロ。ナポレオン率いるフランス艦隊がエジプトに迫り、旧態依然のマムルーク軍では勝ち目がないと見た首
長(アミール)に、万能の執事アイユーブが秘策を授ける。すなわち、読む者すべてを狂気に導くという伝説の本、「災厄(わざわい)の書」を敵軍に献上すること……。
じつに魅惑的な導入だが、ほどなく驚愕の事実が明らかになる。なんと、この話はアイユーブのでっちあげで、「災厄の書」などというものは実在しないのである。ではどうするか? 存在しないなら自分でつくればよい。
かくしてアイユーブは、口述筆記を担当する書家を伴って、エジプト一の語り部ズームルッドのもとを訪れ、架空の書物の製作に着手する──という話がこの本の外枠で、夜ごとズームルッドが語る、千年の時を越えた途方もない物語が小説の中核をなす。いわく、『もっとも忌まわしい妖術師アーダムと蛇のジンニーアの契約(ちぎり)の物語』。あるいは『美しい二人の拾い子ファラーとサフィアーンの物語』。剣と魔法、活劇と魔物、血と暴虐、奇想と乱調の美にあふれたこの作中作のすばらしさは筆舌につくしがたい。その魅惑的細部に立ち入る紙幅はないが、たとえば史上最凶の妖術師アーダムが建設した地下迷宮の凄まじさを見よ。千年後の発掘時、そこは無数の魔物が跳梁跋扈する伏魔殿と化しているのだが、正常な人間は生きて出られぬこの迷宮の封印を解くため、時の支配者は八八八八人の狂人を送り込み、そこで生活させるのである。
この驚くべき物語に土台を提供したのは、古川日出男の幻のデビュー作、『ウィザードリィ外伝Ⅱ 砂の王1』(ログアウト冒険文庫)。ベニー松山がシナリオを書いたゲームボーイ用RPGの名作『ウィザードリィ外伝2 古代皇帝の呪い』をもとに、ノベライズを越えた迫真性とオリジナリティを獲得した未完の小説だが、そのパーツがズームルッドの語る異形の物語に消化吸収され、驚くべき変貌を遂げて甦っている。ファンタジーRPGが本来的に持
つ〝物語の祖型〟の野蛮な力が本書の魔術的な語りによって最大限に引き出され、それが巧緻な文学的枠組と見事に融合する。その原初的なパワーは枠物語の枠を越えて歴史を侵食し、さらに虚構/現実の境界さえも食い破る。掛け値なしに、十年に一度の傑作だ。
偶然にも、『ダイヤモンド・エイジ』とよく似た戦術(ですます調の作中作から大量の訳注まで)を採用しているから、この両者の「枠物語」東西対決も歴史的名勝負になりそう。これが事実上の決勝か?
さて、F組最後の一チーム(違うって)は、粕谷知世の日本ファンタジーノベル大賞受賞作『クロニカ 太陽と死者の記録』(新潮社)★★★★。異教徒支配下のアンデスを舞台に、ご先祖様のミイラがインカ帝国(タワンテインスーユ)滅亡の物語を語るという、これまたマジックリアリズム的趣向を凝らした歴史幻想小説の秀作。『アラビアの夜の種族』を小粒にした感じの好チームですね。ふだんの月ならイチ押しになってもおかしくないが、さすがにこの組では分が悪い。
しかしよくもまあ優勝を狙える作品ばかりが集中したもの。おかげで今月紹介予定だった残り七作はすべて次号送りに。やれやれ。
【この読書日記が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする