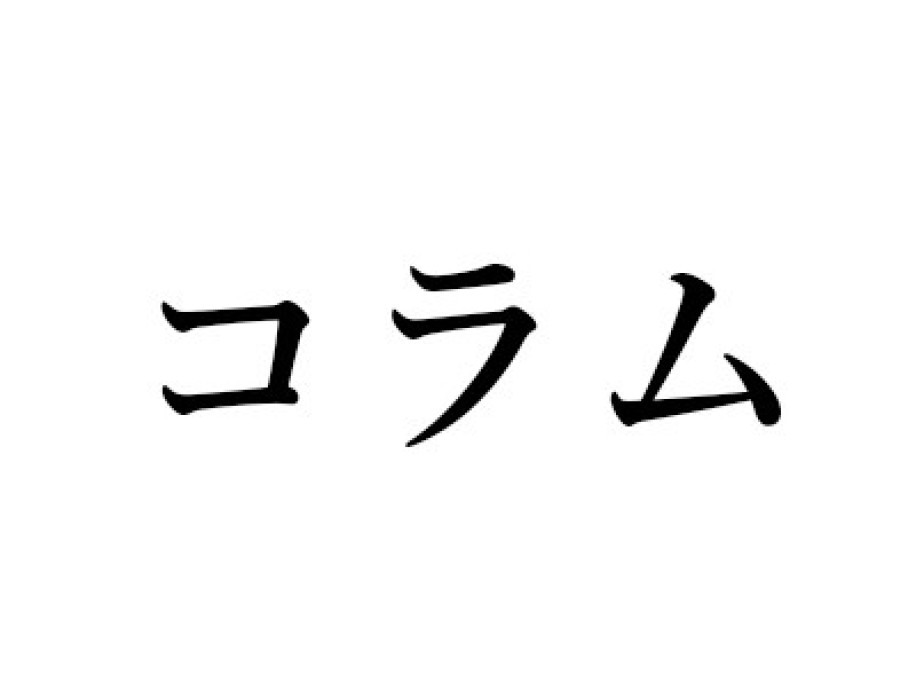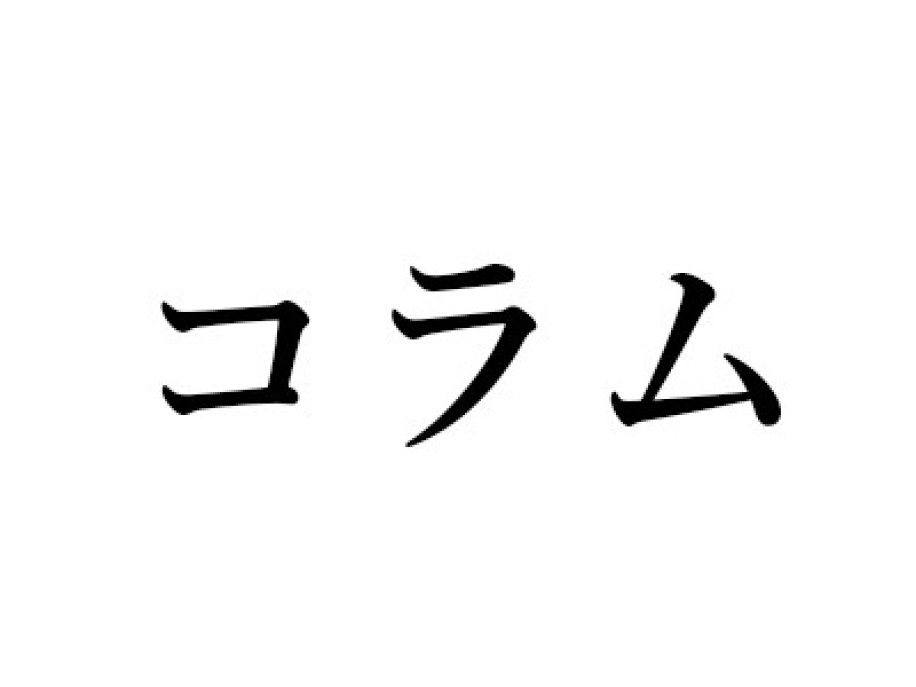解説
『車輪の下』(新潮社)
「自分は詩人になるか、でなければ、何にもなりたくない」
ヘッセは60年代の日本の青年によく読まれた。「受験地獄」「管理教育」がしきりに呪誼されはじめた当時、『車輪の下』とその作家は反「学校」主義の象徴と見なされた。しかし「受験地獄」は、高等教育の大衆化で学生数が急増し、かつ、みながよい会社のサラリーマンになりたがったから生じたのだし、「管理教育」への非難は、おもに自由とわがままの混同、個性とたんなる未熟さを、なかば意図してとり違える民主的教育観から発したのだった。学校とはもともと退屈なところなのである。その結果、子どもでも青年でもないアドレッセンス期、その心象と精神的危機をえがくという、洋の東西を問わず近代社会に普遍する『車輪の下』の主題は見逃されがちになった。
内容解説
ひたむきな自然児であるだけに傷つきやすい少年ハンスは、周囲の人々の期待にこたえようとひたすら勉強にうちこんで神学校の入学試験に通るが、そこでの生活は少年の心理を踏みにじる規則ずくめなものだった。少年らしい反抗心に駆りたてられた彼は学校を去り、見習い工として出直そうとする……。子どもの心と生活を自らの文学の故郷とするヘッセの、代表的自伝小説。【この解説が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする