書評
『侏儒の言葉・文芸的な、余りに文芸的な』(岩波書店)
芥川龍之介『侏儒の言葉』
問題は、顔だ。日本の文学史上、芥川龍之介ほどみごとに顔文一致した作家というのも珍しいんじゃないだろうか。顔文一致、しかも(ここが大事なんだが)美男系で。澁澤龍彥といえどもかなわない。
ひいでた額に、切れ長の涼しげな目。江戸前の、助六役者にしたいような二枚目でありながら、口もとにはかすかに悪魔的な感じも漂っている。イギリスの立派な学者のようでもある。
作家というものが、そのまんま「教養人」であり「言論人」である――そういう時代が確かにあった。漱石・鷗外の時代である。芥川龍之介の顔も作品も、そういう時代の作家のイメージにみごとにこたえている。顔も文も、知的な二枚目だ。そして三十五歳でみずから幕を閉じた、その生き方さえもすきがない。芥川もあのような容貌に生まれつかなかったら、芥川文学もどうなっていたかわからない。私はけっして文学をおとしめるわけではないのだが、人間って案外と自分の顔に引きずられて思想してしまうものだと考えているのだ。くどいようだが、芥川文学はよくも悪くも、知的な二枚目の文学である。
ほとんど三十年ぶりに『侏儒の言葉』を読み直してみた。私の本棚の隅にあった岩波文庫の最後のページを見たら「1964・10・30」というメモがあった。ぴったり三十年前。これは、あんまり明らかにしたくない事実ではあるが……私が高校三年生だった年の秋にあたる。ページをぱらぱら繰ってみると、赤鉛筆やボールペンの強調線や◯印や?印などのマークがあって、どうやら何年か置いて二、三回は読んでいるらしい。私にしては珍しく、熱心に読んでいる様子なのである。(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆年は1994年)
昔の私と今の私。いったいどのくらい重なっているものなのか、ズレているものなのか?――という、少しばかり〈私探し〉的な興味に駆られて、読み始めて行ったら、いきなり、
道徳は便宜の異名(いみやう)である。『左側(さそく)通行』と似たものである。
道徳の与へたる恩恵は時間と労力との節約である。道徳の与へる損害は完全なる良心の痲痺(まひ)である。
妄(みだり)に道徳に反するものは経済の念に乏しいものである。妄に道徳に屈するものは臆病ものか怠けものである。
というくだりに激しくマークがしてあるので、思わず苦笑してしまった。何しろはるか昔のことで、はっきりとは思い出せませんが、高三の私がこのアフォリズムを、ほんとうに身にしみて、深い生活実感を持って、しんそこ共感したとは、とても思えないのだ。笑っちゃうくらい世間知らず苦労知らずの少女(ガキ)だったのだもの。いったい、どういう気持で赤鉛筆を走らせたのか、今ではとんと見当がつきません。
ただ一つだけわかることは、私は少女(ガキ)の頃から、こういう逆説的で皮肉で……つまり、わざわざ“ミもフタもない”ような見方や言い方をするのが、やけに好きな人間だったということだ。
恋愛は唯(ただ)性慾の詩的表現を受けたものである。少くとも詩的表現を受けない性慾は恋愛と呼ぶに値(あたひ)しない
という一節なぞも、だいぶ気に入ったようで、しっかりマークがしてある。
その後、大学に入ってから倉橋由美子小説に惹かれ、「恋愛とは精神の一種の充血状態にすぎない」という言葉をほとんど呪文(じゅもん)か護符のようにしていた時期があったが、どうも私はこんなふうに、まず“ミもフタもない”ような見方をしたうえでないと何もできない、安心できない、納得できない――そういう傾向があるようだ。もしかするとそういうのを簡単に「臆病」と言うのかもしれない。
私は世間知らずで苦労知らずだった(今でも相変らず、というところもある)。俗にまみれるのがこわかった。世間というのは、何が飛び出して来るかわからない深い森のようで、いきなりそこに足を踏み入れるのがこわくて、まずザッと俯瞰(ふかん)で全体像を把握してからでないと。ようするに私は「世界観」というやつが欲しいんだなあ……と、十代の私は焦っていたのだと思う。
そうだ、だんだん思い出して来た。同じ高三の夏にエンゲルスの『フォイエルバッハ論』(ルードウィヒ・フォイエルバッハとドイツ古典哲学の終結。懐かしの大月書店国民文庫だ)を明け方までかかって読んで、まさに「目からウロコが落ちた」ような気持になって興奮した。あれは、俯瞰図を手に入れた興奮だったんじゃないか? 何だかわけのわからない、この世界にも、ある一定のスジミチ立った法則性がある。そこのところを押さえておけば、とりあえず、こわいもんなし。これで私も強気で世間に打って出られる、世間をなめてかかれる――というような。
私がマルクス主義文献に興味を示したのも、『侏儒の言葉』を読んだのも、結局、その動機の根っ子は同じ。「世間」――もう少し気取って言えば「世界」に対する臆病さだったような気がする。地図なしでは一歩も歩けない臆病者。何かしら人目を惹くスタイルでキメなければ外出できない気取り屋。身の程知らずの知的な二枚目志向――。芥川も『侏儒の言葉』の中で言っている。「あらゆる言葉は銭(ぜに)のやうに必ず両面を具へてゐる。例へば『敏感な』と云ふ言葉の一面は畢竟(ひつきやう)『臆病な』と云ふことに過ぎない」。
それ故に、昔の私も今の私も芥川の大衆嫌悪部分には、たぶん一番、共感してしまうのだ。たとえば、「醜聞さへ起し得ない俗人たちはあらゆる名士の醜聞の中に彼等の怯懦(けふだ)を弁解する好個の武器を見出(みいだ)すのである」とか、輿論は常に私刑であり、私刑は又常に娯楽である」――というような。ただし、昔の私はあまり気にとめなかったようだが、芥川はこうも言っているのである。「民衆の愚を発見するのは必ずしも誇るに足ることではない。が、我我自身も亦民衆であることを発見するのは兎も角も誇るに足ることである」と。
ここで私はフッと思う。冷笑こそは臆病者の「俗」にたいする最大の、いや最も安直な復讐(ふくしゅう)なのだと。冷笑にとどまっているようじゃあ、ダメよね――と。
明治時代の斎藤緑雨が好み、大正時代の芥川龍之介が好んだアフォリズムという形式。できるだけ短い文章で、人間や世の中の真実をえぐり出す。警句。格言。金言。つまりは……私好みの“ミもフタもない”言い方をするならキメツケというやつである。おのずから、抽象的で概念的な言葉を駆使することになる。「正義」とか「自由」とか「民衆」とか。
こういう、いわば大ざっぱな言葉を抵抗なくスッと使えるというのは、あまり文学的とは言いがたい。作家というよりもむしろ評論家的な資質であって、作家としての首を絞めることにもなりかねない。緑雨も芥川も危ない橋を渡っているのである。
『侏儒の言葉』は、一九二三年から一九二七年にかけて書かれた。一九二七年というのは芥川が亡くなった年である。
そう思って読むせいか、最後のほうで突然「わたしは……」という書き出しで始まるアフォリズムが続くようになるのが、ざんげじみているというか、遺書めいているというか。全体にストレート過ぎて、アフォリズムらしい芸に乏しいのだが、この一連の最後の、
わたしは勿論失敗だつた。が、わたしを造り出したものは必ず又誰かを作り出すであらう。一本の木の枯れることは極めて区々たる問題に過ぎない。無数の種子を宿してゐる、大きい地面が存在する限りは。(昭和改元の第一日)
というのには胸がしめつけられてしまう。「わたしを造り出したもの」というのが何を意味するのか、はっきりと言葉に置きかえられないにもかかわらず――。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
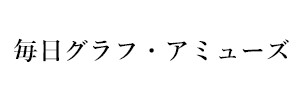
毎日グラフ・アミューズ(終刊) 1994年6月8日号
ALL REVIEWSをフォローする









































