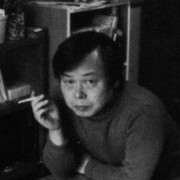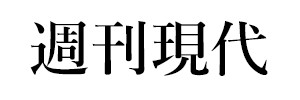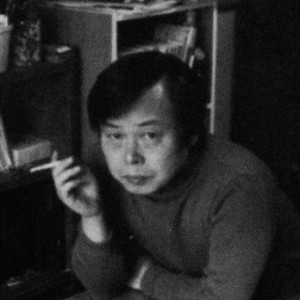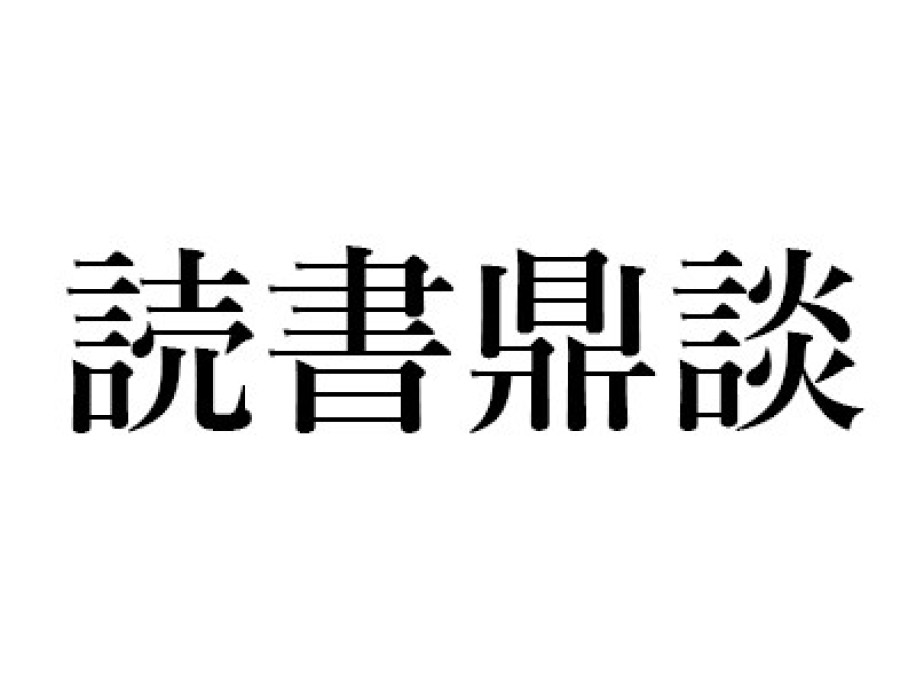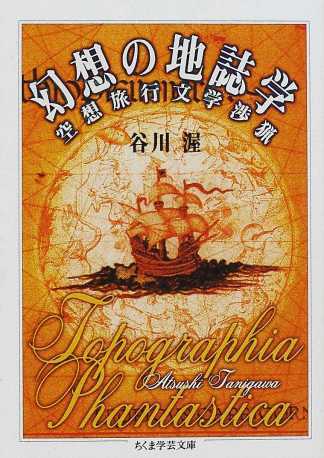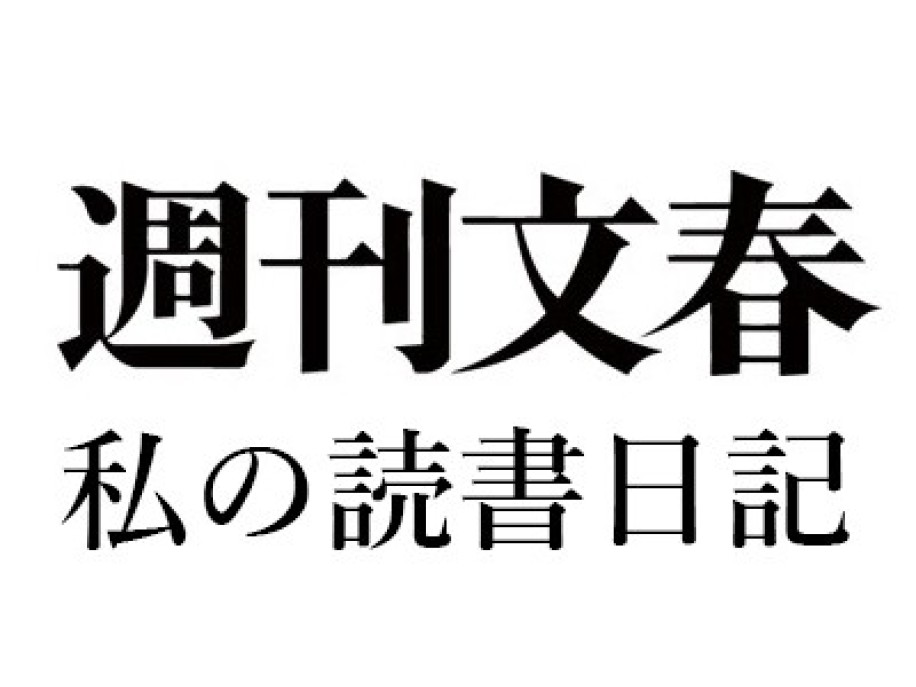書評
『地図のファンタジア』(文藝春秋)
技術のファンタジー
『地図のファンタジア』の題名通り、古今東西の地図を素材にして、これにまつわるファンタジーを縦横に語ったエッセイ集である。もともと地図そのものが人間の宇宙に対する奔放なファンタジーの産物であるのだから、地図のファンタジーの種はつきない。だから地図が実用化されてからも、詩人や小説家はこと地図となるとたちまちファンタジーの赴くがままにとんでもない心得違いの誤測を起こしたりする。たとえば『紅はこべ』の怪盗パーシー男爵が自室の壁にぶら下げているパリとドーヴァー海岸の地図や『宝島』のフリント船長の地図は、現在の測量法を使うと、何人が何日がかりで総費用いくらで出来るか。答えは天文学的な数字で、とうてい小説家の空想通りには行かないことが判明すると同時に、地図制作のプロセスが素人にも分かりやすく説明される。
その他、丸橋忠弥の音響測深法、コロンブスのアメリカ発見の端緒となった誤測、ファリア神父の幾何学的誤算のためにかえって地下牢を脱出することができたモンテ・クリスト伯の幸運など、地図にまつわる珍談奇談が紹介され、東は三国志や西遊記の地誌学的考察から指南車の用法にいたるまで、古今東西の神話や文学の挿話を博学な地理学者の立場から再構成している。
もっとも、著者の観点はあくまでも現代の地図制作術の達した技術水準の現場から割り出されているので、地誌の精神史やイメージの遊戯は周到に避けられている。ファンタジーの誤測を、さめた技術の観点から明らかにするのが著者の意図だからである。そのくせ、ともすれば味気ないものになるおそれのあるさめた技術の記述が、かえって地図のファンタジーを生き生きと輝かせているのが奇妙で、それはたぶん、著者が空想と科学との間をどちらにも偏らずに、くつろいで往復している余裕のためだろう。
【この書評が収録されている書籍】