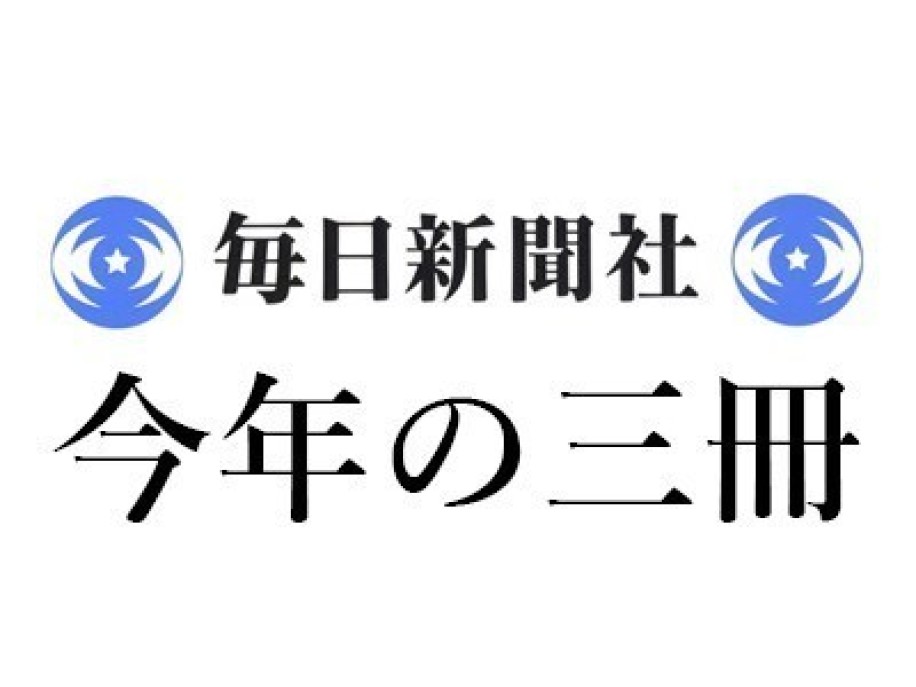書評
『コンテクスト・マネジメント 個を活かし、経営の質を高める』(光文社)
現場へのヒント満載の経営学
ハーバード大の経営学博士で、ロンドン大ビジネススクールで教えた著者は叫ぶ、ありきたりのMBAなどクソ食らえ! そして自前のスクール(ISL)を立ち上げ、それを母体に五年前、大学院大学至善館を日本橋に開校した。本書はそこでの講義録である。MBA(経営学修士)は経営幹部を育てる。金儲けと株主利益に走りがちだ。至善館もMBAだが≪全人格経営リーダーシップ≫を掲げる。本書にはその教育理念のエッセンスが詰まっている。
MBAと言えばケース・メソッド。第1章、ホンダはなぜ北米進出に成功したか、が面白い。コンサル会社が分析する。戦略の勝利ですね。スーパーカブで市場の隙間(ニッチ)に食い込み、それから大型バイクや自動車に展開しました。世界中のMBA教材に載っている。
でも本当か。別な学者がよく調べたら、その逆。大型バイクを売るはずが故障続きで撤退寸前に。そのときたまたま50㏄のスーパーカブが注目されて、あとは成り行き。戦略などなく、偶然が重なっただけで成功したのです、と。
戦略の勝利(ホンダA)か、偶然(ホンダB)か。実は中間(ホンダC)だ、と著者は言う。ピンチのたびに頑張れたのは≪経営陣が…起業家精神に満ちた組織をつくりたいという明確な意図を持っていたから≫。それは、企業コンテクストの勝利なのである。
本書は、経営学のさまざまな潮流や論点の変遷を丁寧に紹介。現場へのヒントが満載である。
著者は言う、組織は≪1人ではできないことを成し遂げるためにつくられる装置≫、経営は≪人を通じてよりよいことを持続的になすこと≫。そして≪よい経営/そこそこの経営≫がある。どうすれば≪よい経営≫ができるか。本書はそれをとことん追究する。
経営は、組織のあり方と関係が深い。単純な機能別組織(U—form)では、トップは研究開発/製造/販売を統括する。企業が多角化すると、事業部制(M—form)が増えた。トップは事業部を統括。事業部はそれぞれの研究開発/製造/販売を統括する。トップ(本社)と事業部の間に葛藤が起こる。縦割りの弊害や大企業病が蔓延(まんえん)する。それならと社内ベンチャーの旗をふり、他社との戦略提携、M&Aなどに手を出すが、小手先なので失敗する。
経営を≪組織構造や経営管理システム…ではなく、プロセスの束として見≫るべきだ。起業家精神を発揮する≪革新プロセス≫、知識やスキルを移転させる≪統合プロセス≫、資金を活用する≪業績達成・活性化プロセス≫である。現場のマネジャーは≪積極的な起業家≫に、ミドルは≪見守るコーチ≫に、トップは≪企業コンテクストの建築家≫になりなさい。
3Mには15%ルールがあった。本務に関係なくても15%以内ならOK。剥がれる接着剤を造ってしまった技術者が社内を説明して歩いた。聞いた社員がひらめいてポストイットが開発できた。
こういう機転は「場の匂い」があるから可能になる。そんなコンテクストをつくるのがトップの役目。≪自分の頭で思考し自分の言葉で語る≫人間力の勝負だ。だから至善館は定番のMBA科目に加え、リベラルアーツを重視する。経営は≪サイエンスとアートの混じった世界≫。本物の経営リーダーを育てる注目の教育法だ。