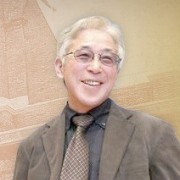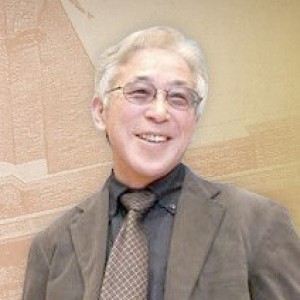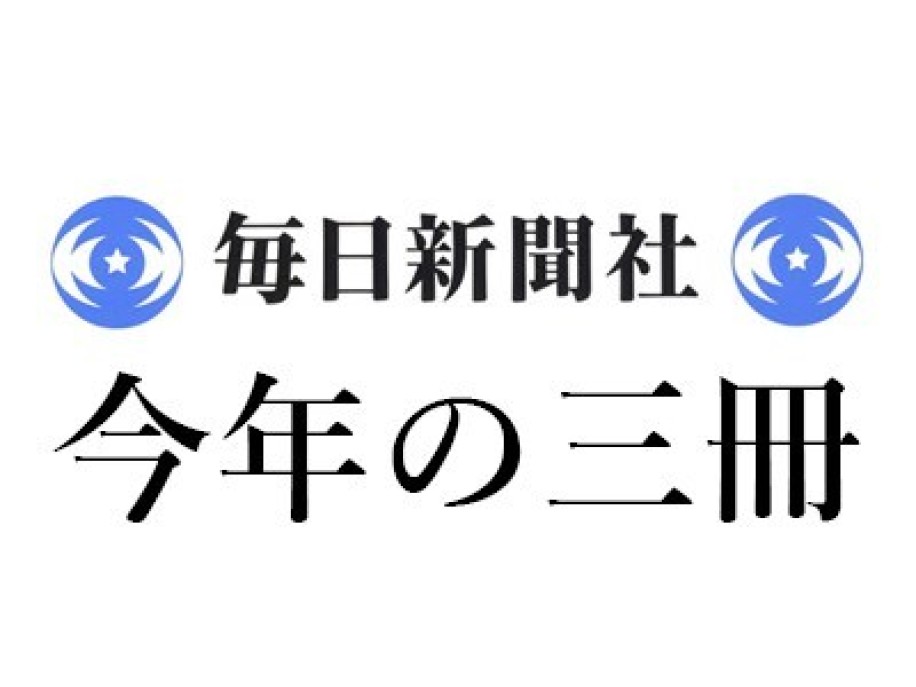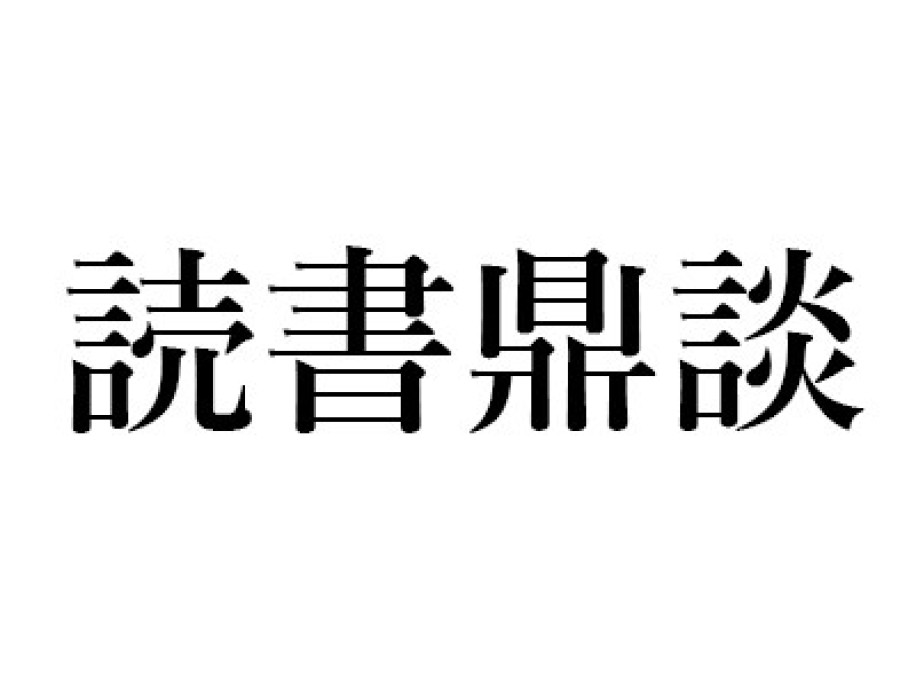書評
『パンテオン: 新たな古代ローマ宗教史』(東京大学出版会)
「生きられた宗教」というテーマ
パンテオンとは汎神(はんしん)の意で、とくに帝国の公認する神々のすべてが祭られたローマの神殿を指す。高さ・直径とも43メートルの円筒形本堂の天井には円形の大穴が開いており、太陽神を示唆している。そこに立つと古代建築の華麗さに圧倒されるほどだ。神々を話題にすれば、近現代の人々は、ジュピター、アポロ、ヴィーナスなどの人格神を想像しがちである。ところが、太古にさかのぼれば、ローマ人はそれらの個性あふれる神々など思い描かなかったらしい。そこでは、造形物が奉献される聖域、明確な表象やシンボル、テクストや教義の確立などがあれば、宗教行為をする者ははっきりするという。
だから、著者によれば、宗教とは「人間生活で直接になじみ深い身近な社会的場を超えた特別な環境の拡張」と定義される。「なじみ深い世界」を超える場とは、完全に文化に依存するものになる。死者であったり、人間の姿や特定できない場所であったり、あるいは海の彼方の人間にも向けられるのだ。
ここで対象となるのは、古代地中海世界の宗教であり、それはきわめて流動的な現象、つまり「パンテオン」の総体を観察することでもある。中心となるのは神的なものの力ではなく、人間の行為であるのだ。登場人物は絶え間なく変わり、宗教行為と宗教概念の変化よりも頻繁におこっている。
ローマに近いエトルリア人は、墓という空間で亡くなった祖先と接触することを重視していた。それは、イタリアの都市で、家族の実績や個々人の祖先の行為が名声や地位のために重んじられたことに結びつくかもしれない。古代イタリアには、ギリシア神話のごとく自分たちを神々の子孫と位置づけるようなことはほとんどありえなかったという。なにはともあれ、過去に生きた人々が先祖と神聖なる領域とどのように交流したのか、その切実な生き方をわれわれは理解しなければならない。
しかしながら、海外地域に進出し、ギリシア、小アジア、ガリア、スペインなどの地中海沿岸域、やがてパレスチナやエジプトにまで領土を拡大するにつれ、使節、商人、奴隷、戦闘兵さえもイタリアにやって来た。とりわけ、先進国のギリシア人の物語叙述は評判が高く、共通のローマ史を発見しようとする試みが生まれたという。
前二世紀にさかのぼる年代記などの作品群が生まれ、諸神殿の寄進の日付とともにローマ人と諸家族の成功例が暦のなかに導入されたという。宗教が哲学の資源となるものであり、その最古層をなすことが知られると、ようやく共和政末期に概念としての「宗教」が論じられるようになったらしい。
しかしながら、本書のなかでもことさら注目されるのは「生きられた宗教」というテーマである。エリートや皇帝ではなく、ローマ市民あるいは庶民が生活経験する古代宗教とはどうであったのか。身のまわりの社会環境に応じて各人各様の生き方はどうであったのか。たとえば、帝政期の都市民にとって、街路は「家」であり、そこにあるランプの光に照らされるものは宗教的交流の道具でもあったという。そこで生きられた宗教実践と経験は色彩に富んでおり、それぞれの行為者を浮かび上がせるのが、新しい宗教史の試みになるはずだという。重厚な大作であるが、読書後の充実感がある。