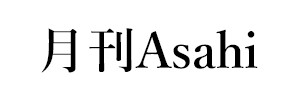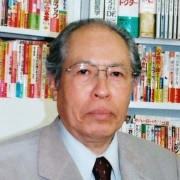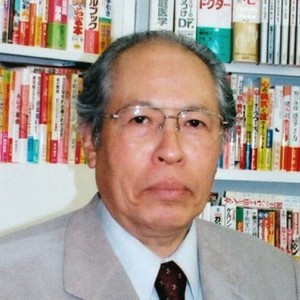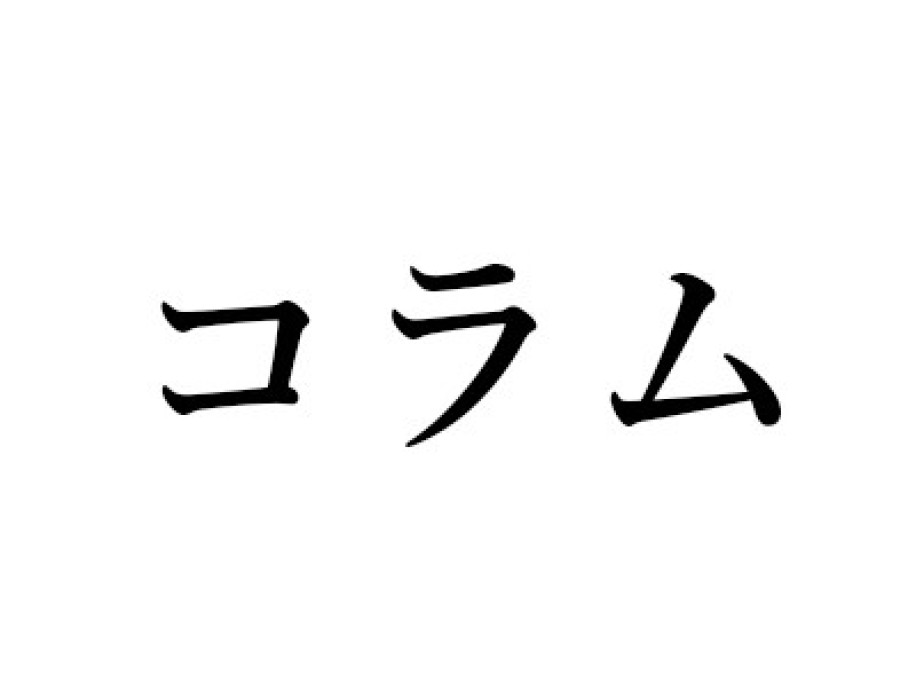コラム
海音寺潮五郎『赤穂義士』(講談社)、渡辺保『忠臣蔵』(講談社)、丸谷才一『忠臣蔵とは何か』(講談社)など
文庫で読むオリジナル「元禄」
忠臣蔵の本は十二月と三月に刊行されることが多い。文庫でも多士済々だが、まず赤穂事件の概要を史実に即して理解するには、海音寺潮五郎の『赤穂義士』(講談社文庫)が便利だろう。口碑伝説の多いこの事件を、信用の置ける文献本位に、多くの創見を加えて整理してみせた正統的史伝。渡辺保『忠臣蔵――もう一つの歴史感覚』(中公文庫のち講談社学術文庫)は、忠臣蔵がこれほど民衆に愛されたのは『仮名手本忠臣蔵』などの芝居の力が大きいとして、現実の出来事がどのように共同幻想としての演劇に収斂していくかを綿密に跡づけている。ほかに史伝スタイルの定本として福本日南の『元禄快挙録』が岩波文庫に収録されているが、現在品切れなのは残念。
しかし、忠臣蔵は史実という点から見ればほとんど洗われつくし、手垢にまみれた感がないでもない。このような現状に一石を投じたのが丸谷才一の『忠臣蔵とは何か』(講談社文芸文庫)で、討入りの浪士たちが火事装束を身につけていることにヒントを得て、忠臣蔵が曽我物語を典型とする御霊信仰の枠組みにあるとし、そこから生じた演劇性、呪術性を解明、さらには将軍綱吉あるいは徳川体制への呪いが盛りつけられている『仮名手本忠臣蔵』の重層的構造を指摘するなど、日本人の精神史としての忠臣蔵に新しい照明を投げかけた。
フィクションとしてはまず大佛次郎『赤穂浪士』上下(時代小説文庫)をあげるべきだろう。昭和二年(一九二七)という不安の時代に現れた作品だけに、赤穂側、吉良側の確執を一種の体制内の闘争として捉え、堀田隼人や蜘蛛の陣十郎など架空の人物に反体制的な役割を与えることによって、元禄という時代を昭和に引きつける。“義士”を“浪士”とした最初の例としても注目される。
年代的にはこのあと真山青果の戯曲『元禄忠臣蔵』上下(岩波文庫)が来る。昭和九年(一九三四)から七年がかりで書かれたもの。「第二の使者」「吉良屋敷裏門」「仙石屋敷」といった構成に独自の工夫が感じられ、緊迫した台詞が見事である。海音寺潮五郎の『赤穂浪士伝』上下(中公文庫のち文春文庫)も戦時中の作品だが、当時武士道が封建的忠誠に過ぎず、日本人の本来の道は皇室への忠誠であるべきだとする世論に反駁する意味で執筆されたという。
戦後は江崎俊平『赤穂浪士』(春陽文庫)に続いて、森村誠一『忠臣蔵』全五巻(角川文庫)がある。綱吉の悪政から筆を起こし、柳沢吉保の死にいたるまで、時代背景を重視しながら関係人物のエピソードを追っていく。朽木民部なる反体制派や、西鶴の後身として石原無息庵なる人物を設定したところがミソ。
現代人が忠臣蔵に惹かれるのは奢侈繁栄の時代における反体制という主題にあるのだろうが、元禄という時代を通史的に理解するには、児玉幸多『日本の歴史・元禄時代』(中公文庫)がある。また、この時代の尾張藩奉行の日記『鸚鵡籠中記』を解説した神坂次郎『元禄御畳奉行の日記』(中公文庫)も見逃せない。当時の武士の風俗や好尚が鮮やかに描かれているが、とりわけ目につくのは彼らの演劇好みで、赤穂事件のイメージが演劇によって形成されたことを側面から立証する結果となっている。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする
初出メディア