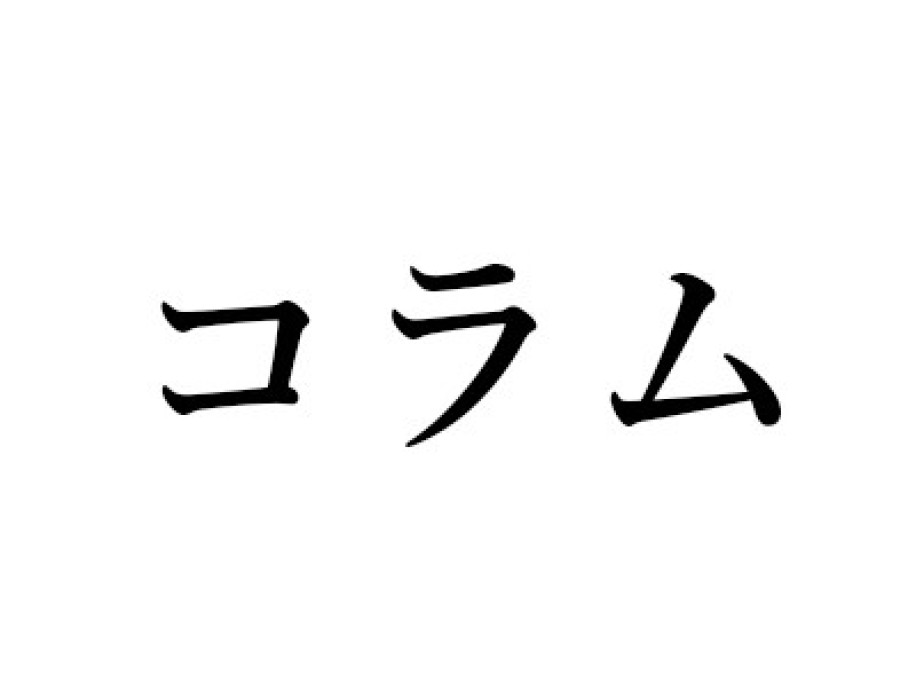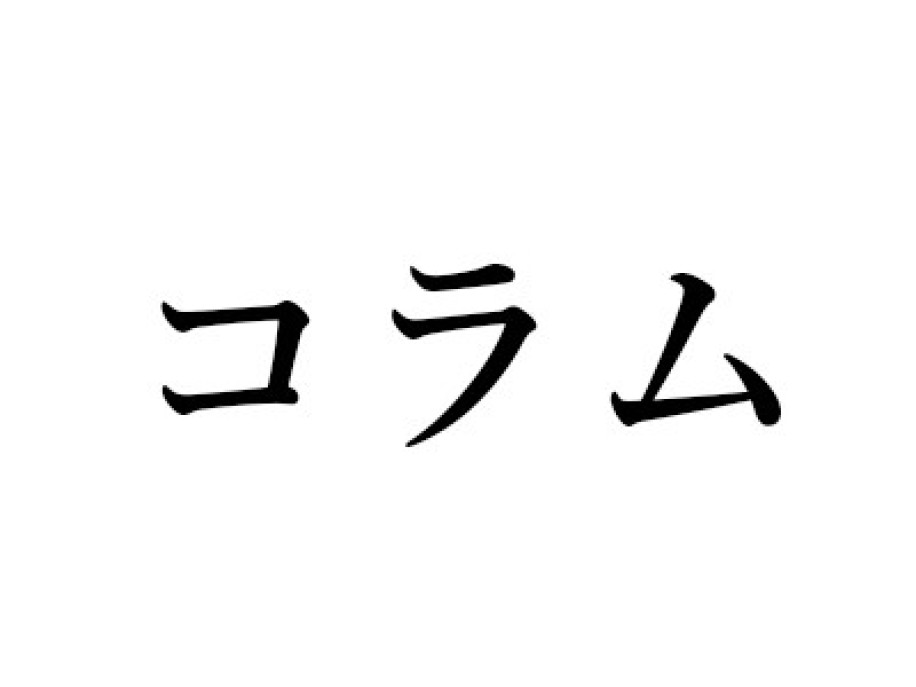書評
『横しぐれ』(講談社)
父親殺しのミステリー
丸谷才一の『横しぐれ』は、昭和四十九年の「群像」八月号に発表された。今から二十年の昔(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1996年付近)。当時、これを読んだときの感銘は忘れがたい。日本語を、あるいは日本の文芸史そのものをミステリーの題材にする、こんな手法があったのか、と小説というジャンルの奥深さに陶然となったものだ。自分もいつか、と闘志をかきたてたのもいまは昔。『横しぐれ』は一九九一年、優れた外国小説に与えられる英国のインディペンデント外国文学賞特別賞を受賞した。大賞はクンデラの『不滅』だった。
語り手の〈私〉は、中世和歌・連歌専攻の大学助教授で、水戸の婦人科医だった父が、晩年問わず語りにきかせてくれた昔話をきっかけに奇妙な追跡劇がはじまる。太平洋戦争勃発の前年の晩秋、友人で旧制高校の国語の教授、黒川先生と四国へ旅をして、松山・道後の茶店で乞食坊主と行きあい、酒を酌み交わした。
酔いも半ば、こつぜん横なぐりの雨がきて、さすが国文学専攻黒川先生が、横しぐれ、といった。それに坊主はいたく感心して、しきりにうなずき、雨の中へ傘もささず、横しぐれ、と一声残して掻き消えた。
父の死後五、六年してから、〈私〉は偶然筑摩書房版『現代俳句集』で、
しぐるるや死なないでゐるしぐるるやしぐるる山へ歩み入る
と種田山頭火の句に行き当たってはっとなる。略歴を読むと、妻子を捨て、行乞(ぎょうこつ)して全国を遍歴、昭和十五年松山にて死亡、とあった。
①父と黒川先生が酒を酌み交わした乞食坊主は山頭火だったか。
②黒川先生が思わずつぶやき、乞食がいたく感心した横しぐれという歌語の出処。
③乞食が山頭火だったとしたら、しぐれの句の多い彼になぜ横しぐれを使った句が一句もないのか。
④日中戦争たけなわ、日米開戦まぢかの折に、ほとんど旅などしなかった父と黒川先生が、なぜ一週間も四国の旅、つまり遍路のような旅に出たのか。
ほぼ以上四つの謎の解明がこの小説、上質のミステリーの変わり種を構成する。①②③はいわば本と資料の渉猟、つまり日本短詩型文芸史の森の迷路へ、④は〈私〉にからまる人間模様と記憶の迷路へ、と〈私〉と読者をいざなう。
ミステリーの常套に従って、偶然と想起と推理の三つ巴によるストーリーが展開する。例えば、〈私〉は偶然大学近くの料理屋の便所の「楽書」で、おとはしぐれか、という山頭火の句に出くわし、立ち寄った碁会所で、決定的な証言を与えてくれることになる、理科の八木沼先生と三十年ぶりに邂逅する。興味が集中を生み、集中が、偶然を呼び寄せて推理が加速し、その運びで想起が生まれる。やがて物語は、たしかにある真実らしきものに到達する。
(ALL REVIEWS事務局注:以下、ネタバレあり)
それは、定家がらみの、横しぐれという歌語の誕生秘話の発見、あの乞食坊主はまちがいなく種田山頭火だったこと、山頭火が横しぐれの句を作らなかった、いや作れなかった理由、などが読者にここちよく明らかになるのだが、僕はやっぱりこのミステリーのミソは、そういうペダンチックなおもしろさよりも、〈私〉が、父親が人殺しであったことを発見する、これにつきると思う。
父と黒川先生の旅は、じつは父が〈私〉の母以外の女を愛して捨て、他の男の子供を妊った彼女の中絶手術に失敗して死なせた、そのことに絡んだ旅だったことが明らかになる。
つまり、探偵たる〈私〉・息子は犯人たる父親をみつけ、そして、たぶん殺す。この父親殺しは、茫々とけぶる横しぐれのなかで行われる。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする