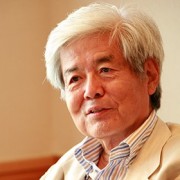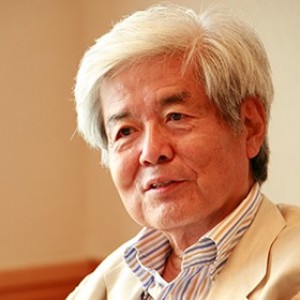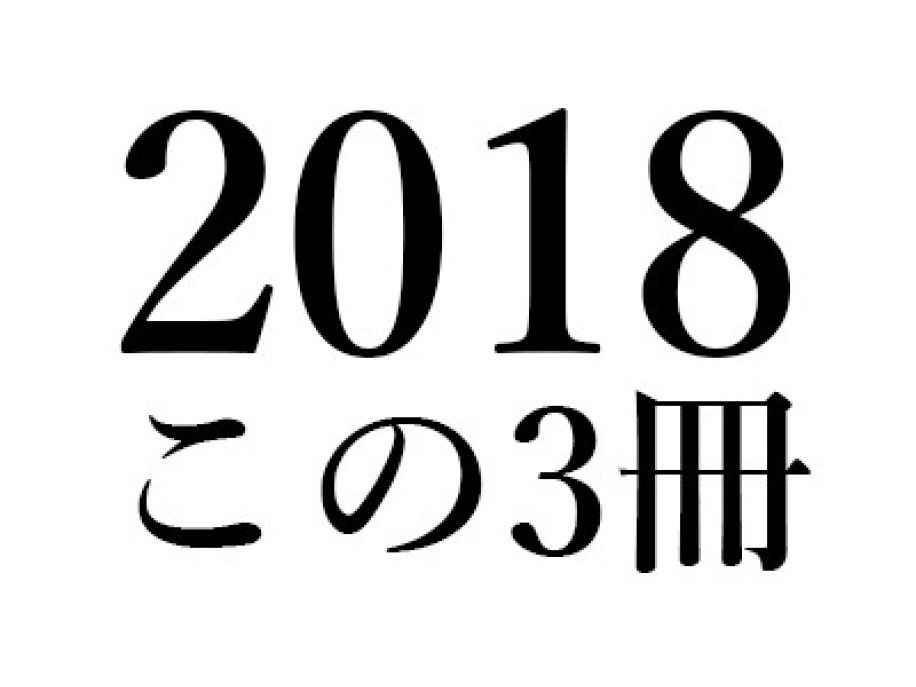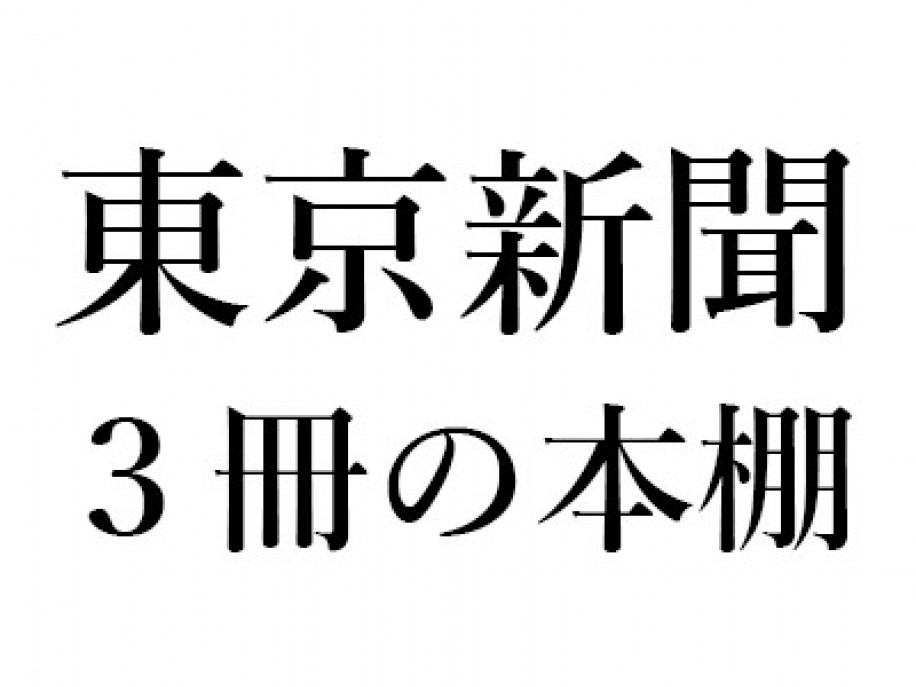書評
『頭のうえを何かが Ones Passed Over Head』(ナナロク社)
「生まれ直し」の壮絶闘病記
アーティスト、批評家の岡﨑乾二郎は、2021年10月30日、「ストローク」(脳梗塞)に襲われた。本書は岡﨑が脳梗塞の当事者として、完全な右半身麻痺から徐々に回復し、ついには自立歩行や作品制作が可能なレベルまで到達していく半年あまりの過程を「内側から」記述した壮絶な闘病記である。しかし、それはまた、ある種の歓びすらもたたえた「生まれ直し」の記録でもあった。本書の前半には、リハビリ一ケ月目以降に描いた色鉛筆ドローイングが収められている。最初は混乱していた線が次第に判別可能になっていき、やがて人物が、風景が、魚やドラゴンが姿をあらわしていく。絵の傍らに添えられた温かくユーモラスなキャプションは、回復の過程を傍らで見守りつつ伴走したパートナー、ぱくきょんみによるものだ。
本書を読みながら、評者はかつての岡﨑の著書に記されたさまざまなエピソードを思い出していた。
たとえば岡﨑はリハビリの過程で、「重力」の把握にかなりの苦労を強いられる。このとき「足裏が(中略)地面を捉えているという感覚」が非常に重要であり、それを通じて正しい重心、重力の方向を把握できる。この記述は、岡﨑が『抽象の力』(亜紀書房)で検討したフレーベルの教育メソッドを思い起こさせる。玩具を用い事物と身体の協働を通じて諸々の感覚要素が大きな全体的秩序に連なっていくプロセスを把握させるという意味で、そのメソッドは抽象芸術に影響を与えた。リハビリに話を戻すなら、ここではたらく「抽象の力」とは、まさに足裏と地面の協働を通じて、「重力という観念」が抽象化されていくプロセスそのものではないか。
さらに興味深いのは、こうしたプロセスが、しばしば意識や意図とは無関係な形でやってくるという点である。例えば岡﨑は、長らく自力での入浴に苦労していた。しかしある時、なんの前触れもなく浴槽をひょいとまたぐことが可能になった。そうした変化について岡﨑は次のように記す。「自分の意思を身体が追い越していて、その身体の教えを受け容れて、それを自分の精神、身体として遅れて内面化していくという感じでしょうか。つくづくリハビリは自分自身を組み替える経験だと思います」と。
してみると、リハビリにおいて回復は、身体と事物の協働において生じ、意識や言葉はそれを遅れて記述し理解するということになる。恐らくこれはリハビリに限った話ではない、あらゆる回復や成長のプロセスにおいて、こうした不連続性は決定的な意味を持つのだ。
そうした不連続性の最大のものが、「ストローク」後の岡﨑に起きた驚くべき変化にも見て取れる。制作する作品数が格段に増え、かつてないほどの大作を制作することも可能になったのだ。この変化から私は、かつて岡﨑が『ルネサンス 経験の条件』(文春学藝ライブラリー)に記していた、「グラッソ物語」のエピソードを連想せずにはいられなかった。友人たちのたくらみで別人として扱われた職人グラッソは、その後ハンガリー行きを決断して大きな富を得る。アイデンティティが再定義されることがもたらす創造性こそは、ストロークが岡﨑にもたらした「恩寵」にして「深い教え」だったのではないか。
ALL REVIEWSをフォローする