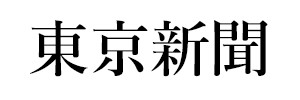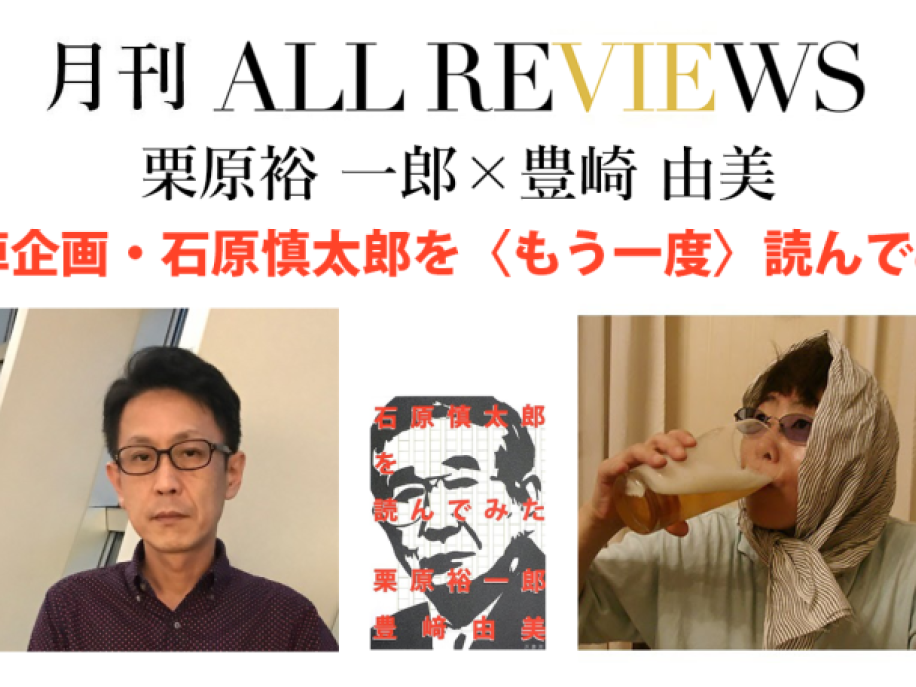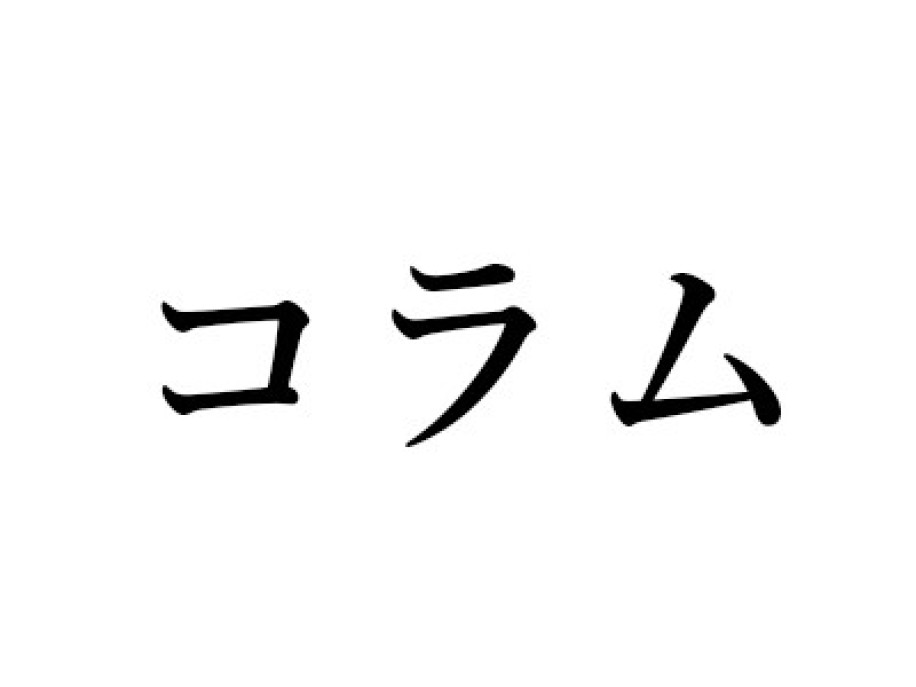読書日記
速水 健朗ほか『バンド臨終図巻』(文藝春秋)、三島由紀夫『行動学入門』(文藝春秋)、寄藤文平『死にカタログ』(大和書房)
終わりあっての生き方
SMAP解散問題にスポットライトが当たった、2016年の暮れ。形あるものは必ず壊れゆくということで、SMAPの解散についても記される<1>速水健朗ほか『バンド臨終図巻』(文春文庫・1,058円)の巻頭言は、「祇園精舎の鐘の声…」という、平家物語の冒頭部分。本書には、国内外の様々なバンドの解散の経緯がひたすら記されます。共に夢を追い、成功を掴(つか)んだバンドであるからこそ、次第に愛だの憎だの金だのが絡まり合って離れていかざるを得なくなる様は、哀(かな)しい。「音楽性の違い」というバンド解散時の紋切り型理由の背景には、かくも様々なドラマがあるのです。
読み続けるうちに感じるのは、まさに「無常」。SMAP解散にショックを受けているファンも多いと思いますが、この本はそんな人にとって無常を受け入れるための一助となるかもしれません。
何事にも終わりがある、ということを受け入れることに苦労する我々。しかし終わり方にこそ「美」がある、と見た三島由紀夫は、「おわりの美学」というエッセイを連載したことがありました。<2>『行動学入門』(文春文庫・518円)に収められているのですが、「美貌のおわり」「旅行のおわり」「礼儀のおわり」等、短く軽い作品ながら、終わり方を通して、ふと自らの来し方を考えさせられます。
その中にしばしば登場するのは、死のモチーフ。何かを美しく終わるためには、美しい死を選択するしかない。…という筆致は、著者の死に様を知る我々をドキリとさせるのです。
<3>寄藤文平『死にカタログ』(だいわ文庫・702円)は、まさに「死」のカタログ。イラストレーター、デザイナーである著者が、世界各国の「死んだらどうなるか」についての考え方や、東西著名人の人生と死に方等を、視覚化していきます。
人生の終わりである死に対して私達が恐怖や不安を感じるのは、死ぬ時、そして死後、自分がどうなるのか把握できないから。しかし本書では、寄藤さんならではの乾いた絵柄で死の世界が図解されており、「こんな感じかも」と腑(ふ)に落ちるのです。
死について考えることは、生きることを考えることでもある、と伝えるこの一冊。一年の始まりに「終わり」について考えることもまた、一年をよりよく生きることにつながるかもしれません。
ALL REVIEWSをフォローする