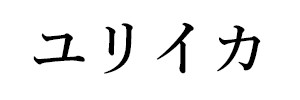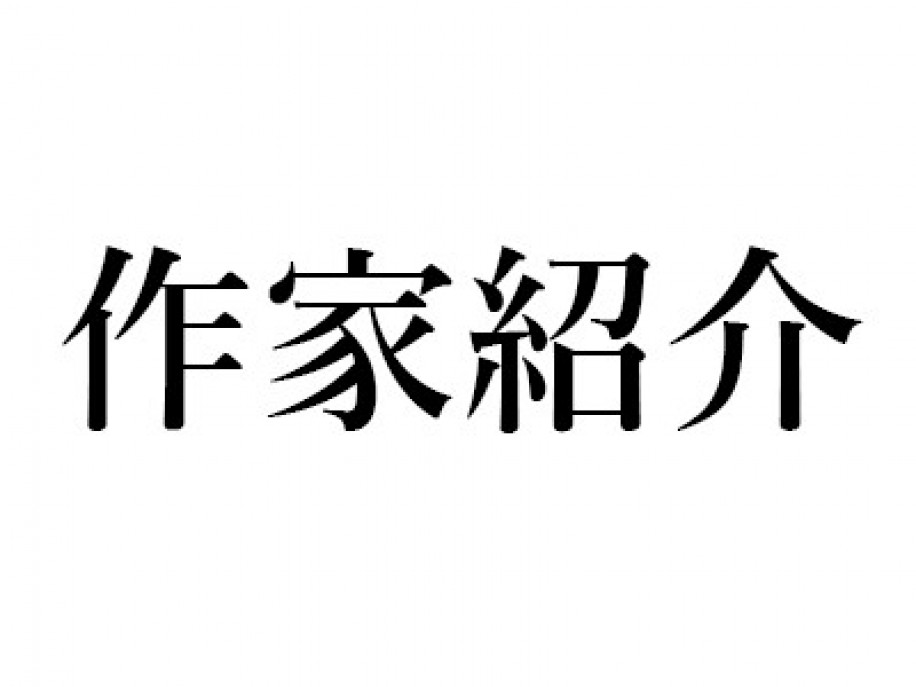作家論/作家紹介
リチャード・バーギン『ボルヘスとの対話』(晶文社)、マリオ・バルガス=リョサ『嘘から出たまこと』(現代企画室)、マリオ・バルガス=リョサ『果てしなき饗宴』(筑摩書房)
フォークナーとラテンアメリカ文学
I
ケンブリッジを訪れたボルヘスと対話を行なったリチャード・バーギンは、その記録を『ボルヘスとの対話』という本にまとめている。その序文で彼は、次のように述べる。そうして私たちは話しはじめた。十五分とたたないうちに、私たちはフォークナー、ホイットマン、メルヴィル、カフカ、ヘンリー・ジェイムズ、ドストエフスキー、そしてショーペンハウアーの話をしていた。(柳瀬尚紀訳)
ところが、彼が会話をテープに採り始めるのはその後であり、しかも記録として残っているテクストには、なぜかフォークナーの名がまったく出てこない。録音されなかった幻の会話で、ボルヘスはフォークナーについて何を語ったのだろうか。まっ先に話題になったと思われるだけに、余計気になるところだ。
わずか九歳で『幸福な王子』をスペイン語に訳したボルヘスは、その後、ヴァージニア・ウルフの『オルランド』、カフカの『変身』、ミショーの『アジアの野蛮人』といったモダニズム文学の重要な作品の翻訳を行なった。そして、一九四一年には、彼の手掛けたフォークナーの『野性の棕櫚』の翻訳が出ている。原作が発表されたのが前年であることを考えると、当時のボルヘスが、フランスで評価の高まったフォークナーに強い関心を抱いていたであろうことは想像に難くない。大橋健三郎氏の指摘するように、自分と同世代の作家であることによる共感や「モダニズムの面」の親近感から接近したということもあるだろう。「自伝風エッセー」によると彼は、当時図書館員として働くかたわら、休日になるとフォークナーやウルフの翻訳をしたという。
ところが、今日残っているボルヘス語録によれば、彼がフォークナーという作家に敬意を抱きながらも、その作品を好んだかどうかは疑わしい。自分が好む作家について述べた件で彼は、バーナード・ショウとフォークナーを対比し、その相違をこんな風に説明しているからだ。
私が好む作家はジョージ・バーナード・ショウです。彼とそれ以外の著名な現代作家の違いは、おそらく彼が英雄的な感覚を備えた唯一の作家であることだと思う。他の作家たちは、私が大いに感服しているウィリアム・フォークナーのように、下劣な状況や悪魔的環境を専門にしているようです。(J.M.プリエト編『ホルヘ・ルイス・ボルヘスの英知』※未訳)
たとえばならず者のうちにも英雄的精神を見出すように、ボルヘスが不純なものより純枠なもの、あるいは高貴なものを好んだことはいうまでもない。その意味で対照的なフォークナーの世界をボルヘスが好まなかったであろうことは十分想像できるのだが、この度機会あって訪れたブエノスアイレスで、晩年のボルヘスに連れ添ったマリア・コダマにボルヘスとフォークナーのことを訊いてみた。すると予想に違わず、彼女も同意見だった。ボルヘスがガルシア=マルケスの『百年の孤独』を読み(聴き)切れなかった理由も、そのあたりにありそうだ。
ところで、今、右に引用した一節が、フォークナーの作品の内容に触れているとすれば、次の一節はコルタサルを引き合いに出しながら、フォークナーの作品の形式もしくは構成について批評した言葉として興味深い。
私はコルタサルのある短篇をアルゼンチンで初めて認めたエディターであるという名誉を得ました……。彼のその後の作品もいくつか読みました。でも、短篇を中程から語り始めるといった類の不快な遊戯には魅力を感じません。それはすべてフォークナーの模倣だからです。しかも、非凡な人物であるフォークナー自身の作品においてすらその種のことは不快なのですから。(『ホルヘ・ルイス・ボルヘスの英知』)
さらに、次のような言葉を聞くと、フォークナーという作家に感服しながらも、そのすべてをボルヘスが認めていたわけではないとの印象を強くする。
フォークナーは農場主になることに固執し、自分は作家ではないと言っていた。彼を知った私の友人が、フォークナーは馬の話をしたがったと私に語った。そのとき私は心の中でこう思った。「変った人だ、私は馬のことは何も知らない、興味があるのは文学なのだ」と。(一九八四)(C.R.ストルティニ編『ボルヘス辞典』)(ALL REVIEWS事務局注:当該書籍確認できず)
もっともこのような語録では一般に文脈が無視される傾向があり、この『辞典』も例外ではない。そのため、ボルヘスの言葉にユーモアもしくはアイロニーを認めるべきなのか、それとも真摯な言葉として文字通り受け取るべきなのかは、にわかには決めがたい。彼がにこりともせずに冗談を言うことを、ぼく自身実際に知っている。
II
ところで、ボルヘスがコルタサルの短篇構成法にフォークナーの模倣を見出したという事実は、ラテンアメリカの現代小説の性格を考える上で、ひとつの手掛かりになるだろう。ボルヘスが言っているのが、物語のフラグメント化や時間の非直線的進行のことであるとすれば、彼が別の機会に指摘しているように、それはたとえばフアン・ルルフォがフォークナーに学んだ技法でもある。『ペドロ・パラモ』の舞台となる、死者がささめく町コマラを創造する上で、ヨクナパトーファが参考になっていることは明らかだが、この小説に生気を与えているのは、何よりもまずフォークナー譲りの構成法なのだ。そしてこの構成法が、ルルフォばかりでなく、実に多くのラテンアメリカ作家に霊感を与えていることは問違いない。それはこの構成法が、アメリカ深南部同様あるいはそれ以上に混沌としているラテンアメリカの現実を表現するのにきわめて適していると、多くの作家たちが考えたからだろう。
学生だったガルシア=マルケスが、ボルヘス訳の『変身』から魔術的リアリズムのテクニックを学んだとしても、それをラテンアメリカの現実に適用するには、フォークナーを読むことにより、「土地」を発見し、構成法をマスターする必要があった。したがって、彼より先にフォークナーを消化吸収したルルフォの作品は、格好のモデルとなったはずだ。
ここで思い出すのが、バルガス=リョサがそのフォークナー論「サンクチュアリ――悪の聖域」(『嘘の真実』所収)で引いている、アンドレ・マルローの言葉である。それは一九三三年、マルローがフランス人にフォークナーの小説を紹介する際に用いたという「探偵小説のギリシア悲劇への接木(インセルシオン)」という表現だ。これがルルフォやガルシア=マルケスの作品、とりわけ『ペドロ・パラモ』、『落葉』、『予告された殺人の記録』の性格を言い表わす言葉にもなっている。まだ見ぬ父親、医師の自殺の原因、娘の名誉を汚した犯人と、対象は異なるが、いずれも「探し求める」という探偵小説の構造を持ち、大衆小説的性格を備える一方で“ソフォクレス”が意識されており、そのためにジャンルの闘争を孕んだ「文学」となりえている。
面白いのは、フォークナーの特徴を分析把握しながら、バルガス=リョサ自身は『誰がパロミノ・モレーロを殺したか』という探偵小説を書くに当たり、構成面ではフォークナーを継承しながらも他の二人とは異なり、ギリシア悲劇を導入してはいないことだ。そのため、現実を加工しながらも、彼の小説は自身の言う「現実的現実」にきわめて近いレベルに踏み止まることになる。言い換えれば、彼の小説はその構成に大きく頼っているということを意味する。
おそらくそのためだろう。彼は先に挙げたフォークナー論において、形式の重要性を強調して次のように述べている。
あらゆる小説において、その物語が豊かなものになるか貧弱なものになるか、深遠なものになるか下世話なものになるかを決定するのは、形式――その小説が書かれる文体と語られることが現れる順序――である。しかし、フォークナーのような小説家の場合、形式はきわめて可視的で、語りのうちにはっきりと存在しているために、それ自体が主人公に代わり、骨と肉を備えたもう一人の登場人物として行動したり、挿話中の情熱、犯罪あるいは天変地異と同様「出来事」の形を取ったりする。
(ALL REVIEWS事務局注:本稿ではバルガス=リョサ『嘘の真実』)
III
評論『果てしなき饗宴』で自ら語っているように、バルガス=リョサは小説を書き出したころ、フロベールを初めとするフランス文学に傾倒している。しかし、ペルーの「現実」をダイナミックに描き出そうとするとき、西欧的ブルジョア社会を扱う方法だけでは不足だったはずだ。まして同国の前世代の作家たちの写実主義的リアリズムによってその「現実」を捉えることなど不可能である。つまり彼が言うように、マニアックなまでに写実的であっても、「完全に書かれた」小説など存在しないのだ。したがって、「あらゆる小説は物語の一部を語り残し、読者の純然たる推測か空想に委ねる」ことになる。そして彼によれば、『サンクチュアリ』における形式の効果は、クロノロジカルなデータの順番を乱したり、それを消し去ることにより、語り手が読者に対して隠してしまうものに負っているという。バルガス=リョサのフォークナー論は、短いながら、彼のフロべール論と同様、自らの作品についての考察として読める点でも興味深いのだが、次の一節などは、まさに彼自身の小説の手法として読むことが可能だろう。
語り手は「決して」我々にすべてを語らず、しばしば我々を惑わす。すなわち、ある登場人物が行なうことは明示するが、考えていることは明示しない(たとえば、ポパイの私生活を明らかにはしない)か、あるいはその逆であり、予め我々に知らせることなく身振りや行為、思考を飛び越えてしまう。そして、後になって、消えたハンカチを突然取り出して見せる手品師のように、びっくりするような方法でそれらを示して見せるのだ。
『野性の棕櫚』でフォークナーが用いた二重小説の手法の影響はともかく、『都会と犬ども』にせよ『緑の家』にせよ『ラ・カテドラルでの対話』にせよ、バルガス=リョサの重要な作品において右に引用した文の中で彼が語っている手法が効果を挙げていることは言うまでもない。
また形式あるいは構成法ということで言えば、コルタサル、プイグ、ガルシア=マルケスがフォークナーから学んだ手法が、彼らの小説を通じて、ウォン・カーウァイの映画にまで受け継がれている。それはつまり、フォークナーという方法が、非ヨーロッパの現実を描く時により有効性を発揮するということなのだろう。フォークナーという分光器は、彼の影響を受けた作家たちの特性を浮び上がらせて見せる一方、それを逆向きに用いたとき、作家たちの多様性の中に存在する共通性を浮び上がらせもする。その共通性こそ、フォークナーの影に他ならない。
ALL REVIEWSをフォローする