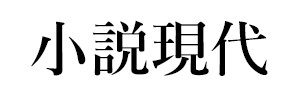コラム
渋沢 青花 『世界ふしぎめぐり』(偕成社)、「月刊みんぱく」編集部『100問100答 世界の民族 生活百科』(河出書房新社)、長 新太、野村 雅一監修『世界のあいさつ』(福音館書店)、小松 義夫『地球生活記』(福音館書店)
世界をぐるりと
子どもの頃うちにあった本で、気に入っていたのが、『世界ふしぎめぐり』(偕成社)だ。三年までの「学年別おはなし文庫」というシリーズに入っていて、それぞれの学年向けに『理科なぜどうして』『日本のむかし話』など二十冊あるが、いちばん夢中になったのは、この『世界ふしぎめぐり』だった。世の中には木に上る魚がいること、虫をつかまえる植物のあることを、その本で知った。年々少しずつ傾くピサの斜塔、死海と名がつくのに沈んで溺れることのない湖、群れをなして崖から次々落ちるまで集団で行進を続けるレミングというネズミの話。すべてそれで読んだ。
溜め息をついて思うのは、
(世界は広い)
ということ。ふだんの自分の生活からは想像のつかないことだらけだが、作り話ではなく、確かにあるのだ。
甥っ子が小学校に上がったとき、まっ先に読ませようと思いついたのも、その本である。書店に行ってみたら、なんと、背表紙も昔のままだったから、驚いた。挿し絵も見覚えのあるものばかり。
「うわー、なつかしい」
贈り物用に買ったことも忘れて、読みふけった。奥付によれば、一九五八年に刊行されてより、版を重ねているロングセラーだ。
一年生向けともなると、さすがに字が大きくて、文章も長々とは展開できない。そのためか、導入がすごく急なのだ。
うみよりも りくちの ほうが ひくい くに。そんな ところが あるでしょうか。ありますよ。よーろっぱの おらんだと いう くにです。
おうちを もって あるけたら、べんりでしょうね。ありますよ、あふりかに。
前ふりからすぐタネあかしになる。大人の本なら、もうワンクッションかツークッション置きたいのだろうが、そこが一年生の限界か。
「早いんだよ、本題に入るのが」
げらげら笑っているうち、あっという間に読み通した。
出てくる話は、もはや私には未知ではないにもかかわらず、やはり面白かった。庄司浅水が世界の奇譚を集めた本を、たまに読みたくなるのと同じだ。はるかな国の自然や事物に対する、初々しいとも言える好奇心が、自分の中に残っているのを、確認できるからだろうか。
『世界ふしぎめぐり』の大人版とも言えるのが「月刊みんぱく」編集部編『100問100答 世界の民族 生活百科』(河出書房新社)。大人向けとあって、質問も「インドの女神シャクティはどういう神か」など難度が高い。
一方で、問いの立て方から正解が予想できてしまうものも。「ヨーロッパにも日本のナマハゲのような行事があるのか」の項なんて、答が「ない」だったら、一行で終わってしまうものな。
「月刊みんぱく」は国立民族学博物館の広報誌だ。執筆者は、すぐれた研究者ばかり。それぞれの項は短いけれど、中身がぎゅっと詰まっている。
長新太著、野村雅一監修『世界のあいさつ』(福音館書店)は、図書館的に言えば、子ども向けの絵本になるが、大人もじゅうぶん楽しめる。野村雅一著『身ぶりとしぐさの人類学』(中公新書)と併せて読むと、さらに思いが広がる。
前にロシアで、現地駐在の日本企業の事務所長を訪ねたことがある。そこに至るまでも、ロシアのいろいろな人と会い、挨拶を交わしてきたので、その延長で彼とも握手を交わしたのだが、握ってからおたがい、
「?」
と目を見合わせた。ロシアでは握手がごく自然だから、「郷に入らば郷に従え」で彼も日常的にしているのだろうが、その地においてでさえ、日本人どうしだと違和感を覚える。この本のサブタイトル「身体がしめす社会の記憶」には、まさに、
「言い得ている」
とうなずいた。
しぐさと言えば、私は子どもたち(どうかすると、いい大人も)が、写真を撮られるとき中指と人差し指をVの字に立てて突き出すのを、かねてより苦々しく思っていた。あれをすると、皆が無個性に、言い方は悪いが、バカに見える。
いつだったか新聞に、インドネシアの、たしかバリ島だと思うが、日本人の家族連れの観光客が落としたフィルムが無事戻る、といった美談が紹介されていた。
「どうして日本人とわかったんですか?」
との問いに現地の人は、
「写真をとるときこういうポーズをするのは、日本人の子どもしかいない」
と答えていた。記事を読んで私は、
「国際的な恥だ」
と顔を赤らめていたのだ。
本書によれば、ピースサインは、一九六〇年代のベトナム戦争中、アメリカのヒッピーや反戦運動家からはじまったそうだが、いまだ「ピース!」とやっているのは、世界広しといえども日本人だけだろう、と。
一方で、なぜそれほど定着したか、私なりに考えるところがあった。
写真を撮るとき、私たちは手をどうしようと迷い、困惑する。著者によれば「人間の手も指もあまりに表現的なのである」「過剰な意味作用が人間のからだをわざとらしく、ぎこちないものにしてしまう」。
日本人はだいたい、そういうとき両手を前で重ねるのを常としてきた。が、経済的に豊かになり、スナップ写真を撮る機会が増えると、「それではあまりに堅苦しい」となり、代わりにピースサインが採用されたのではないか。語り過ぎる手を、型にはめておさえるための、新たな、そして現代的な「黙する」ポーズなのである。
そう理解できるが、著者は何と言うだろう。
小松義夫著『地球生活記』(福音館書店)は「世界ぐるりと家めぐり」のサブタイトルどおり、アフリカの奥地からニューヨークの摩天楼まで、住まいを訪ねた写真集。タイトルがけっして誇張に感じられないビッグな企画と取材力と、人々の暮らしをみつめるこまやかな視点とが合わさった、千七百余点に圧倒される。
ぷかぷか浮かぶ筏(いかだ)の家、屋根の上がすなわち通りとなっている街、掘削機で掘るだけで部屋や収納スペースをいくらでも増やせる地下の家(しかもそこに、コンピューターやホーム・バーがある)など、日本の「家」の固定観念を裏切って快い。
人間の文化、習慣の多様性を改めて感じるとともに、
「地球は狭くなったとはいえ、まだまだ、よその国の人のことを知らないな」
と頭を垂れたいような、謙虚な気持ちになるのだった。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする