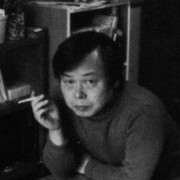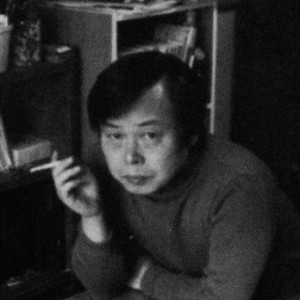書評
『江戸の悪霊祓い師(エクソシスト)』(筑摩書房)
マダム・キラーの悪霊祓い
下総国羽生村、鬼怒川ぞいの寒村で、十四歳の少女妻菊が突然床に倒れて口から泡をふき、夫や父親がおどろいて駆けつけると、父に向かって形相もすさまじく、「我は菊にあらず、汝が妻の累(かさね)なり」とわめきたてた。聞けば、菊の父与右衛門は前妻累を殺して鬼怒川に投げ込み、そしらぬ顔をして後添いの妻六人を迎えたが、六人とも累の怨念にタタラれて次つぎにとり殺された。それでも怨みは晴れず、いまこうして菊のからだをかりてうらめしやと現れたのだという。菊はからだのなかに別人格が入ってのたうちまわる。祈祷師を呼んでもせせら笑って受けつけない。名主が問答して一時は退散するが、二度三度とまた出てくる。三度目に隣村飯沼村の飯沼弘経寺(ぐきょうじ)の所化僧祐天が、悪霊に巧妙な誘導尋問をかけてようやく除霊に成功する。これで終わりではない。また出た。今度は童子霊が出た。先代与右衛門が助(すけ)という連れ子を川に流した。その水死霊が菊のからだをかりて出たのだ。
土佐浄瑠璃や歌舞伎でおなじみの怪談累の原話である。実在した事件で、寛文十二年(一六七二)正月二十三日が菊狂乱の最初の日付である。しかし本書の主人公は、かならずしも菊でもなければ、怨霊累でもない。菊三度目の狂乱のときに調伏しにきた祐天、これが表題の「江戸の悪霊祓い師」だ。飯沼弘経寺の住職檀通上人に従って当地に滞在していたこの浄土宗の学僧は、のち五十歳ごろ教団をはなれて在野の布教活動に携わり、それから異例の抜擢をうけて、浄土宗の最高機関芝増上寺の住職の座についた。将軍綱吉の母桂昌院のお声がかりだった。
水死霊の続出した羽生村事件は、鬼怒川の治水、したがって江戸への水運開通と、それにともなって起こる中世的村落共同体の崩壊の結果である。徳川体制の都市論的基礎固めのために肥大化してゆく江戸のかげに、死産流産してゆく後背地寒村のドラマを要約している。一方、羽生村の水死霊調伏(水子供養)に味をしめた祐天は江戸へ出て、人妻たちの安産願望や堕胎の後始末につけ込んでフロイト博士のような辣腕のマダム・キラーとなり、死産流産の不安に悩む大奥の側室たちに取り入って出世街道をばく進してゆく。といっては要約が単純にすぎよう。まさに累(かさね)のように重層的に複合する江戸の深層が、一枚一枚めくられてゆくミステリー怪談としての学術読みもの。
【この書評が収録されている書籍】
朝日新聞 1991年3月10日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする