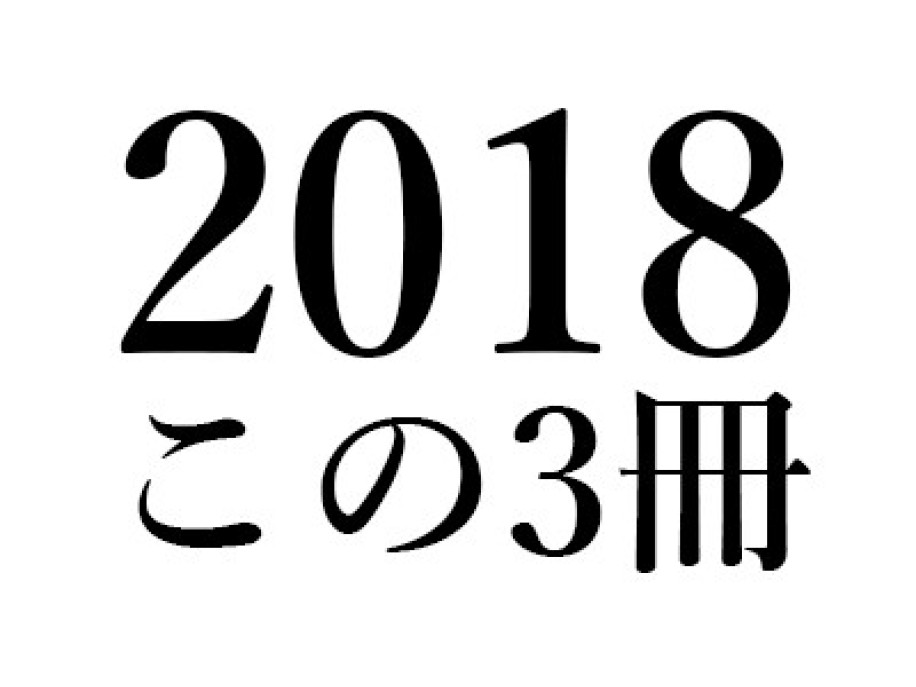書評
『線量計と奥の細道』(幻戯書房)
私たちはなにを学んだのか
貴重な記録である。東日本大震災の翌年、二〇一二年八月のことだが、ドリアン助川は、こつこつ勉強していた松尾芭蕉の『奥の細道』を実地にたどってみようと思い立った。「細道」のコースの多くは大震災の被災地とかさなっている。おりしもへんな状況が生じていた。大震災にともなう原発事故で甚大な被害を受けた福島県をめぐり、「どういうわけか忘却が起きた」。深刻な事態は急速に解決に向かっており、除染がすすめば、避難先の人も町に戻ってくる。農産物の風評被害もいずれ収束する。復興五輪こそ「美しい日本」にふさわしい――。
ことあるごとに美文調で詩的に見たがる芭蕉には、何事にもリアリストの曽良がつきそっていたように、平成の風狂人には徹底して機能的な放射線量計がおともをした。パトロンのいる俳聖とちがって、こちらはしがないもの書き、小舞台のライブ演者、朗読家であって、旅は折り畳みの自転車とした。月に一週間ほど奥の細道。折り畳んで列車で戻り、翌月、前回の旅で中止した地点まで運んでもらって、そこから再びペダルを漕(こ)いで行く。
日光で芭蕉は「あらたふと青葉若葉の日の光」と透明な陽光をたたえたが、「薬師堂 杉のそば 0・33マイクロシーベルト」と出た。観光客は通過するだけだが、東照宮の関係者はずっといるしかない。年間なら0・33×24×365=2・89ミリシーベルトの線量のなかで暮らす。日本政府の定めた線量限度、年間1ミリシーベルトをはるかにこえている。継続的な低線量被曝(ひばく)から何が生じるか。チェルノブイリの先例が示している。
夜は、なるたけ安いビジネスホテル。居酒屋の夕食。朝はコンビニのサンドイッチ。五十男に長い坂を漕ぎ上がるのは地獄の沙汰のように辛(つら)いのだ。そんなとき、幼いころ殺処分寸前の犬を飼っていたことを思い出した。生まれつき尻尾(しっぽ)のない犬で「メグ」と名づけた。少年が走ると、メグは「ハア、ハア」いいながら走ってきた。その吐息を地獄の坂道で聞いた気がして、自転車を「メグ号」と名づけた。この本には、全篇(ぜんぺん)にわたり、著者の心のゆたかさ、やさしさがしみ通っている。
栃木県那須高原。農園での線量測定を怠っていた。牧牛を放棄したご夫婦に会ったばかり。気持ちをとり直して線量計を差し出す。とても高い数字が出た。「那須 国道4号沿い 0・52マイクロシーベルト」
農家は深刻な汚染はわかっていても、出て行くことができない。農地は除染されても、基本的に山野は除染不可能だから、雨とともに拡散していく。
県庁所在地、福島市のど真ん中、信夫山の展望台、1・34マイクロシーベルト。年間だと、およそ11・7ミリシーベルト。「線量の数値にあまり驚かなくなってきている。だが、さすがに『え?』と声が漏れ出た」
最終章「その後」に報告してある。由緒ある信夫山の山頂が削り取られていた。放射性物質を剥ぎ取るには、禿(は)げ山にするしかないからだ。信夫山は一つの広告塔であって、ほかの山は無視するか忘れるしかない。オリンピックという「仮想繁栄」を設定した国らしいやり方ではないか。
出るはずのない数値が出たとしても、口をつぐんでいるしかない人々。深いいたわりのなかで逡巡(しゅんじゅん)の六年間がはさまった。神戸淡路、中越、東日本、熊本、大阪北部……。強烈な地震があいつぐなかで、つぎつぎと原発再稼働のお墨つきが出る。「……私たちはなにを学んだのか。危機はすぐ目の前にある」
ALL REVIEWSをフォローする