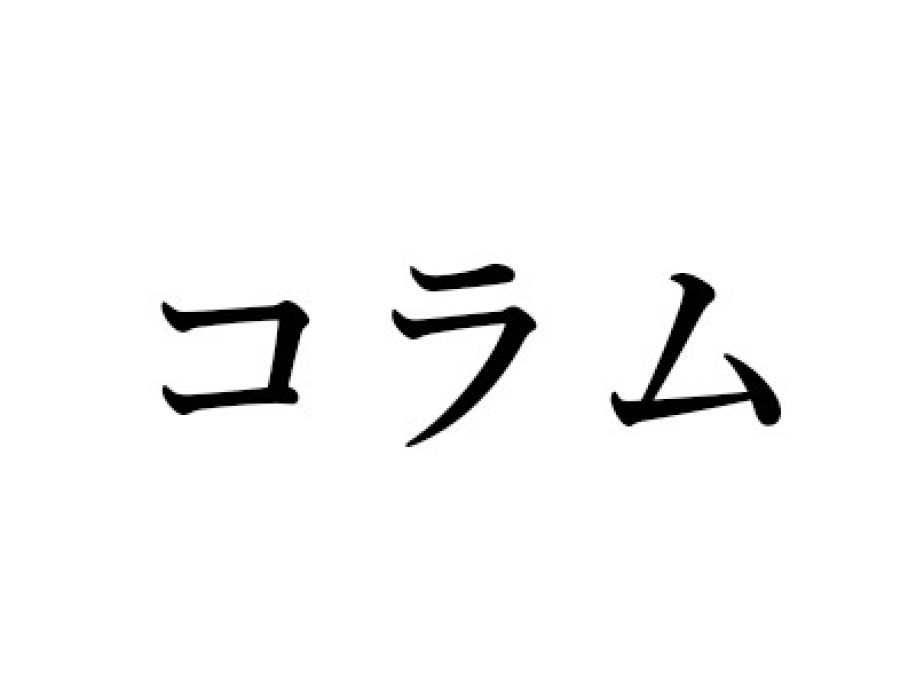書評
『銀狐抄』(新潮社)
夢と夢のあいだに語られる物語
安政年間からつづく祇園のお茶屋「あげまき」。この店を支えてきた女たちの生の連鎖を描く宮本徳蔵『銀狐抄』は、現在の女将である琴子を中心に、噎(む)せるような女の町を典雅な筆致でたどりつつ、切り売りすれば隙のない短篇に仕あがったはずの素材を惜しげもなくつぎこんで、あえて豪奢に押してみせたまことに贅沢な作品だ。アメリカの富豪に莫大な金で落籍(ひか)されてニューヨークに渡り、戦後をパリに暮らして帰国した曾祖母の雪子、戦犯に挙げられた元首相、鹿ヶ谷侯爵の自害を追ってみずからも喉を掻き切った祖母の佐用子、西洋人風の顔だちで、シモーヌ・シモンやフランス映画の「肉感女優、フランソワーズ・アルヌール」に似ているといわれた美女であるにもかかわらず、廓の掟に反して冴えない男と駆け落ちしてしまった母の由李子、そしてどうやら先の侯爵の血を引いているらしい琴子。そこに琴子の幼馴染みや、岩之助、順吉と二代にわたって茶屋に通う骨董屋親子らが交錯していく。しかし彼女たちが織りなす物語を、女の愛だ業だとお決まりの文句で小綺麗にまとめてしまうより、曾孫の琴子とマンション暮らしをしながらパリの食生活を頑固に守り通す雪子の、仏語まじりの京都弁にこめられた細部の趣向を、まずは堪能すべきだろう。
たとえば雪子が「フランス語でいうたらビザージ・ド・ルナールや」と評される結婚相手と移り住んだパリの別邸はマレー地区にあって、由緒あるこの王家の街が二条城の裏に、お天子様の抱え画家「カンタン・ド・ラ・ツール」が狩野派に譬えられる。くわえて「ポンパドールの女御(にょうご)」を言うのに、小野小町でもかなわないとする対比のいかにものびやかな感覚は、まちがいなくこの小説の魅力のひとつである。エイの食べ方について蘊蓄(うんちく)を傾け、「パリの粋人は京と同(おんな)し舌を持ったはる。明るぅて暖(ぬく)い地中海より、マンシュというてエゲレスとの境の狭苦(せせこま)しい海で釣った小魚に目ェ剝くようなお銭(たから)を払うんどす。人かて魚かて、廃(ずる)けかけたとこがかえっておいしおすえ」と断ずるくだりの色彩と音楽などは、プルーストの登場人物が口にした台詞だといってもおかしくないほどだ。
各章を時間の早送りを用いて空白で接ぎ穂していくのも意識的な手法である。作者は祇園の女たちを実写するのでなく、妾執のうわずみだけを丁寧にすくい、あとは時間の経過に語らせている。人物と人物がかすかに重複し、謎の解明を求められぬままひとつの大きな輪舞を形づくっていく。女たちの横顔をもう少しふくらませてくれてもよかったのではないかとの不満を抑え込む、確かな技術がここにはある。
この技術の機軸が「夢」の活用にあることは、あらためて指摘するまでもないだろう。中心となる琴子だけでなく、登場人物はみな影絵のようにうごめいている。幼い琴子の前を狐面の男が横切る冒頭から、ながい夢の先触れは現われていたのだ。無視されているのを承知で店に顔を出した岩之助と由李子の関係、琴子への思いを遂げたその晩に順吉が味わういわれのない恐怖、月見の場面でやす子から雪子になされる驚くべき問いかけ。これらはいずれも確証を欠いて推測の域を出ていないのだが、それがかえって幻覚に似た後味を残している。
彼らは、もはや生身の人間ではない。物語の最後で琴子が出会う「逆立ちした姿で進んでくる」男女の群れや、むかしと変わらぬ「狐面の男」たちと同様、化かしあいに興じて踊る銀狐たちの仮の姿なのだ。夢と夢のあいだに語られる物語が、どうして現実でありえよう。この夢幻の状態こそ、『銀狐抄』をありきたりな情緒に沈む京都物から引き離し、宮本徳蔵をジュリアン・グラックやマンディアルグといった、夢の富に意識的なフランス作家たちと交感させている、最大の秘密なのだと言っておきたい。
【この書評が収録されている書籍】
図書新聞 1994年11月19日
週刊書評紙・図書新聞の創刊は1949年(昭和24年)。一貫して知のトレンドを練り続け、アヴァンギャルド・シーンを完全パック。「硬派書評紙(ゴリゴリ・レビュー)である。」をモットーに、人文社会科学系をはじめ、アート、エンターテインメントやサブカルチャーの情報も満載にお届けしております。2017年6月1日から発行元が武久出版株式会社となりました。
ALL REVIEWSをフォローする