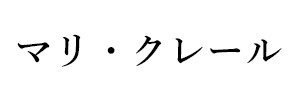書評
『恋の文学誌―フランス文学の原風景をもとめて』(筑摩書房)
考えてみれば、恋愛小説とか恋愛詩といったものは、じつに不思議なものである。そもそも、これは、誰が読むものとして書かれているのか。恋愛が現在進行形である男女はまずまちがってもこんなものは読まない。吉本隆明が『リテレール』第三号の『わが読書』でいっているように、「(純愛)小説は(純愛)行為の生々しさや、切実さにはとうてい叶わない」のである。
では恋愛経験のない読者が未来形として読むのかといえば、必ずしもそうとは言い切れない。とすると残りは恋愛過去形の読者ということになるが、恋愛小説の好きな爺さん婆さんなどというのはめったにお目にかかれるものではない。だが、現実には、文学というのは恋愛なしには存在し得ないものであり、文学=恋愛文学と言っても、決して言い過ぎではないのである。しかし、それにしては文学に描かれた恋愛を登場人物や作者に還元せずに、「描かれた恋愛」それ自体として考察した書物は、バルトなどを除くと意外に少ないと思っていたら、ここに待望の本が現れた。その名も、『恋の文学誌』である。
まず、本書は、本の中の恋愛を好む人にとりわけお薦めである、と言っておこう。つまり恋愛は好きだが読書は嫌いという人には無理で、必要条件として、恋愛はさておいても、本が何よりも好きでなければならない。だが、この条件をクリアしている人にとっては、本書は、一粒で二度おいしいグリコのようにお得なものとなるだろう。なぜなら本、つまりテクストを読むとはじつは恋愛をするのと同じことであり、恋愛をするとは実はテクストを読むのと同じであることが見事に語られているからである。
たとえばプルーストの『失われた時を求めて』の中で、スワンや語り手はオデットやアルベルチーヌという読み取りにくいテクストに出会って、困惑すると同時に真の姿を知りたいという激しい欲望を掻きたてられ、さまざまな解釈を試みる。しかし、テクストのほうは、それを察すると、よけい姿をくらまそうとする。あるいは逆に、テクストが確固たる姿であらわれると今度は読み手のほうが変化を強いられる。さらにまたテクストも読み手も共に変化して、その読書=恋愛は、複雑にもつれあう。というのも、テクストも読み手も(すなわち恋人同士が)、共に先行テクストの引用のモザイクからなる変幻きわまりないジェノテクストであるからなのだ(第III部「テクスト」)。しかしながら、こうした要約を掲げると、なんだ、また例のこ難しいテクスト理論か、と誤解される恐れがあるので、予(あらかじ)め言っておくが、本書は決してそのような味もそっけもないレトルト食品ではない。それどころか本当の学識とは、消化不良の難解さとは無縁の、馥郁(ふくいく)たる香りを放つ美味なる料理であることが理解されるはずである。
そのことは『トリスタンとイズー』から『ナジャ』に至る宿命の女性との出会いや恋の発端のプロセスを考察した第I部「恋」や書物の歴史と恋愛心理を重ね合わせた第II部の「書物」を読むだけでも十分に納得がいくと思うが、評者としては、Ⅳ部の「物語」をとりたい。そこでは、書物そのものに対する愛と結びついた著者のラテン的要素が、漸層法や撞着(どうちゃく)語法などの修辞学のレトリック、あるいは、精神分析のクリプト(地下聖堂)といった用語に滋味ゆたかな肉付けを施して、「恋はやがて物語としてのみ残り、その物語もいつしか衰弱し、消滅するという、もう一つの恋愛のプロセス」を巧みに浮き上がらせることに成功しているからである。
ところで、恋愛と読書は、確かに、著者のいうようにきわめて類似したプロセスを経ていくものだが、両者が示す「切迫」の度合は、やはり決定的に異なる。その点は、著者も十分に意識的で、本当の恋愛の切実さは、恋情を語ろうとするものから言葉を奪うという絶対的真理も「恋文の話」や「至福の表現」の章にはちゃんと書き留められている。つまり、究極の恋愛のテクストとは、あなたが好きだということを九官鳥のように繰り返すおよそ面白味のない恋文ということになるのだが、とするなら本書が抜群におもしろいのは、恋愛について語ったテクストを語るという、恋愛の切迫性からできる限り遠ざかったところにポジションを設定しているからなのかもしれない。こうした高級な本は、恋愛現在完了形ぐらいの成熟した読者にこそふさわしい。
【この書評が収録されている書籍】
では恋愛経験のない読者が未来形として読むのかといえば、必ずしもそうとは言い切れない。とすると残りは恋愛過去形の読者ということになるが、恋愛小説の好きな爺さん婆さんなどというのはめったにお目にかかれるものではない。だが、現実には、文学というのは恋愛なしには存在し得ないものであり、文学=恋愛文学と言っても、決して言い過ぎではないのである。しかし、それにしては文学に描かれた恋愛を登場人物や作者に還元せずに、「描かれた恋愛」それ自体として考察した書物は、バルトなどを除くと意外に少ないと思っていたら、ここに待望の本が現れた。その名も、『恋の文学誌』である。
まず、本書は、本の中の恋愛を好む人にとりわけお薦めである、と言っておこう。つまり恋愛は好きだが読書は嫌いという人には無理で、必要条件として、恋愛はさておいても、本が何よりも好きでなければならない。だが、この条件をクリアしている人にとっては、本書は、一粒で二度おいしいグリコのようにお得なものとなるだろう。なぜなら本、つまりテクストを読むとはじつは恋愛をするのと同じことであり、恋愛をするとは実はテクストを読むのと同じであることが見事に語られているからである。
たとえばプルーストの『失われた時を求めて』の中で、スワンや語り手はオデットやアルベルチーヌという読み取りにくいテクストに出会って、困惑すると同時に真の姿を知りたいという激しい欲望を掻きたてられ、さまざまな解釈を試みる。しかし、テクストのほうは、それを察すると、よけい姿をくらまそうとする。あるいは逆に、テクストが確固たる姿であらわれると今度は読み手のほうが変化を強いられる。さらにまたテクストも読み手も共に変化して、その読書=恋愛は、複雑にもつれあう。というのも、テクストも読み手も(すなわち恋人同士が)、共に先行テクストの引用のモザイクからなる変幻きわまりないジェノテクストであるからなのだ(第III部「テクスト」)。しかしながら、こうした要約を掲げると、なんだ、また例のこ難しいテクスト理論か、と誤解される恐れがあるので、予(あらかじ)め言っておくが、本書は決してそのような味もそっけもないレトルト食品ではない。それどころか本当の学識とは、消化不良の難解さとは無縁の、馥郁(ふくいく)たる香りを放つ美味なる料理であることが理解されるはずである。
そのことは『トリスタンとイズー』から『ナジャ』に至る宿命の女性との出会いや恋の発端のプロセスを考察した第I部「恋」や書物の歴史と恋愛心理を重ね合わせた第II部の「書物」を読むだけでも十分に納得がいくと思うが、評者としては、Ⅳ部の「物語」をとりたい。そこでは、書物そのものに対する愛と結びついた著者のラテン的要素が、漸層法や撞着(どうちゃく)語法などの修辞学のレトリック、あるいは、精神分析のクリプト(地下聖堂)といった用語に滋味ゆたかな肉付けを施して、「恋はやがて物語としてのみ残り、その物語もいつしか衰弱し、消滅するという、もう一つの恋愛のプロセス」を巧みに浮き上がらせることに成功しているからである。
ところで、恋愛と読書は、確かに、著者のいうようにきわめて類似したプロセスを経ていくものだが、両者が示す「切迫」の度合は、やはり決定的に異なる。その点は、著者も十分に意識的で、本当の恋愛の切実さは、恋情を語ろうとするものから言葉を奪うという絶対的真理も「恋文の話」や「至福の表現」の章にはちゃんと書き留められている。つまり、究極の恋愛のテクストとは、あなたが好きだということを九官鳥のように繰り返すおよそ面白味のない恋文ということになるのだが、とするなら本書が抜群におもしろいのは、恋愛について語ったテクストを語るという、恋愛の切迫性からできる限り遠ざかったところにポジションを設定しているからなのかもしれない。こうした高級な本は、恋愛現在完了形ぐらいの成熟した読者にこそふさわしい。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする