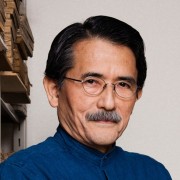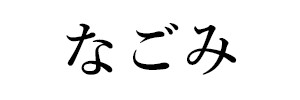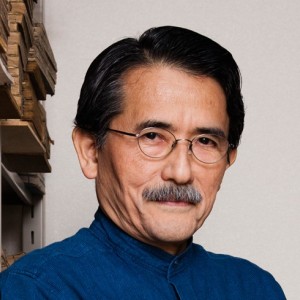書評
『ペンネームの由来事典』(東京堂出版)
随時随所の読書に
伝記というものを好むのは、私の性であって、こればかりは、どうしてだとも言いようがない。しかし、いやしくも歴史上に名を残したほどの人が、いかにして人となり、いかなる行跡をあゆみ、ついにいかにして死んだかという消息を知ることが面白くないわけはない。紀田順一郎さんの書いたものを、私はとりわけまた好む。格物致知というか、どこまでも実事を明らかにして、その実を以て語らしむという風な強さがあるからである。それは、あたかも、森鷗外の『澀江抽齋』に代表される所謂史伝ものの面白さにも通じるであろう。
そんなわけで、つい最近出たこの『ペンネーム事典』を一読、その面白さにたちまち虜となった(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2001年)。
本書の巻末に、著者の筆になる「日本ペンネーム考」という小論が付されているが、そこに、およそペンネームというもののもつ属性はあまねく論じられているから、これも是非一読の価値がある。
夏目漱石といい、森鷗外といい、北村透谷といい、北原白秋といい、その号(ペンネーム)の由来はなにかと聞かれて、すぐにすらすらと答えられる人はまずほとんど絶無であろう。しかし、かれらの著作が興味津々であるのと同じくらい、その号の由来もまたあっと驚く面白さである。実は、私自身、年来鷗外の愛読者でありながら、その号「鷗外」が、友人で解剖学者の斉藤勝壽が漢詩を読むときに使っていた号を、無断で拝借してそれきりになったものだとは、ついぞ知らなかった。まあ、これにも幾つかの異説があるとも書いてあるが、この暢気な由来がいちばん鷗外にふさわしいような気がする。
かくのごとく、およそどの項目を見ても、ほほぉ、と横手をうたぬことがないくらい、意外なことでペンネームというものが決まっているのである。
結局、一つの名前を名乗るということについては、それが肯定的な意味にせよ、否定的な意味にせよ、本名に対する微妙な思いがあるわけで、つきつめれば、その号・ペンネームを論ずることは、その人の人生を論ずることに限りなく近づいていく。だから、この「事典」は、結局のところ、単なる事典ではなくて、まったく古今伝記集成の観を呈している。それが、紀田さん独特の、エスプリ溢れる筆致で、飄々と書き進められるので、読むほうはいかにも面白く感じられるのである。
しかも一人あたりの文書量はおのおの一ページ前後の短いものなので(古今名士の一生をそのくらいのサイズにまとめるというのは、非常に筆力を要するが、その点、本書は短かい散文のお手本といってよい)、随時、どのページでも好きなようにめくって、あれこれと散歩でもするように読まれるとよい。五分なら五分の、一時間なら一時間の、それぞれの読書の醍醐味が味わわれるであろう。ちなみに、私はかつて「澤嶋優」というペンネームで幾許かの小説をものしたが、この由来は、ははは、当時K書店の担当編集者が澤嶋優子という人で、私はこの人を大変好きであったから、ちょいとその名前を拝借したのである。
ALL REVIEWSをフォローする