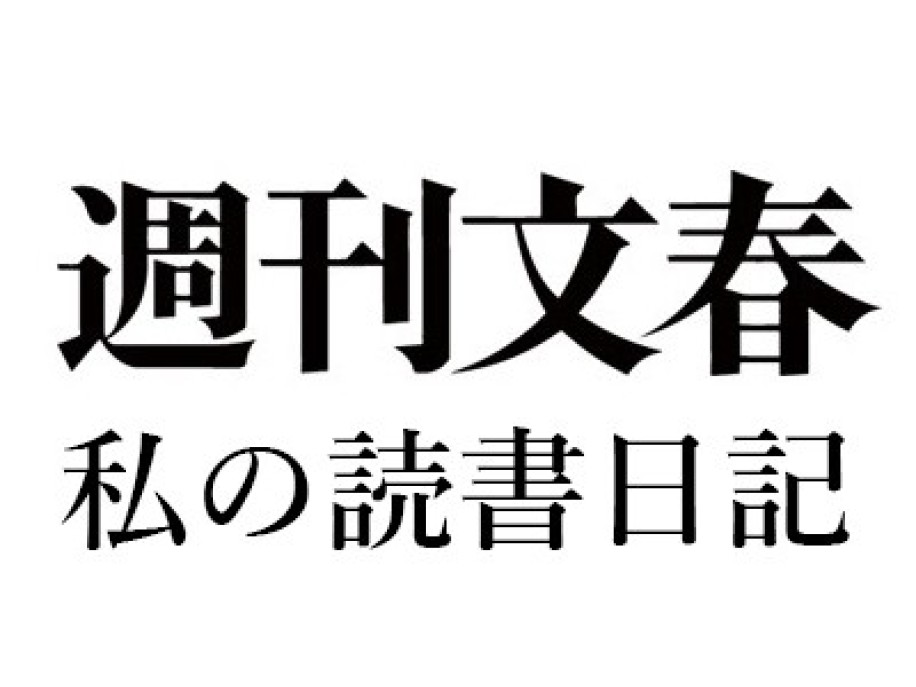書評
『進化考古学の大冒険』(新潮社)
土器の「美」の変遷から捉え直す人類史
考古学への関心は年々高まっている。その高まりは、一つには新たな遺跡・遺物の発見にある。新発見によって歴史がこう書き換えられるといったトピックが、人々に興味をかきたて刺激をあたえてきた。しかしこれらは、実際はよくよく検討してみないとわからないことが多く、時に捏造などの不祥事を招く起因ともなってきたのである。
これに対してもう一つの高まりといえるのが周辺諸科学の研究の進展に基づくもの。
本書はその諸科学の発展から見えてきた「進化考古学」を論じ、その冒険に船出しようという気宇壮大な試みである。進化といっても、これはその時々の社会的・自然的な環境に適応した形のものが伝えられてゆくことを意味するもので、必ずしも進歩や発展を意味しない。
その試みは何よりも日本列島の、限られた時代の考古学に視野を閉じ込めるのではなく、広く人類史の視点から考察することにある。旧石器時代以前から人類がいかに進化の過程を辿(たど)ってきたのかを探り、その動きや流れのなかから縄文時代や弥生時代、古墳時代を捉え直してゆくのである。
それならば、これまでにも行なわれてきたというかもしれないが、これまでと違うのは、人の心の問題をとりあげ、認知諸科学の成果を援用して、人類史の流れを整理し、新たな知見を提出しているところである。
たとえば、石器などの道具に心の変化を探り、美しいと感じることがどう変化してきたかを考え、集団生活にともなう身体や脳の変化について考えてゆこうとする。認知に関(かか)わる脳科学の成果に基づいて、モノとそれをとりまく社会現象を解明するのである。
美には体制的な美、美に反する美、倫理の美があるとして、世界的にも有名な縄文土器の文様の美しさは、定住社会の成長とともに一定の秩序をともなう体制的美として展開していたものが、その美に反する美が求められたことに起因していると説く。
では日本の考古学で重要な論点になっている縄文土器から弥生土器への変化についてどう考えればよいのか。一般的には狩猟・採集社会から農耕社会への変化として捉えられてきたが、最近では縄文土器の末期の時代には稲作が始まっていたとする見解が強いのだが。
これに対しては、まずこうした人工物を分析する場合には、物理的な機能を担う容器や衣装などのフォーム、そのフォームの下で社会的な機能を体現する時代や地域によって異なるスタイル、そしてそのスタイルのうち細部の形状やデザインが変化するモードの三つにわけて考えてゆくべきとする。
その点からすると、縄文土器から弥生土器への変化はスタイルの変化に過ぎず、縄文土器も末期には複雑な文様ではなく単純な形のものが出現しており、そこから狩猟・採集社会から農耕社会への変化を見るのは難しいと見る。この変化は定住社会における集団の性格に起因するものと見るべきであると説いて、さらに農耕社会そのものの捉え直しへと向かう。
ほかにも民族の誕生といった問題や、巨大古墳から文字への社会変化の性格の解釈など、本書はこれまでの考古学の解釈に根底から再考を迫るものがあり、それもあって「大冒険」と称しているのだが、これにより考古学の可能性は大きく広がってゆくことであろう。
この挑戦を通じて、社会変化における新たな動きや意味が解明されることを期待したい。