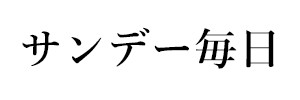書評
『英国風の殺人 世界探偵小説全集』(国書刊行会)
英国でしか起こりえぬ犯罪
タイトルに惹かれて読みはじめた本が期待に違わなかったとき、読書そのものからくる感銘とは別の満足がある。欺(だま)されなくてよかった、という安堵感でもあろうか。タイトルにはいつも欺される。タイトルを付けるほうも、あの手この手で欺そうとする。「欺す」で語弊があれば、興味をひこうとする。
最近、タイトルにつられて、「哀しみのスパイ」というフランス映画をみた。原題は「愛国者たち」。輸入配給会社が改題した気持もわかる。
シリル・ヘアーの『英国風の殺人』という探偵小説もタイトルに惹かれて手に取った。深い緑と黒をアレンジした粋な装丁もよかった。だいじな要素だ。
こちらは原題も同じく、『An English Murder』である。イギリスミステリーの伝統を継ぐ正当派として評価の高いシリル・ヘアーの一九五一年の作品で、彼には既に『法の悲劇』『ただひと突きの……』などの翻訳もあるが、僕は、一昨年邦訳の出たこれがいちばんだと思う(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1997年頃)。
作風はあくまでもオーソドックスで、ドンデン返しもない。謎解きより、英国伝統社会の雰囲気と、作品世界全体とまるでジグソーパズルの一片のように有機的に結ばれている細部の描写をじっくり楽しむようにできあがっている。
イギリスの古い家柄で、余命いくばくもない老貴族の屋敷に、クリスマスを祝うために一族が集まってくる。当主の後継者で、ファシストの息子、姪、当主の従弟で現職の大蔵大臣、遠縁の人妻(夫は政治家で、大蔵大臣の有能な部下だが、アメリカに出張中)、屋敷に残された古文書の研究のため滞在中の、国籍も定かでない老歴史学者。
時は第二次世界大戦直後、場所はロンドンから遠い田舎。
到着の前から激しく雪が降りはじめ、彼らは屋敷に閉じこめられる。降りつもる雪が最高潮に達したとき、事件が起きる。後継ぎの息子が何者かに青酸カリを盛られて殺されるのだ。雪のため外との連絡は断たれている。この辺も古典的探偵小説の常道をいく。
犯人は客のいずれかだ。探偵役は、老歴史学者に振り当てられる。読者としては、彼に対する嫌疑も一応考慮しながら読み進めなければならない。しかし、探偵が犯人だった、なんてルール違反を作者が犯すはずがないということを、英国小説十八番(おはこ)の、公正で、ユーモアとウィットにとんだ語りくちが保証してくれるから、こちらはせこい緊張を強いられずにすむ。
くだんの大蔵大臣はいう。
「昨夜我々が目撃した不幸な事件、あれは英国の生活習慣とは無縁ですからな。それどころか、極めて非英国的と申し上げてよろしいでしょう」
ところが、英国の歴史をよく研究している異国の歴史学者は、だんだんこれこそ英国でしか起こりえない犯罪だと確信するようになる。英国の伝統社会を自慢にする連中ほど英国の歴史に無知であり、この無知ぶりが事件の解明を遅らせ、第二の殺人を呼ぶことになるのだ。
雪がやみ、気温もあがり、雨が降りだす。雪解けと共に探偵の推理も加速して、犯人の姿が明らかになってゆく。
もちろん犯人は客の中の一人だった。動機は、保守的な英国の政治制度そのものにあった。
英国でしか起こりえぬ犯罪。動機と行為が、タイトルそのものになっているのだ。探偵小説としても一級だが、フィールディング、ディケンズにつらなる英国小説伝統のリアリズムとユーモアの調和をじっくり味わえる。作者は法律家。そういえばフィールディングも弁護士だった。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする