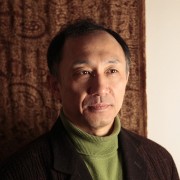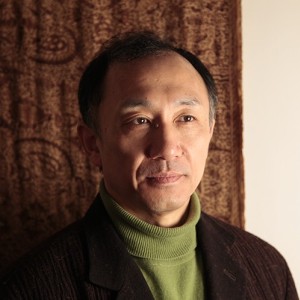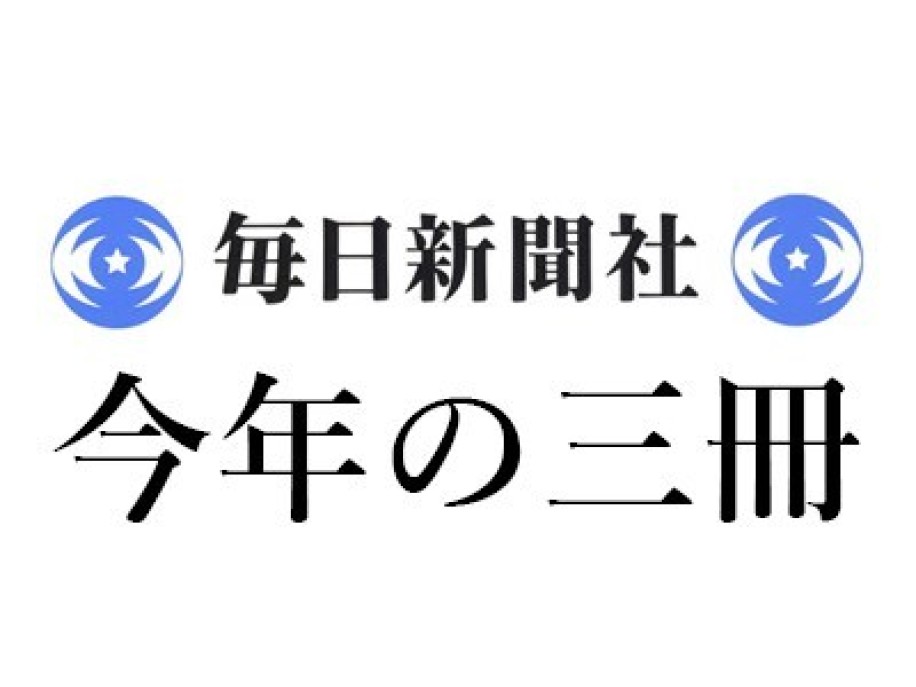書評
『沢村忠に真空を飛ばせた男: 昭和のプロモーター・野口修 評伝』(新潮社)
勝利までお膳立てする手腕
読売巨人軍が9連覇した1973年、三冠王を取った王貞治は「日本プロスポーツ大賞」を受賞しなかった。同年、ボクシングジムに併設された芸能事務所に「日本レコード大賞」がもたらされた。龍反町が輪島功一に勝っていたらジムにはボクシングでも世界王者が誕生し、「異ジャンル三冠」が達成されたところだった。それぞれが当時どれほど国民の関心事であったかを考えれば、異様な出来事ではある。それでいて半世紀を経たいま、この件が回顧されることはない。それもまた異様である。
やってのけたのは野口ジム会長の野口修(1934~2016)。タイの国技「ムエタイ」を「キックボクシング」に、無名の空手家を「沢村忠」に仕立て上げ、プロスポーツの頂点に立たせた。また何度芸名を変えても売れなかった歌手を「五木ひろし」として再デビューさせ、「夜空」のサビでは野口ジム仕込みのパンチを振り付けて、レコ大レースで沢田研二「危険なふたり」に競り勝たせた。
この稀代のプロデューサーはなぜ忘れられたのか。「沢村忠の試合は真剣勝負だったんですか、八百長だったんですか」。誰もが口に出せないできた問いをぶつける著者は、キックボクシングのリングアナも務める放送作家。いわばインサイダーであり、日本ダービーを制さんと入れあげて80年代には破綻していた野口の晩年に密着、昭和臭漂う実像に迫っている。
野口は「真剣勝負だよ」と返すのみだが、沢村の240戦227KOのうち27KOが同一タイ人からのものという本書の発見で十分だろう。一方の芸能部門は金がものを言った。レコ大レースでは票を持つ音楽評論家から「資料を持ってくるように」との隠喩で再三要求があったという。
野口の発想と手腕はいかにして培われたのか。本書が光を当てるのが、ひとつは戦前に「最高最大の豪傑ボクサー」と呼ばれた父の右翼人脈である。野口進は甲子園球場でも戦った日本王者だったが、若槻礼次郎暗殺未遂事件を起こして収監された刑務所で児玉誉士夫と出会う。大戦中に上海の大陸浪人サロンで芸能興行を体験し、戦後に見いだした三迫仁志を鍛え上げ、児玉の支援を受けつつボクシング興行に乗り出した。
進の死後、ジムを継いだ修は弟の恭と矢尾板貞雄の対戦を主催している。その結論が、「いくらお膳立てしても、選手が勝たなきゃ意味がない」だった。プロモーターが儲けるには必ず勝つようお膳立てするしかない、と。
本書はテレビの興隆にも詳しい。思うに日本では有料テレビが未発達で、格闘技の技術に通じるせいぜい100万人の視聴者では放送が成り立たない。1000万人を熱狂させるコンテンツが必要だった。それで沢村は真空を飛び、テレビ4局がキックボクシング中継を奪い合った。熱は冷めたものの半世紀にわたる先人の苦悩の果てにいま、那須川天心が真剣勝負で大晦日のお茶の間を沸かせている。
銀座のクラブ「姫」のママであり五木を見いだした直木賞作家の山口洋子は修の内妻だった。歌詞を提供した中条きよしの「うそ」はこう唄う。「折れた煙草の吸いがらであなたの嘘がわかるのよ」。吸い殻を折る癖のある男を著者は目撃している。泣ける結末だ。
ALL REVIEWSをフォローする