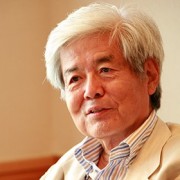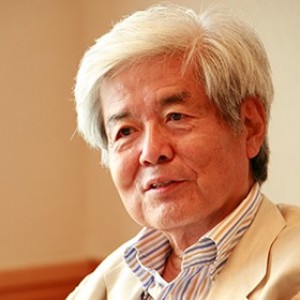書評
『生きのびるための流域思考』(筑摩書房)
社会運動まで含めた「総合治水」
子どものころから不思議に思っていたのは、川の水である。雨も降っておらず、一見乾いていると見える地面を流れてゆくのに、次第に川が太くなり、河口ではまさに滔々(とうとう)と流れる。あの水はどこから来るのか。支流が次々に合流するからだという理屈はわかる。だが、感覚が納得しない。そこで小学生の時に、友人と語らって、市内を流れる川を源流までさかのぼる冒険をしたことがある。確かに源流にはたどり着いたが、川の水は細くなる一方で、川の水が一体どこから来るのかという疑問は、解けないままだった。いまだに直感的には納得していない。八十を超える年齢になって、流域思考に関心を持つ根本にはその疑問がある。
本書は鶴見川の流域で暮らし、何度も水害に遭い、総合治水に関心が強い著者が流域についてまとめたもので、学者という言葉から連想される理論だけではなく、社会運動をも含めたいわば筋金入りの流域思考を展開する。
本書は二〇二〇年国土交通省河川分科会が流域治水という方針を発表したことを受けて、流域治水の新しい動向を紹介する緊急出版だと著者は書く。
第一章「流域とはなにか」では集水、流水、保水、増水、遊水、氾濫、排水など概念と言葉の定義を扱うので、やや教科書的であり、たとえば私自身は「洪水」とはそういうものか、と認識を改めた。洪水を通常の流路つまりいわゆる川から水が外にあふれ出た状態だと単純に理解していたからである。
第二章は「鶴見川流域で行われてきた総合治水」と題され、この川の流域に関するきわめて具体的な各論である。一九八〇年以降四十一年にわたって、著者たちが進めてきた「総合治水」がいかなるものであるかが、現場に即して理解できる。ただし「現実の制度・法律の世界は一筋縄ではゆかない複雑さがあります。流域治水の提言ひとつで、流域管理が一本化されるわけではありません。流域治水そのものはビジョンであり、総合的な法定対策を円滑に進めるためには、さまざまな法律や条例等の改定、関連づけや予算執行についての課題を解決してゆかなければなりません」。この文章だけを読んだ人は、その通りだとただ簡単に読み過ごすかもしれない。しかし第二章の詳細に触れた人は四十一年にわたる著者たちの努力がいかなるものであったかに思いが届くであろう。
第三章「持続可能な暮らしを実現するために」は未来への見通しを語っている。著者は生物学者、進化学者、生態学者でもあり、総合治水は単に土木技術の問題ではなく、地球環境、生物多様性の問題でもあることをはじめからよく知っている。著者はそこで「流域地図を持つ」という提案をする。自分の住む流域の地図を各人が頭の中に持つ。それを共通認識とした上で、さまざまな問題を考えようと提案する。最近環境省では子どもたちのために「読本」を作っており、それは「森里川海大好き!」と題されている。要するにこれは流域であり、流域という漢語で示すより子どもが具体的にイメージしやすいということから採用されたのであろう。著者自身は複数の表現があってもいいという考えのようである。
ALL REVIEWSをフォローする