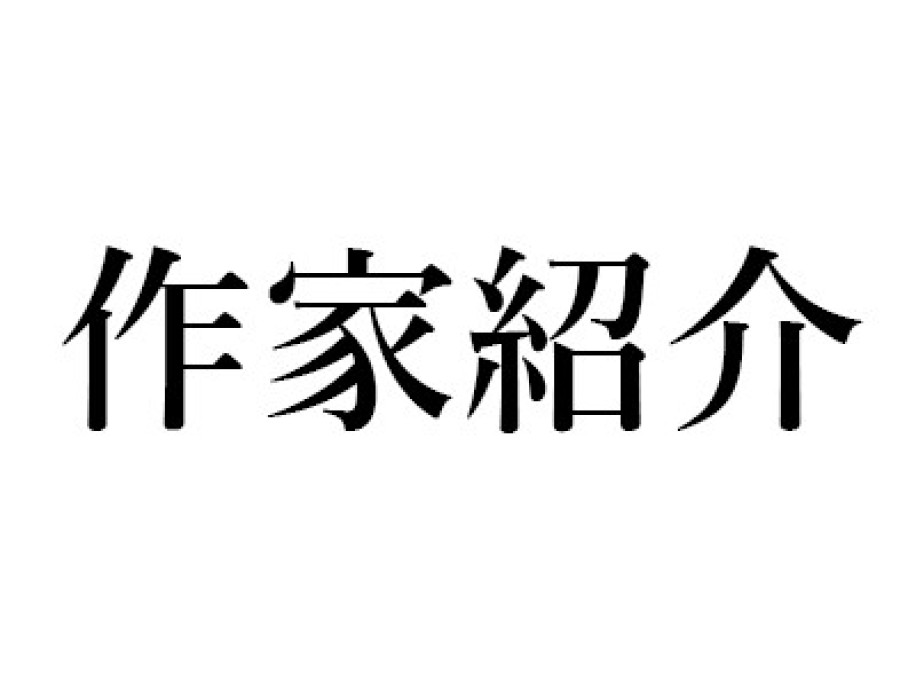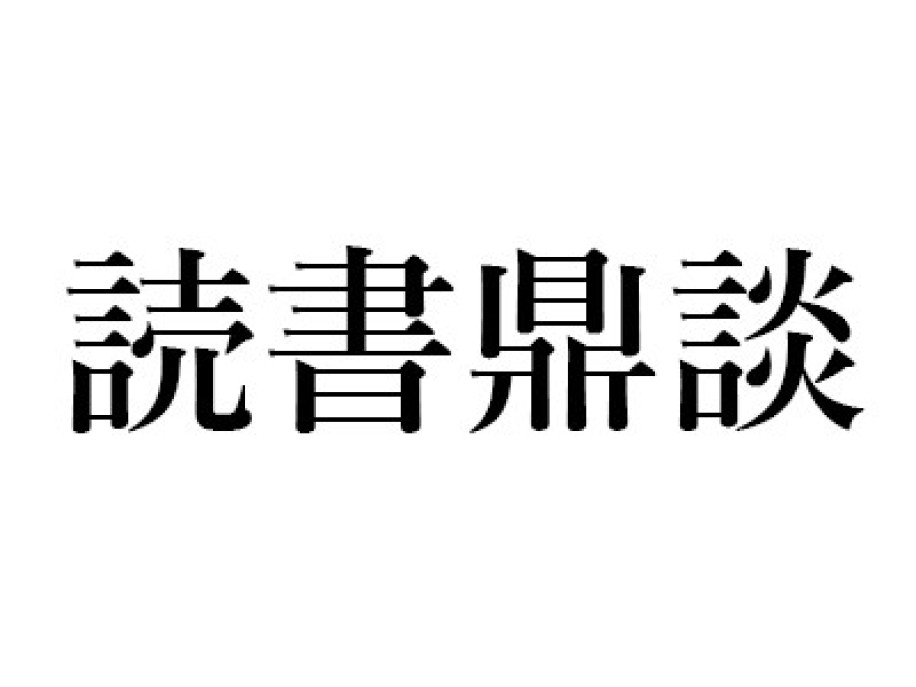書評
『自選随筆集 野の果て』(岩波書店)
自然という書物を読む 手が考える
著者はこの人と同時代を生きてよかったと思い多くを学んでいる方の一人。紬織(つむぎおり)での重要無形文化財保持者、文化勲章受章者として御存知の方も多いだろう。随筆家でもある著者の自薦で編まれた「私」、「仕事」、「思想」三部構成の本書からは、人間志村ふくみが浮かび上がる。随筆を書く基本には、工芸の仕事だけに一心になっていると必ずゆきづまりがくるので、何か別なことを勉強するようにという陶芸家富本憲吉の言葉がある。そこで選んだ文学の原点に、28歳で亡くなった長兄に病床の側で読み聞かせた『カラマーゾフの兄弟』がある。著者の言葉に、師と兄とドストエフスキーから授かったものを感じる。
離婚をきっかけに仕事として選んだ染織の支柱としたのが柳宗悦の民芸だった。自然に帰依すれば誰もが美しいものを生み出せるという考え方に支えられて生み出した最初の着物「秋霞(あきがすみ)」が第五回日本伝統工芸展の奨励賞を受賞する。その後トントン拍子に評価が高まるのだが、柳宗悦は「秋霞」には作意があるとして破門を宣告するのである。辛いが「思いっきり、自分のやりたいことをするのだと心に言いきかせた」。惹かれるのはこの生き方だ。
著者は草木染を選ぶ。「染色の口伝」に「染料になる草木は自分の生命を人間のために捧げ」るのだから、「感謝と木霊への祈り」をもつようにとある。印象的なエピソードがある。道路拡張で切り倒された榛(はん)の木の切り株から地面を真っ赤に染めて木屑が散っているという知らせに、急いでかけつけ剥いだ皮を炊き出す。できた金茶色の液を媒染すると、榛の木の精の色としか思えない色になったというのだ。「榛の木がよみがえった」と思ったそうだ。
草木染では緑が出せないというのが興味深い。自然はこれほど緑に満ちているのに、葉を絞った緑の液は刻々色を失い灰色になる。刈安(かりやす)や梔子などで染めた黄色の糸を藍甕(がめ)につけて初めて緑が生まれるのだ。他の色は染まるのだが、緑はなぜか生まれると言いたくなると著者は言う。ここでゲーテが登場し、「光のそばに黄があり、闇のそばには青がある。この二つが完全に均衡を保って混ざると緑が現れる」と語る。闇と光が生み出す色が生命の色、緑だというわけだ。ここで著者は、藍甕の中で竹棒で絞り上げた後、力を抜くと、空気に触れた糸がエメラルドグリーンに輝くことを思う。ところがこれは一瞬、すぐに縹(はなだ)色になるのだ。緑はどこへ行くのか。
著者は日々自らの手と眼を通して自然という書物を読んでいるのだ。「機を織っていてしばしば手は考えている、と実感する」。頭よりも先に手が色を選ぶのだそうだ。そこで「人類が手仕事をしなくなれば滅びるのではないだろうか」と思う。そこには、手仕事を通しての人間への信頼が見える。ところが今や「身に迫る危機は世界を覆っている」という現実を直視しないわけにはいかない。ここで著者は「今、目前にある現実がすべてではない。もっと全く違った別の道があるかも知れない」と書く。私も全く同じ思いだ。
通常書評は本の全体像を伝えたと思って筆を擱(お)くのだが、今回は難しい。どのページにもこれぞ著者の真髄と思わせる言葉が溢れており、伝え切れないのだ。それらの言葉に直接触れていただきたい。