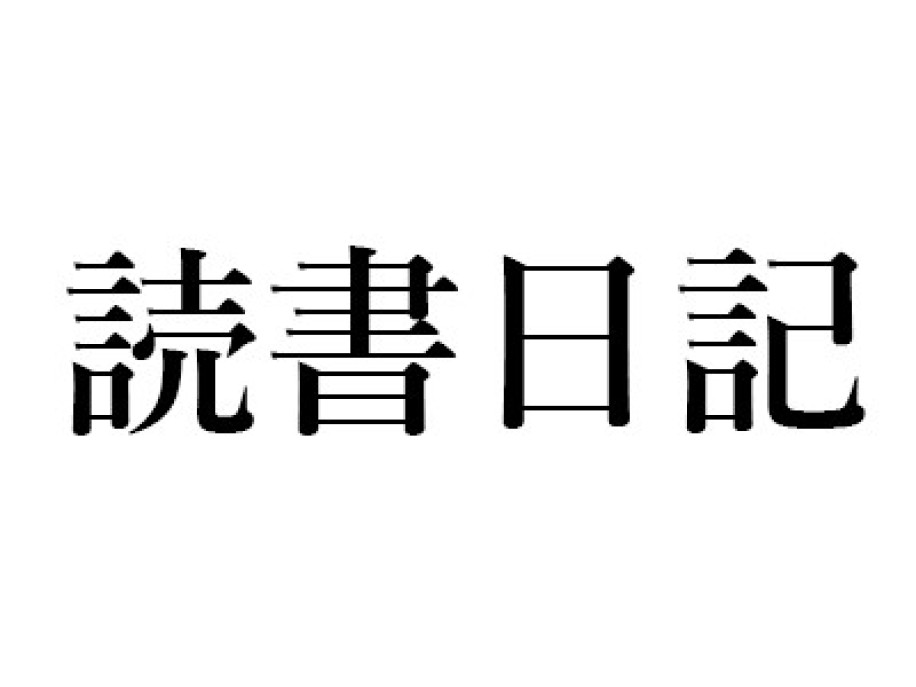書評
『産業文明とポスト・モダン』(筑摩書房)
ポスト・モダンなんか正体不明の、ぐにゃぐにゃ軽薄思想さ――と、敬遠するむきには小気味よい、硬派の書きっぷり。斬新な提起を続ける気鋭の経済学者、佐伯啓思氏の最新論集だ。書き下ろしを含め全六章、氏が「高度市場社会」とよぶ、産業社会のいちばん新しい様相を、多様に切りわける文章が並んでいる。
粗っぽいまとめで著者に怒られそうだが、この本の中心になる論点は、つぎの二つだと思う。
第一に、市場が最近、いちじるしく拡大して、これまで「市場の枠外にあった情報やサーヴィスを市場の領域に大規模に取り込んだこと」。ただしこれは、あくまでも市場の拡大なのであって、産業社会が本来の姿とすっかり違ったものに変化してしまったとは見ないほうがよい。
第二に、そのような変化が必然的に、ポスト・モダン、つまり価値の相対主義とニヒリズムをうむこと。それは「文化の固有の価値の基準が市場による評価の基準におきかえられてしまう」からだ。著者はそれに対して、知識人が「ドン・キホーテ的騎士精神」で立ち向かうよう訴える。
このため佐伯氏がお手本にするのは、ソクラテスである。
かつてギリシャのポリス文化は、公衆の前で言論を応酬しあう競技の達人、ソフィストたちをうんだ。いままたポスト・モダン(演ずる者と見る者からなる知のスペクタクル)は、現代のソフィストの群れをうみだしている、という。この書物は、彼らにあてた倫理的闘争宣言だ。
ソクラテスは、ソフィストのなかのソフィスト。彼の弁証法は、ソフィストたちの言論のゲームを終了させるための、命をかけたパフォーマンスだった。それにならい佐伯氏も、ポスト・モダンの混迷を抜けだす、ひと筋の活路をひらこうとするらしい。その気骨をよしとしよう。
著者の専門である経済学的分析も随所に織りまぜながら、六〇年代から八〇年代へと変貌を重ねる日本社会、特に、知識の舞台がポスト・モダンにぬり変わっていく必然を活写する筆致は、説得的で示唆に富む。それだけにどうやって、その必然性をかいくぐるつもりか心配になる。
ところが著者の掲げる処方箋が、わかりにくい。
文化の商品化には「文化それ自体の力で抗する以外にない」、「文化や価値の領域のなかに容易には商品化できないひとつの世界を残しておこう」と言う。そして、そういう自由のある市場を「自己生成的市場」と名付ける。知識人の頑張りに期待しようということらしい。
しかし、そうは問屋がおろすのか。
著者の分析どおりなら、近代の行き着く先がポスト・モダンである。その洗礼を受けた若者やわれわれが、このうえどうやってポスト・モダンとひと味違った線を出せるのか、もうひとつ決め手が見えない。心構えを提案するだけなら、ただのお説教で、浅田彰さんあたりに軽くかわされてしまいそうだ。
【この書評が収録されている書籍】
粗っぽいまとめで著者に怒られそうだが、この本の中心になる論点は、つぎの二つだと思う。
第一に、市場が最近、いちじるしく拡大して、これまで「市場の枠外にあった情報やサーヴィスを市場の領域に大規模に取り込んだこと」。ただしこれは、あくまでも市場の拡大なのであって、産業社会が本来の姿とすっかり違ったものに変化してしまったとは見ないほうがよい。
第二に、そのような変化が必然的に、ポスト・モダン、つまり価値の相対主義とニヒリズムをうむこと。それは「文化の固有の価値の基準が市場による評価の基準におきかえられてしまう」からだ。著者はそれに対して、知識人が「ドン・キホーテ的騎士精神」で立ち向かうよう訴える。
このため佐伯氏がお手本にするのは、ソクラテスである。
かつてギリシャのポリス文化は、公衆の前で言論を応酬しあう競技の達人、ソフィストたちをうんだ。いままたポスト・モダン(演ずる者と見る者からなる知のスペクタクル)は、現代のソフィストの群れをうみだしている、という。この書物は、彼らにあてた倫理的闘争宣言だ。
ソクラテスは、ソフィストのなかのソフィスト。彼の弁証法は、ソフィストたちの言論のゲームを終了させるための、命をかけたパフォーマンスだった。それにならい佐伯氏も、ポスト・モダンの混迷を抜けだす、ひと筋の活路をひらこうとするらしい。その気骨をよしとしよう。
著者の専門である経済学的分析も随所に織りまぜながら、六〇年代から八〇年代へと変貌を重ねる日本社会、特に、知識の舞台がポスト・モダンにぬり変わっていく必然を活写する筆致は、説得的で示唆に富む。それだけにどうやって、その必然性をかいくぐるつもりか心配になる。
ところが著者の掲げる処方箋が、わかりにくい。
文化の商品化には「文化それ自体の力で抗する以外にない」、「文化や価値の領域のなかに容易には商品化できないひとつの世界を残しておこう」と言う。そして、そういう自由のある市場を「自己生成的市場」と名付ける。知識人の頑張りに期待しようということらしい。
しかし、そうは問屋がおろすのか。
著者の分析どおりなら、近代の行き着く先がポスト・モダンである。その洗礼を受けた若者やわれわれが、このうえどうやってポスト・モダンとひと味違った線を出せるのか、もうひとつ決め手が見えない。心構えを提案するだけなら、ただのお説教で、浅田彰さんあたりに軽くかわされてしまいそうだ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする