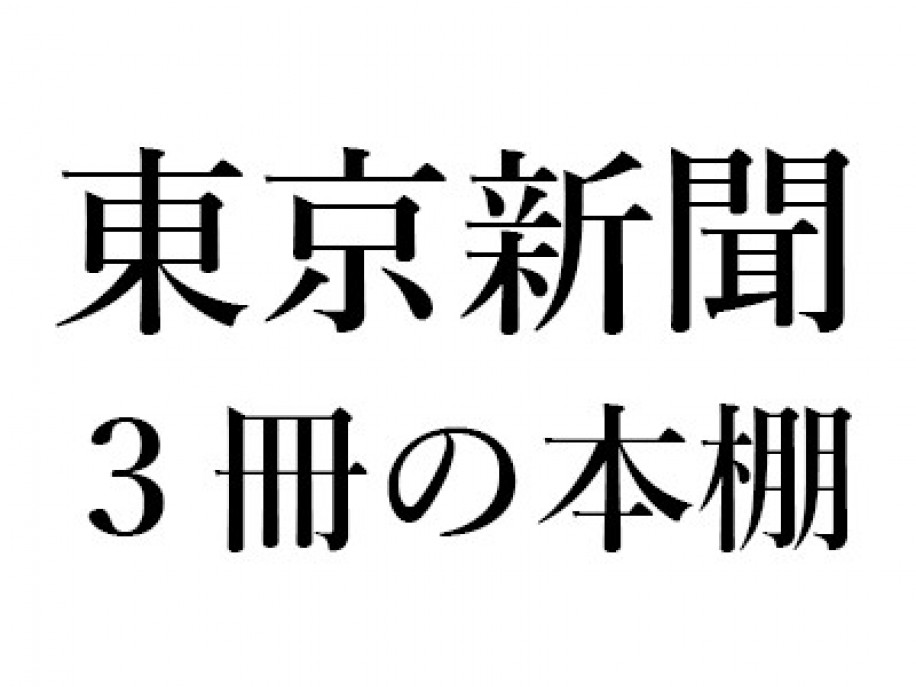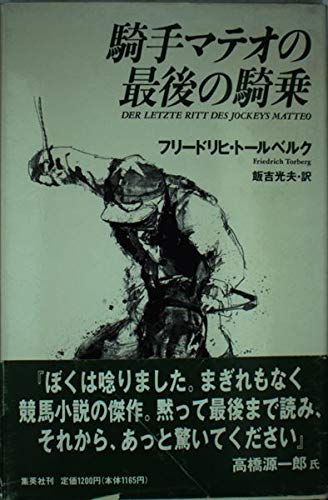選評
『東京島』(新潮社)
谷崎潤一郎賞(第44回)
受賞作=桐野夏生「東京島」/他の選考委員=池澤夏樹、川上弘美、筒井康隆/主催=中央公論新社/発表=「中央公論」二〇〇八年十一月号すべてを捨ててすべてを得る
まずニッポン系の漂流者や棄民たちが、つづいてホンコン系の男たちが、さらにフィリピン系の女たちが、微妙な時差をつけながら、縦七キロ、横四キロの無人島へ次つぎに流れ着く。ロビンソンクルーソー式孤島譚だが、本作ではその祖型がうんと複雑になっている。こうなるともう期待しない方がどうかしている。言葉を異にする人間たちが集団で生きて行く以上、農漁業や言語や戒律や宗教や経済といった小文明を創り出し、できればそれらを展開し発展させなければならない。つまり読者は、文明誕生の瞬間とその発展を目のあたりにすることができるので、それがおもしろくて無人島ものに読みふけることになるわけだが、じつは作者は、そういった無人島ものに欠かせない仕掛けにまったく興味を示さない。
言語一つとってみても、最初に三つの言語がまぜこぜになるピジン語世代があるはずであり、次にそのピジン語をそのまま母語として受けとめるクレオール語世代が育つにちがいないのに、それについてなにも書いていない。
モノやココロを交換するさいに必要な島共通の価値(たとえば、島の貨幣)、それをだれが発明するのか。発明者はしばらくのあいだ島の権力を掌握するだろうが、それはいつになるのか。……だが、そのときはついに訪れることがなかった。
島に一丁しかないナイフは権力の象徴のようなものだが、しかしナイフの行方をめぐって、島の権力分布が微妙に変化するというようなところも捨てられて、本作のナイフはただの小道具にすぎない。ひっくるめて、国造り神話の構造化(このお話にもっとふさわしいスタイル)が不徹底である。
それでは駄作かというと、じつはそうではない。作者は、右に書いたような無人島ものの約束ごとをすべて、きっぱり捨てたのだ。そして人間に本源的な男女の営み、つまりセックスと生殖に的をしぼり、その一点に向けて全才能を傾注した。その大胆不敵な潔癖さから生まれた緊密な文体と劇(はげ)しいリズム感が、本作を好個の傑作に仕立てあげている。
作者はすべてを捨ててすべてを得た。
【この選評が収録されている書籍】
中央公論 2008年11月
雑誌『中央公論』は、日本で最も歴史のある雑誌です。創刊は1887年(明治20年)。『中央公論』の前身『反省会雑誌』を京都西本願寺普通教校で創刊したのが始まりです。以来、総合誌としてあらゆる分野にわたり優れた記事を提供し、その時代におけるオピニオン・ジャーナリズムを形成する主導的役割を果たしてきました。
ALL REVIEWSをフォローする