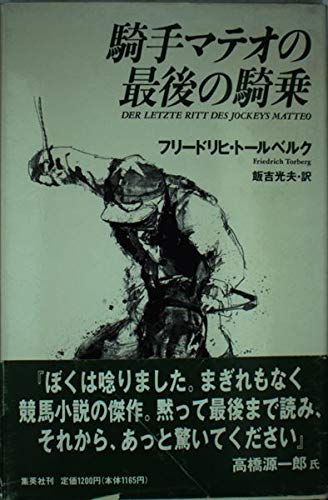書評
『市村弘正著作集 上巻』(集英社)
注意深く読む、さまざまな出合い
社会が壊れていく。5年後、10年後はどうなっているだろう。不安と絶望感が襲う。こんなときこそ、小さなものに目を向け、かすかな音に耳を澄ませよう。天下国家を論じる大文字の言葉や大きな声ではなく。市村弘正の文章を読んでいると、そういう気持ちになってくる。市村は1945年生まれの思想史家、批評家。『市村弘正著作集』は現時点における市村のほぼ全ての文章が収められている。上下巻合わせて約1000ページ。上巻には『「名づけ」の精神史』『標識としての記録』『小さなものの諸形態 精神史覚え書』。下巻には『敗北の二十世紀』と『読むという生き方』、そして単著未収録論考。その知名度や影響力に比べて、ずいぶんと寡作だったことに驚く。「怠慢の謗(そし)りを免れないが、私にとって考えるべきことを考え書くべきことを書いた結果である」という後記の言葉にグッとくる。
この2冊の本には、考え抜かれ、慎重に選ばれた言葉の数々。覚えておきたい言葉、抜き書きしておきたい言葉がたくさん詰まっている。たとえば「私たちは物に対する哀悼からはじめなければならないのではないか」。『「名づけ」の精神史』の「物への弔辞」という章の冒頭だ。まるで「いま」のために書かれたような文章。しかし、初出は1984年の雑誌だから、まだスマートフォンもソーシャルメディアも生まれていない時代に書かれた。この文章を読んで考える。ぼくはいまネットの中の言説をいちど括弧(かっこ)に入れて、物と人間との関係を見つめ直すべきではないか?
この著作集には月報「市村弘正研究ノート」がはさみこまれている。これが素晴らしい充実ぶり。市村と縁ある研究者や編集者が寄稿しているのだが、格好のガイドブックになっている。たとえば石川健治の「トランシルヴァニアに『声』をきく」。新聞の片隅にあったブダペシュト発の特派員報告から、市村が「晩年のバルトークについての脚註」(のちに加筆され、「文化崩壊の経験――晩年のバルトークについての脚註」として『小さなものの諸形態 精神史覚え書』に採録される)を書くにいたる道筋を解説してくれる。市村の文章には注意深く読まないと見過ごしてしまうことがたくさん隠れている。
今回ぼくがもっとも楽しく興味深く読んだのは、下巻に入れられた『読むという生き方』。読書論的自伝とでもいうべきか。「読んだ本の気にかかる著者に会いに行こう」と橋川文三や藤田省三を訪ねたこと、アーレントやベンヤミン、バフチンとの出会い、そして藤田省三の私的な研究会や読書会のこと。
驚いたのは次の一節だ。
小さな切断が遂行される。八〇年代の前半から新刊書を購読することをやめた。新聞の書評に目を通すこともやめた。
ひたすら「古本」の再読を続ける。出版界・読書界がニューアカ・ブームで浮かれているときに、流行の本や言説から遠く離れて「小さなもの」に目をこらし、耳を澄ませていたのだ。なんと大胆な切断! その切断はいつまで続いたのだろう。
『市村弘正著作集』を手がかりにして、ぼくは晩年の読書計画を練ろうと思う。
【下巻】
ALL REVIEWSをフォローする