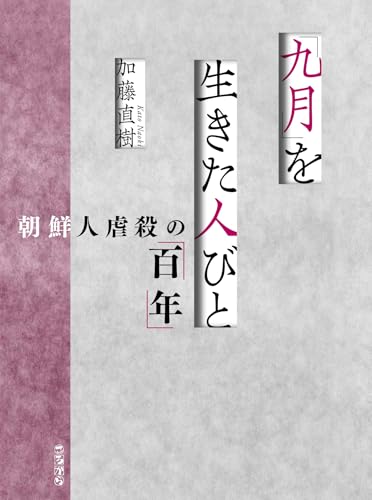書評
『千年の歓喜と悲哀 アイ・ウェイウェイ自伝』(KADOKAWA)
奪わせてはならない記憶、父子の闘い
北京オリンピックのスタジアム「鳥の巣」の建築を手がけたことで知られる艾未未(アイウェイウェイ)は、躊躇なく体制批判を繰り広げる社会活動家でもあり、中華人民共和国政府にとっては危険人物である。2011年4月、北京空港で突然拘束される。目隠しされたまま収容施設に連行され、家族にも弁護士にも連絡できないまま、「監視居住」が始まった。自伝であるとともに、彼の父の伝記でもある本書は、艾未未がこの「ブラックホールに吸い込まれていた」期間に構想された。
父・艾青は高名な詩人で、国民党政府に共産主義者であるという理由で投獄され、文化大革命期には右派知識人として「労働改造」のために下放された人物だった。表現者となった父と息子は、奇しくもよく似た人生の軌跡をたどることになった。
いつ終わるとも知れない拘束と監視と尋問の日々の中で、父を思うことは艾未未を支えただろう。艾未未にも幼い息子の艾老がいる。「子どもは追放された人間の究極の希望」と書く彼は、父にとって息子・未未が何者だったか知ったに違いない。
冒頭、父が下放された「小シベリア」での日々が思い起こされるのは、そこが父と息子の苦難の歴史の結節点であるからだ。
文化大革命のさなか、艾青は極寒の地へ送られる。母はまだ幼い弟と北京に移住を決め、艾青は妻の連れ子の高剣と未未を連れて奥地へと向かった。人の便が地面から生えたつららのように凍る土地で、毎日、屋外共同便所の掃除をして汗だくになって帰宅する父。その父が時折、なにかに憑(つ)かれたように語る「記憶」が、本書の原点にある。
ページをめくっても、めくっても、苛酷な弾圧の歴史が続く本書の記述は、しかし、どこか奇跡的に温かい。「小シベリア」の生活に突然光が射す瞬間。北京から、母と弟の艾丹がやってきて、生活に加わる。「穴倉の家には笑い声が上がり、温かく、父も私も孤独や不機嫌さを感じなくなった」。追放や隔離のもっとも残酷な面は、人からその人間性を奪うことなのだと思う。
「監視居住」は81日間に及んだ。その間、艾未未の観察が、若い衛兵たちの姿に及ぶのにも心動かされる。独裁国家の歯車である彼らの時間は、毎日をただただ「犯罪者」である芸術家を監視するだけに費やされる。その理不尽を、艾未未は思いやる。
父・艾青の人生は苛酷だ。浙江省にある小さな村の地主の息子として生まれ、若い時にパリ留学を果たすが、彼が不在だった間に、祖国中国は激変していた。
艾青は帰国した年に、国民党政権下で逮捕され、獄中で3年余りを過ごす。それから先は、抗日戦争の時代だ。日本の占領で家を失い、職と住居を求めて転々とする。国民党政権への失望から、共産党の本拠地・延安に向かうが、そこで求められたのは自由な表現ではなく「文芸労働者」となることだった。1945年に正式に共産党員となり、新中国の国旗のデザインを作る委員会の議長まで務めるのだが、その後も知識人・芸術家たちは、絶え間ない嵐の中を生きる。「文化大革命」では「五十五万人もの知識人が『労働による改造』の対象」となり、「二十年たってやっと『名誉回復』されたとき、生き残っていたのはわずか十万人だった」という。
文革時代を、父・艾青とともに「小シベリア」で過ごした艾未未は、80年代にニューヨークへ向かう。父が30年代のパリを見たように、最先端のアートと自由を吸収した艾未未は、アーティストとしての才能を開花させる。そして89年6月に、母国の政府が天安門広場の学生たちに戦車を向けるのを、CNNにくぎ付けになって見ることになった。
90年代に帰国し、天安門広場に中指を突き立てる写真を撮ったり、「FUCK OFF」(非協力的な態度)と名づけた展覧会を開いたり、挑発的ともいえる作品を発表する。建築家として名を成し、時代の寵児となっていく一方で、常に彼の心をとらえるのは、独裁国家の犠牲になる声なき人々だ。めざましい経済発展を遂げる背後で、SARS、四川大地震といった災害が牙を剥くが、政府は多くの人を救うことよりも、事実の隠蔽や忘却に熱心だった。艾未未はインターネットのブログや、ビデオカメラを駆使して闘う。
「記憶」という言葉が心に残る。「国家とは人から記憶を吸い取って漂白してしまう機械」だと彼は書く。
「歴史や記憶をごまかそうとする独裁政治」に抗って、わたしたちは「記憶」しなければならないのだ、と。
艾未未の芸術は記憶であり、そのための詳細な記録であり、記述であり、表現だ。
それがいかに大切なものか、奪われてはならないものかということが、この一冊に詰まっている。
これは、隣の国の同時代の記録だけれども、記憶と歴史と表現を奪わせないために、わたしたちがするべきことについての本である。
ALL REVIEWSをフォローする