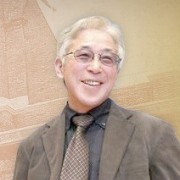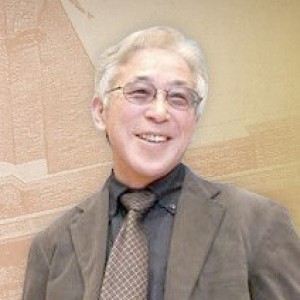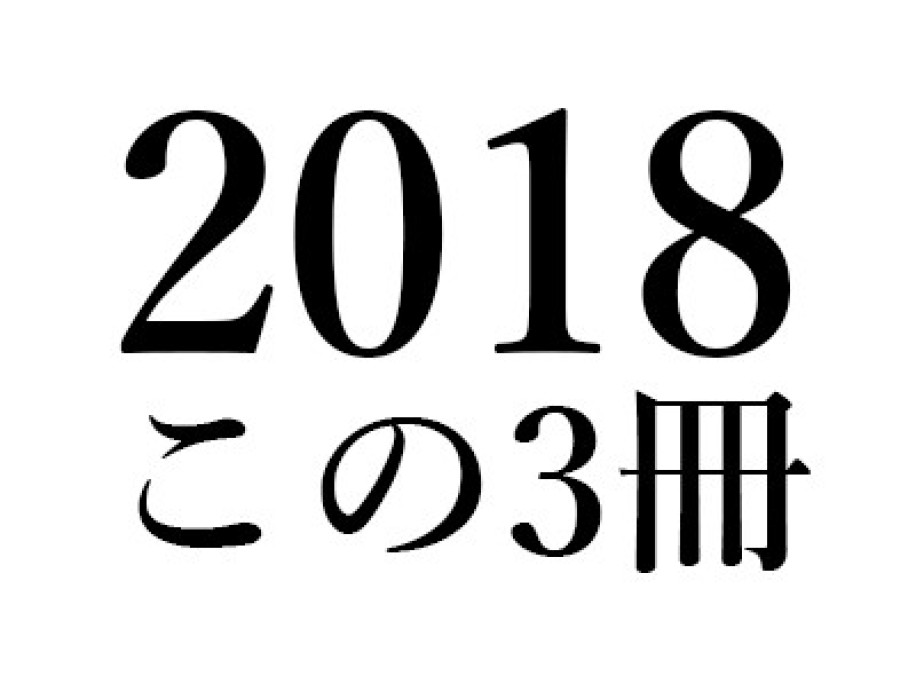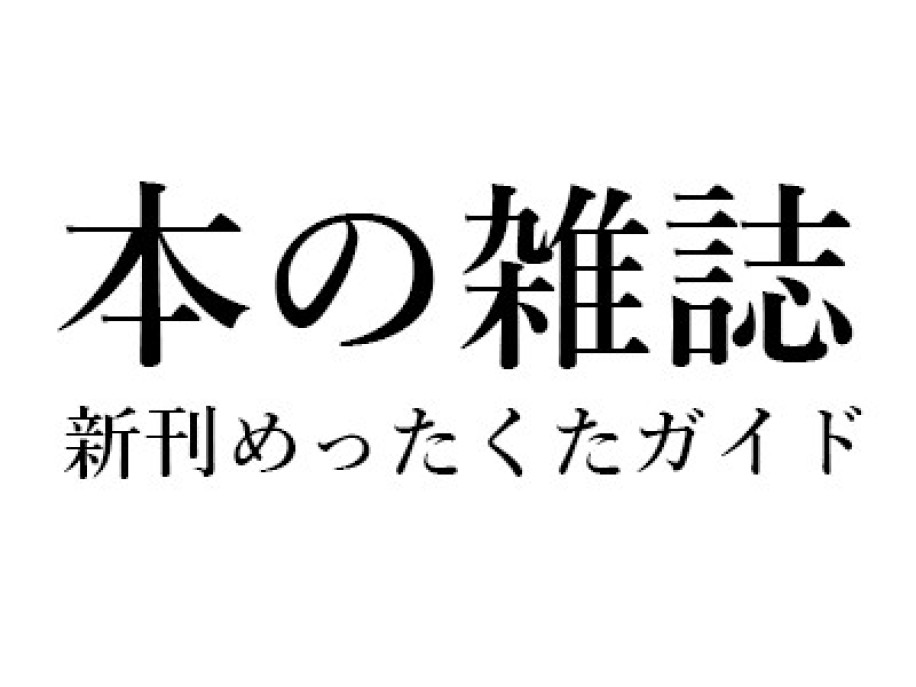書評
『十五の夏』(幻冬舎)
人生をふりかえらせる力
十代半ばころの団塊世代にとって、ソ連といえば『ドクトル・ジバゴ』だった。詩人パステルナークの小説でノーベル文学賞に選ばれたのだが、受賞すれば祖国に戻れないという政府の圧力で作家は辞退する。原作を読んだかはともかく、数年後に映画化されたので、それを観(み)た青少年は少なくなかったはずだ。それから十数年と経(た)たない一九七五年、十五歳の高校一年生が夏休みの四十二日間に独りでソ連・東欧圏を旅行したのだ。それだけでも事件である。決意したマサル少年もさることながら、資金援助をして許した両親もなかなかのもの。もっとも、横浜港に帰り着いて電話をしたら、とにかく大宮の自宅までタクシーで帰ってきなさい、と母親の命令である。わが子の旅行中、心配のあまり何度も寝込んでいたというから、なるほどと涙をさそう。
そもそもハンガリーの二歳年上のフィフィと英語で文通していたのが機縁だった。マサルはフィフィ一家とともに生活する。観光地や博物館よりも普通の人々の生活風景に目は向かいがちだった。好奇心が旺盛で物怖(ものお)じしないせいか、何事も聞きただし究めようとする。外観をながめるだけではなく、物事の仕組みを知ろうとする姿勢が後の卓越した分析家の姿と重なり印象的である。
家のなかで洗濯物を干したり、下着にまでアイロンをかけたりする風習を不思議に思い、アイロンが消毒になると考える文化の違いに納得する。とくに、飲食物に対するマサル少年の関心は目をみはるものがある。とうとうフィフィ一家のために炒飯(チャーハン)を作ることになり、食材を事細かにメモして渡すのだから、とても十五歳の少年とは思えない。
やがてルーマニアに着くと、チャウシェスク大統領の肖像画の多さに驚く。なじめない雰囲気にさんざんな思いをしながら、やっとのことでキエフに着き、ソ連に入国した。ここでは、送迎、ホテル、観光ガイドなどの何事にも管理システムがはりめぐらされている。同じ社会主義国といっても、チェコスロバキア、ポーランド、ハンガリーはやはりヨーロッパの国だったと気づく。東欧諸国に比べてソ連が閉ざされた世界であると肌身で感じたのだから、その経験はひとかたならぬ重みになったはずだ。
モスクワに着いてレーニン丘の展望台に上ると、首都の美しい全景が目に入り、ソ連を訪れたという実感がこみあげてきたらしい。ほどなくモスクワ放送の日本課長を訪ねて話しているうちに、ラジオ番組に出演することになった。もともとモスクワ放送の日本語番組を聞きながら、しばしば感想文の手紙を書く常連だったというから、その凝り性ぶりも出色である。
モスクワで完結しないのがマサル少年の独り旅の凄(すご)さである。中央アジアを見ずしてソ連を語れないと思っていたらしい。サマルカンド経由でブハラに着きホテルの部屋でシャワーを浴びると、鉄錆(さび)の混ざった赤い水だった。
ウズベク人はイスラム文化圏にあるが、お酒はロシア人よりも強いという。バザールをのぞいて食材の豊富さにあらためて驚く。タシケントは近代都市になっており、ホテルの風呂もお湯が出てゆっくりできた。とはいえ、中央アジアにあってもソ連の監視体制は色濃く、地元の人々とふれあう機会はほとんどなかったという。
本書には読者をして自分の人生をふりかえらせる力がある。あらためて自分がほんとうに好きなものは何であるのかを問い直してみたくなる。まぎれもなく青春紀行文学の傑作である。
ALL REVIEWSをフォローする