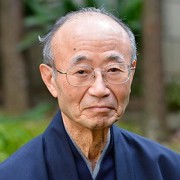書評
『仏と霊の人類学―仏教文化の深層構造』(春秋社)
「死ねばホトケ」信仰の奥に
インドの民主主義とアメリカの民主主義が違うように、インドの仏教と日本の仏教もその性格を大きく異にしている。この至極あたりまえのことが、仏教学や思想史の分野では、これまでかならずしも自覚的に追求されてはこなかった。
一例をあげよう。わが国では、人が死ぬとホトケになるという。成仏した、ともいう。死んでホトケになることを誰もが信じていたのである。それが日本語としても市民権をえてきた。ところが周知のように、本家本元のインドの仏教では「仏」とは悟った人のことをいう。死者を仏と称するような事例は、インド仏教のどこを探してもみつからない。事情は、中国や東南アジアに伝わった仏教でも同じである。どうしてそういうことになったのか。その謎(なぞ)が解ければ、日本仏教の性格がわかるだけではない。日本人の精神や信仰の特徴があぶりだされるはずだ。
この魅力あるテーマを、文化人類学の手法で明らかにしようとしたのが本書である。著者は東南アジアや華僑社会で綿密なフィールドワークを積み重ねてきた宗教人類学者であり、とりわけシャーマニズム(神がかりや霊界体験)の研究分野では第一人者と目されてきた。その広い視野から日本仏教の現状を見渡して、そこに民俗信仰の中核をなす霊魂観が大きな作用をはたしてきたことに着目したのである。
自然の万物に霊魂が宿っているように、人間もまた霊魂の宿りどころである。その霊魂を日本人はタマと呼びならわし、死んでのちこのタマがカミになったりホトケになったりするという独自の信仰を発達させた。仏教と神道がタマ信仰というアニミズムの洗礼をうけて結びつき、仏(悟った人)すなわちホトケ(死者)という重層的な観念が生じたというわけである。
最後に一言。データが曹洞宗関係のものに偏っており、そのためか、主題にとって重要な、日本人の浄土観の検討が抜け落ちている。再考すべきところだろう
ALL REVIEWSをフォローする