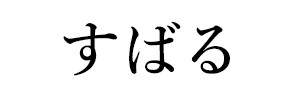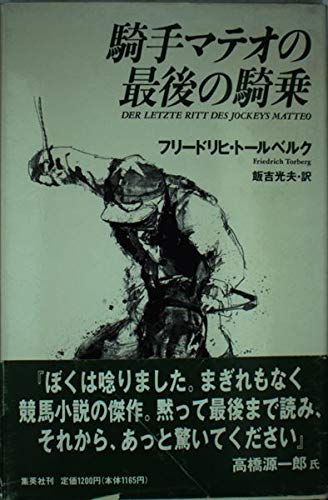書評
『日本・現代・美術』(新潮社)
楕円軌道を認識すること
「あらかじめ断っておくが、『日本・現代・美術』と題されているからといって、これは、日本の現代美術史を扱うものではない」という一行から語り起こされる本書は、第二次世界大戦と呼ばれる「暴力」の「忘却」に基づく戦後の、「あらゆる表現行為」に張りついた矛盾を、明快な論旨で暴き出した力業である。「日本現代美術」とは、独立して存在している空間ではなく、対外的には「暴力」でしかない「平和」の仮面をかぶった「現実」の、つまりいっさいの歴史から切断されている「閉ざされた円環」のなかで堂々めぐりを繰り返す「現在」そのものだと述べる椹木氏は、みずからもおなじ「円環」の内側で生きるほかない運命を真正面から見据え、その運命に目をつむろうとしてきた近代以降の日本に対していらだちをぶつけるのだが、ここで重要なのは、先の「円環」が、じつは真円ではなく、『復興期の精神』(講談社学術文庫)の花田清輝とともに、歪みのある「楕円」と見なされていることだろう。赤瀬川原平や岡本太郎らの意義を再検討に付す章に横溢する冴えた共感が、作家論の枠に収まらず、つねに巨視的な思考のうねりを見せるのは、この「楕円」の認識によっている。
楕円である以上そこには複数の焦点があり、架構された完璧な真円には見られない、ばらばらでいびつな、それゆえに豊沃な細部がうごめいている。この楕円のなかで、「もの派」「読売アンパン」「アンフォルメル」といったさまざまな「前衛」が、それぞれに焦点を結ぼうとして弾け飛んできたのであり、著者の目はこれら複雑な軌道の中心と弾け飛んだ残骸の軌跡をけっして見逃さない。「あいまい」を通り越して「スキゾフレニック」になった日本の「現代」を皮切りに時代を遡行し、「現代」という言葉が「現代美術」の起源を創出するばかりでなく、近代の歴史を覆い隠す機能をも備えていた事情を鮮やかにたどったのち行き着く最終章は、冒頭の予告どおり本書が美術論の枠を超えた思考の産物であることをはっきり示している。すべての超越的価値が崩壊したあの敗戦の日、頭上に広がっていた抜けるような「青空」の現象学的な意味が解かれるとき、おそらくその「青空」は、やはり忘却によって歪曲された「戦後文学」の楕円軌道の内部でも仰ぎ見ることが可能なのだ。雑誌連載ゆえの適度な反復も冗漫さに陥ることなく、あくまで明晰な論理の道筋と熱のこもった文章とで、美術に疎い読者をも最後まで摑んで離さない。「日本現代美術」が自明のものではないことを、わずか中黒ふたつで解きあかしてみせた着想と勇気に、深い感銘を受けた。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする