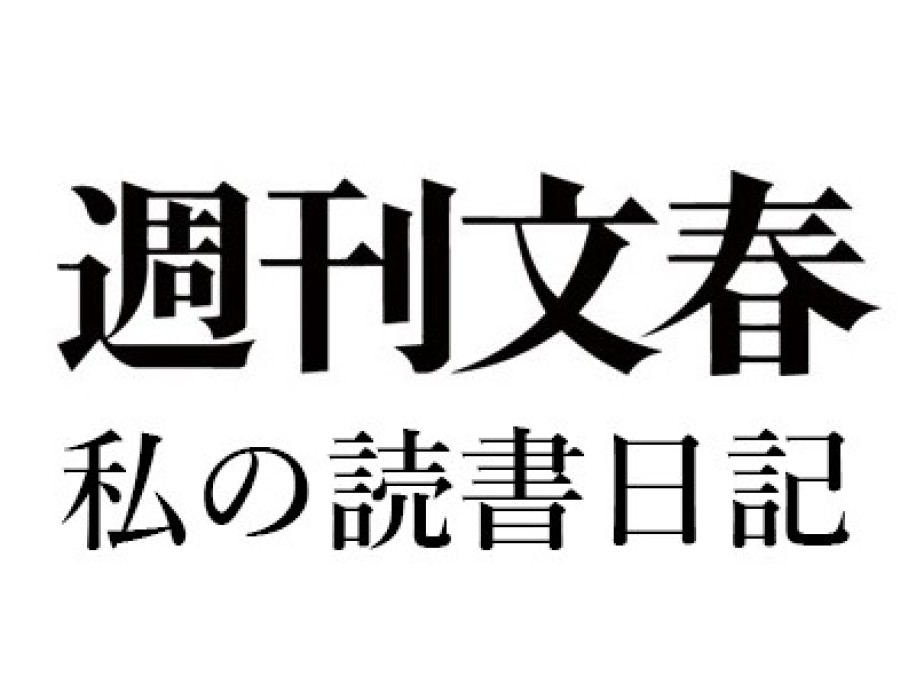書評
『主婦マリーがしたこと』(世界文化社)
たった五十年前のこと
本ばかり読んでいたら目がちかちかしてきた。きのうは深夜、『ミッドナイト・コール』(上野千鶴子著・朝日文芸文庫)を読んでいた。上野さんはよく「なぜ産まなかったの」と挨拶代わりに聞かれるらしい。悩みは逆で私は「どうして三人も産んだの」としょっちゅう。「ハァ、成り行きで」「つい出来心で」「できやすい体質かも」……「まァ、せめて“授かった”くらいおっしゃいよ」と眉をひそめたおばさまもいる。男はいい。父親に「なぜ三人も産ませたの」とは聞かないだろうに。
映画になって公開され、さほど評判にもならなかったが、フランシス・スピネル著、福井美津子監訳『主婦マリーがしたこと』(世界文化社)が本棚の隅にあったので再読してみた。
驚くべき本である。いまからたった五十年前、一九四三年七月、人権の国フランスで、四十歳の女性が「堕胎を施した罪」で死刑になっている。名はマリー=ルイーズ・ジロー、シェルブール市の主婦。パリのカフェではサルトルやボーヴォワールが哲学を論じていた頃である。
彼女は貧しい育ちの水兵の妻、洗濯屋だった。五人の子を産んだが二人しか育たなかった。夫は船乗りでめったに家に帰らない。要するにどこにでもいそうな所帯やつれした主婦。
同じ水兵の恋人を持つジゼールが、望まないでできた子を堕すため、芥子湯に足をひたしているのを見た。
「そんな方法じゃだめよ!」
「じゃあ、別のをやってみるわ。石鹸水をなかに……注入すればいいって」
ひょんなことで浣腸用のゴム球を使ってはじまったこの危なげな施術。ジゼールは苦しんだが中絶はうまくいった。すなわち人生を台なしにしないですんだのだ。つまり最初は困った同性を助けるため。次の女性からはお礼を受けとった。あそこへ行けば助けてくれる。その噂は広がり、マリー=ルイーズはだんだん金に汚なくなった。愛人をこしらえ、生活は派手になる。そしてある日、警察の手入れがあった。
第二次大戦下のフランスでは堕胎は禁止。もちろんヤミでははびこっている。彼女を頼ってきたのは、戦地に恋人を送り出した少女、夫がドイツで捕虜になっている間、行きずりの情事で妊娠した人妻、四人目の出産で苦しんで五人目は産みたくない主婦、などである。マリー=ルイーズは金もうけをしながら一方で、自分を“人の役に立つ女”と思っていた。それは甘かった。
戦時中、日本でも「産めよふやせよ」が奨励されたように、ナチスに屈服したヴィシー政権下、ペタン元帥は敗北の原因が「子どもと武器が少なすぎた」ためとして、出生率向上のキャンペーンを張る。そして堕胎施術常習者を「国家に対する殺人者」として死刑にできるよう法律を改悪したのだった。
女性の弁護士である著者は、数十年前の「ジローの妻事件」の裁判書類を発掘し、じつに淡々と記述していく。文飾は少ないが映像的な鮮明なシーンが積み重ねられる。しかしどうしても一九四〇年代のこととは思えないのだ。読んでいて脳裏に浮かぶのはマリー・アントワネットの時代のような服を着た女たちだ。それほど時代錯誤な事件である。
「マリー=ルイーズ・ジロー裁判に関する一件資料をひもとけば、正義が空間と時間において相対的であることをまのあたりにし、めまいに襲われずにはいられない」と著者は書く。じっさい、処刑から三十年たって一九七五年、フランスでは妊娠中絶が合法化された。ようやく、というべきか。しかしフランスでも日本でも、いや世界中でいまだに、「望まぬ妊娠」は女の側だけに、深くかかえ込まされている。
いつになったら男の人が、それをわがことのように考え、産むか産まないかの決定にともに悩み、受けた傷も共有できるようになるのか。それを考えるとめまいがした。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア

毎日夫人(終刊) 1993年頃
ALL REVIEWSをフォローする