書評
『イエズス会がみた「日本国王」: 天皇・将軍・信長・秀吉』(吉川弘文館)
天下人を注意深く観察
フランシスコ・ザビエルが日本にキリスト教を伝えたのはよく知られている。彼はカトリックのイエズス会という修道会の創立者の一人。そしてアジアへの熱い布教の使命を抱いて来日した。本書は、ザビエルをはじめとするイエズス会の宣教師たちが、布教活動を通じて関わった天皇、将軍や戦国大名、織田信長、豊臣秀吉といった天下人の権力や権威のありようを注意深く観察していたことを解き明かしてくれる。
同会の布教方針は、対象とする布教地の権力者を改宗させるか、その保護を求め、その下で領内の布教を効率的に行うというものだった。
そのために宣教師たちは日本社会の権力構造を正確に把握することが必須になった。彼らは西から畿内に進出するにつれて、その権力構造の理解を深化させていく。当初、天皇を将軍と同じ「国王」と見ていたが、将軍と異なる「Vо(皇)」という特別な権威の存在であることに気づく。
宣教師たちは、日本の中世以降の歴史を、権力が次第に移行していく過程ととらえた。当初天皇が将軍や大名たちを従えていたが、戦乱とともに将軍が実権を握る。さらに戦国大名へと権力が移って、天皇と将軍の権力が失われた一種の「連合国家」だと洞察した。
また彼らが戦国大名を「(その地域の)国王」とも呼んでいるのは、現在の戦国時代の国内研究においても、戦国大名の領国を「地域国家」ととらえていることと一致していて興味深い。
最後に著者は、宣教師たちの認識する日本王権の特徴が、中央(京都)と地方の重層的な構造であり、日本の王権が天皇と武家の両者によって成り立っていたと結論する。
はるばる西欧からやってきた宣教師たちは布教の拡大のために、日本社会を緻密かつ合理的に分析していたことを、本書から実感する。異文化との遭遇という視角から、歴史の別の素顔を教えてくれる一冊である。
[書き手] 桐野 作人(きりの さくじん・歴史作家)1954年、鹿児島県生まれ。武蔵野大学政治経済研究所客員研究員。主な著書に『織田信長 戦国最強の軍事カリスマ』KADOKAWA〈新人物文庫〉、『真説本能寺』『関ヶ原 島津退き口』ともに〈学研M文庫〉、『さつま人国誌 戦国・近世編』南日本新聞社、『龍馬暗殺』『本能寺の変の首謀者はだれか』ともに吉川弘文館など多数。
初出メディア
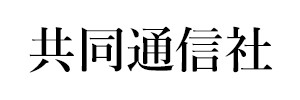
共同通信社 2020年11月
ALL REVIEWSをフォローする





































