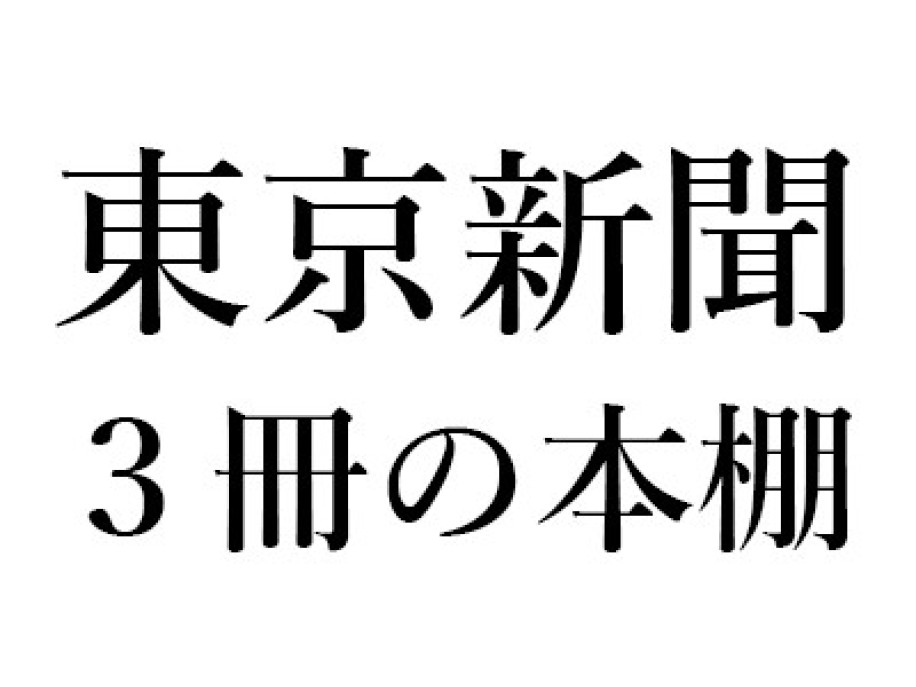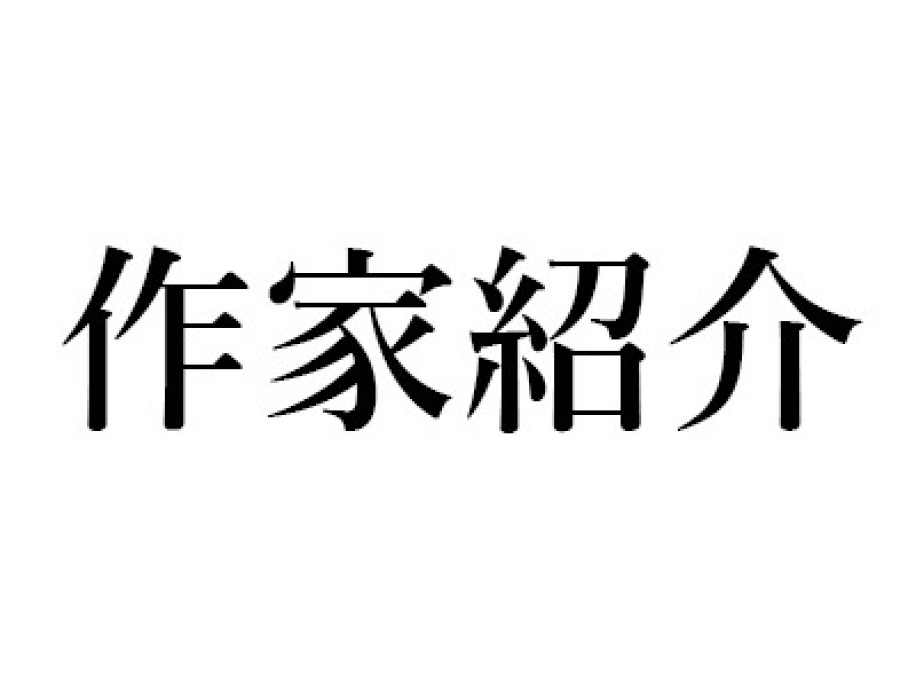書評
『羽生 21世紀の将棋』(朝日出版社)
スパコンと羽生と将棋と文学
実は、わたくし、将棋の羽生七冠王と「対局」したことがある。将棋で?まさか。モノポリーである。羽生七冠王に、糸井重里魚釣王を含む豪華メンバーで行われたその「対局」では、前半大きく出遅れながら直線鋭く追い込んだ羽生七冠王の豪脚に目を見張った。いや、それより「すいません。あなたのお持ちになっている黄色いカードニ枚とわたしの側の鉄道会社二枚との交換に関して交渉させていただけないでしょうか」というあまりにも丁寧な交渉態度に、思わず「ご親切な提案、さっそく社に持ち帰り上司と相談の上、ご期待に沿えるような回答を致したいと存じます」と口走ってしまったことが思い出深い(ウソ、ウソ)。
棋士という種族の頭脳は、「コンピューター」と呼びたくなるような作りになっているが、中でも羽生さんはその代表的存在といわれている。回転が早く、記憶力ものすごく、勘に優れ、さらに付け加えて文学好きでユーモアたっぷり、と話していてこっちが嬉しくなってしまうような方だけに、「文学」戦線の側からその中身をぜひ検討してみたいと思う人が現れてもまったく不思議ではない。
それが、保坂和志小説王の『羽生 21世紀の将棋』(朝日出版社)だ。
『羽生』のなにより素晴らしいところは、徹底して将棋について書かれていることである。この本の主人公である羽生さんは将棋のチャンピオンだ。だから、羽生さんが将棋のどの部分で時代を画しているのかがわからなければ、彼のすごさはわからない。しかし、わたしのように将棋がほとんどわからない人問は、どうやって羽生さんのすごさをわかればいいのか。
保坂さんは、将棋をわからない人間にも理解できる言葉を使って、羽生さんが指している将棋のすごさを説明しようとした。この場合、著者には「禁じ手」がある。それは、将棋のすごさを他の何かの「比喩」で説明してみることである。もちろん、著者はそんな馬鹿なことはしない。ハナから無視している。なぜなら、将棋という特別の規則を持った世界のすごさを、その規則を知らない人間にも説明できるのが「言葉のすごさ」であることを著者はちゃんと知っているからである。
さて、羽生さんの指す将棋とはどんなものなのか。簡単にいうなら、こういうことではないかと思う。
将棋は特定の数の駒を特定の数の枡目に置いてゆき、最後に相手の王を奪取するゲームである。結論に至る道はたくさんあるが、それは無数ではない。その膨大な数の道筋の中で、自分も敵も最高の(というか最善の)選択をし続ける。そして浮かび上がってくる将棋という規則の本質を見極めたい……。
将棋というゲームの中で、棋士は「指す」。しかし、「指す」よりもっと重要なのは「読む」ことなのだ。そのことに気づくと、読者は、この本が「将棋」について語っていながら、自動的に「文学」についても語ってしまいそうになっていることを知るだろう。
そして、この本の最後近く、わたしたちはこんな文章に出会う。
これは私ひとりの予想だが、計算と記憶の力業を能力の中心とするコンピュータ将棋(これは人工知能も同じだろう)が人間と対等に指せるようになったとき、力業では絶対にコンピュータに勝つことのできない人間の将棋は、将棋のとてもエレガントな面を発見しているのではないか
言葉もまたさまざまな酷使に耐えた後、なお生き長らえることができるとするならそれはその「エレガントな面」なのではないか?
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする