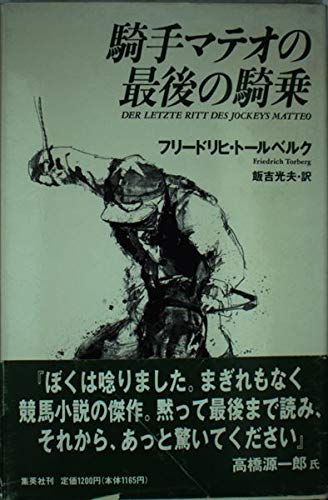書評
『言語表現法講義』(岩波書店)
加藤典洋さんの『言語表現法講義』を読んでバラバラな感想
加藤典洋さんの『言語表現法講義』(岩波書店)を読んだ。読んでいる時間より、頁から目を上げて、あれやこれや考えたりしている時間の方が長かった。それは、最高の読書をしたということだ。もちろん、「最高」の読書には、それを読んでいたらその本から出られなくなってしまったという形態もあるが、ぼくは、考え事をしている時間の方が長くなっちゃったという方が好きだ。とにかく、ぼくはあれやこれや考えた。というより、バラバラな感想がたくさん浮かんだ。たとえば、①自分が取り上げられている箇所を読んでいると、やっぱり恥ずかしいな。
②加藤さんは、「言語表現法」という授業を大学でやって、それは「言語表現」を学生に教えることなんだが、なぜ「法」かというと、言語表現「学」ならほとんどが「頭」で考えるだけの理論になり、言語表現「論」なら少し実践的になって「手」を通じて、つまり実際に書くことを通じる度合いが多くなり、そして言語表現「法」では「頭」と「手」がフィフティ・フィフティになるといっているが、「手」の割合がさらに多くなっていくとハウツーに近い「術」になると付け加えた、ぼくはこの辺を読んでいてなんだかニッコリしてしまった、それはぼくが長い間やりたいと思ってきてまだ実現できずにいることで、それは「小説教室」なんだが、加藤さん流にいい換えると「小説表現・術」となるだろう、そして小説表現を「術」として描くためには、不思議なことにそれ自身も小説になるしかないとぼくは思っているし、きっと加藤さんも同意してくれるだろう、その「小説教室」はこんな風にはじまるはずだ、「先生」が教室に入っていくと、「生徒」が三人机についている、その三人というのは、おばあさん(おじいさんでも可だがやはりおばあさんが望ましい、おとうさんでも可かもしれない)、女子高生(女子中学生でも可だがやはり女子高生が望ましい)、カエル(リスでも羊でもゴジラでも可、アリは条件付きで可、犬は不可、ウィルスは要面談、猫は当猫次第、人間が変身したものは絶対不可)だ、「先生」はまず生徒たちに前回提出させた文章(小説を書くためにはまず文章を書かなければならない、だから最初の部分は加藤さんの「言語表現法」とほとんど重なっているともいえる)を採点して返す、厳しい評点をもらった生徒たちのブーイング、ちなみにその講義の第一回の課題は「なぜこの授業を受けようと思ったのか」で第二回の課題は「私について」となるはずだった、ぼくが加藤さんの本を読んでいてニッコリした理由をわかってもらえると思う、加藤さんの講義の課題の一回日と二回日はぼくが書くはずのそれとまったく同じだったのだ(!)。
③加藤さんは、この本を学生に対する授業として書いた、それは「法」という形になった、この本が活き活きしているのはそのせいでもあるけれど、同じことを文芸雑誌に書いてもこんな風にはならなかっただろう、それはたぶん、文芸雑誌が「論」や「学」ばかりでできているからだし、文芸雑誌でもう一つイヤなのは加藤さんが「マッチョな」文章と批判している「書き手と言葉」が「一対一対応」している文章で充満しているからで、そこではまだなにか古めかしいものが信仰されている、信仰自体はいいとしてもそれが「下品」で「物欲しそう」に見えるのはなぜだろうか、そうそうぼくがこの本を好きなのはなによりも「嗜みがあって上品」(decent)だからなのだ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする