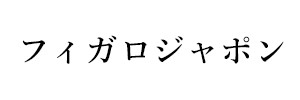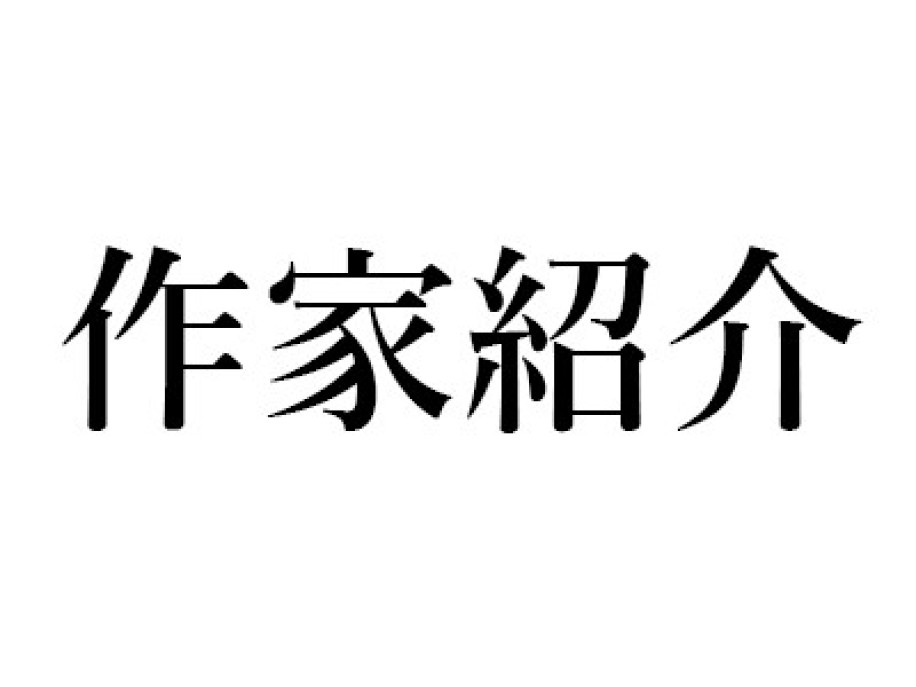作家論/作家紹介
ビオイ=カサーレス『モレルの発明』(水声社)、ギジェルモ・マルティネス『オックスフォード連続殺人』(扶桑社)、他
ボルヘスから受け継がれる、知的幻想の遺産。
ボルヘス、コルタサル、プイグに代表されるアルゼンチン文学とはブエノスアイレス文学であり、最大の特徴は知的幻想性と言える。それはボルヘスの作風の代名詞でもある。彼の短篇の多くは純粋な虚構からなり、バロック的博識が幻想をもたらす。そこに見られる論理ゲーム的な遊びやユーモアは、世界の作家、思想家、芸術家ら、様々な分野の人々の思考を刺激し、想像力を掻き立ててきた。ボルヘス以後の作家達。
ヨーロッパ系の移民が多いこの国では、ラテンアメリ力の中では例外的に早くから推理小説やSFが書かれ、ボルヘスや彼との共作もあるビオイ=カサーレスらは、そうしたジャンルにも手を染めている。そして新世代の作家ギジェルモ・マルティネスのミステリーがボルヘスの作品を意識して書かれているように、文豪の遺産は世代を越えて受け継がれているのだ。ボルヘスに才能を見出されたコルタサルも魅力的な幻想小説を得意とした。日常の現実に突如亀裂が走り、幻想が滲み出てくるのが特徴で、分身や現実と夢の逆転といったモチーフを使い、彼は物語をスリリングに展開させる。コルタサルの後年の作品は政治性を帯びるが、それは彼のユートピア志向が、軍事政権による圧制という現実に着地したことによる。
そんな中でプイグは異色の存在だ。エリート文学とは一線を画し、女性やゲイ、病人といったマイノリティーの眼差しで世界を眺め、男性やシステムの暴力性を鋭く批判し、新しい風を吹き込んだ。
J.L.ボルヘス『伝奇集』(岩波文庫)
少年時代に作家になることを決意したボルヘスは、豊富な読書量を生かしパロディや抽象的な作品を書き始める。『伝奇集』には『ドン・キホーテ』を越える作品を書こうとしてそっくり書き写してしまう男の話など代表的な短篇が収められている。国内では長らく理解されなかったが、国外では早くからポストモダンの教祖として高い評価を受けた。フリオ・コルタサル『コルタサル短篇集 悪魔の涎・追い求める男』(岩波文庫)
コルタサルは反ペロン独裁運動に関わってパリに亡命、幻想的な作品の多くはヨーロッパを舞台にしている。この短篇集には、高速道路上にユートピア空間が生じる話や、ラストで墜落する飛行機の乗務員が見た夢と現実が交錯する話、主人公のモデルがチャーリー・パーカーという、いかにもジャズ好きの作家らしい話などが収められている。マヌエル・プイグ『蜘蝶女のキス』(集英社文庫)
地方出身のプイグはエリート作家ではない。最初、映画監督を目指すが挫折し、小説に転じたところ特異なスタイルが評価される。だがペロン派政権の下で弾圧され、自主亡命の道を選ぶ。『蜘蛛女のキス』は主に同じ監房で交わされるゲイと革命家の対話からなり、ゲイの男の心理を反映した映画のストーリーが誘惑の道具となるところが圧巻だ。ルイサ・バレンスエラ『武器の交換』(現代企画室)
本書は亡命女性作家による短編集。作品には決まって男女が登場し性描写がある。主人公は女性で、肉体的快楽は自らの身体性を回復する手段であり、他者である男とコミュニケートもしくはディスコミュニケートすることで「女」という自己同一性を回復する。方法意識が強く、文体は硬質で緊張を帯びているが、それは亡命を促す政治状況から生まれるものでもある。マヌエル・ムヒカ=ライネス『七悪魔の旅』(中央公論新社)
職人的作家だった著者の作品には、ブエノスアイレス物とヨーロッパ物の二つの系列がある。邦訳された『ボマルツォ公の回想』は後者の代表作だが、本書は地獄の大魔王の命令を受けた七悪魔が時空を越えて自由に飛び回り、ローマ帝国時代のポンペイ、西太后時代の中国、未来のシベリアなどに出かけて標的に罪を犯させるという、著者には珍しいSF的ユーモア小説。ホルヘ・ブカイ『寓話セラピー』(めるくまーる)
著者は1949年生まれの精神科医。本書は著者と同名の医師と患者の青年がセラピーの診療室で交わした会話および医師の語る51の断片的テキストからなっている。それらの診療用テキストは、著者の創作と世界の民話や寓話などの改作の混じったものなのだが、この原作の語り直し及びそこに創作を混ぜるという手法は、興味深いことにボルヘスのそれに通じている。トマス・エロイ・マルティネス『サンタ・エビータ』(文藝春秋)
著者にはボルヘスが生涯嫌悪した独裁者ペロンに関する小説があるが、本書はその妻エビータことエバ・ペロンを主人公にした小説。彼女の生涯と死後の物語が同時に進行していく。聖女として崇められる一方悪女として呪われる彼女の存在は、アルゼンチン人にとって強迫観念となっている。社会の矛盾が生んだエビータ神話を著者は公平な目で描き出そうとする。アドルフォ・ビオイ=カサーレス『モレルの発明』(水声社)
ボルヘスの影に隠れがちな著者だが、本書で若くして頭角を現した。漂流者が孤島に辿り着き、そこで毎日決まった時間に男女が群れ集うのを隠れ見る。彼はその中の女性に恋してしまう。しかし、それは波を動力源にして半永久的に動く映写機による映像だった。著者にはこうしたSF的作品がある。ただし愛のテーマにより、人間の哀しさを浮かび上がらせるのが特徴だ。ギジェルモ・マルティネス『オックスフォード連続殺人』(扶桑社)
1962年生まれの著者は早熟の作家。また数理科学の博士でもあり、オックスフォードに留学している。本書にその経験が反映していることは言うまでもない。アルゼンチン人留学生である「私」が、不可解な殺人事件の謎解きをする世界的数学者の活躍を語るのだが、ボルヘスの短編を踏まえたこの知的ミステリーは、作中人物ばかりか読者も罠にかけようとする。ALL REVIEWSをフォローする