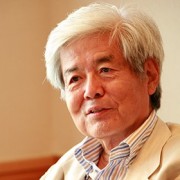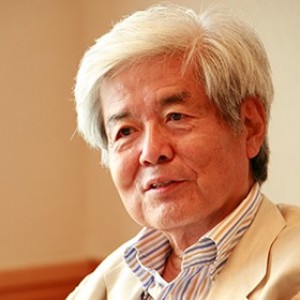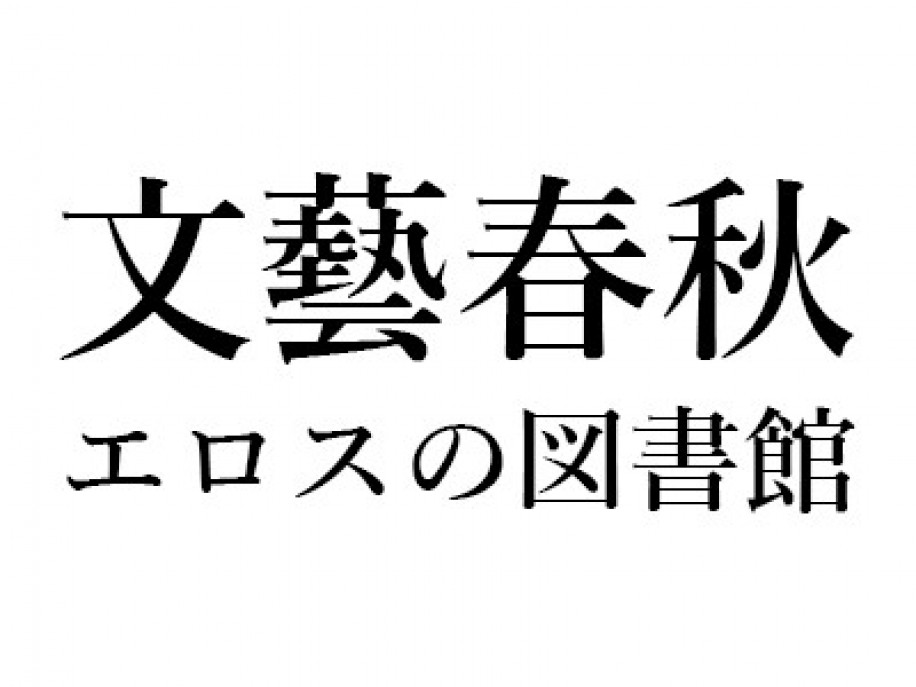日高 敏隆『チョウはなぜ飛ぶか』(岩波書店)、金子 修治,鈴木 紀之,安田 弘法 編『博士の愛したジミな昆虫』(岩波書店)
大好きな虫をもっと知りたい君たちへ
子どもたちはなぜか虫が好きである。そのまま変わらず大人になる人もいて、虫の専門家になってしまったりすることもある。この二冊はいずれも世間的にはその種のいわばヘンな人たちが書いた本である。私には素直に面白かったが、ふつうの人もそう思うかどうかは、私にはわからない。ただ子どもたちにはぜひ読んでもらいたいとしみじみ思う。
日高敏隆の本は古典的な名著であろう。日高は子どもの頃、チョウが好きで、チョウが決まった道筋を飛ぶのに気づく。家で飼って親になったチョウでも。放せば野生の個体と同じような道筋を飛ぶ。これをチョウ道という。チョウは「なぜ飛ぶか」というより、チョウは「いかに飛ぶか」と言うべきであろう。科学は初めは「なぜ」から始まるが、実際に調べ始めると問題は「いかに」になってしまう。戦後の社会状況が悪い時代に、日高は千葉県に通い、協力者とともにチョウが谷のどこを飛ぶかを記録し、図示する。こうしてチョウ道がどのように成立しているかを明らかにした。研究者になってからは、雄が雌を発見するのに、どのようにしているのか、本書にはその研究過程が具体的に丁寧に記されている。こうした報告に比べると、科学論文は電報みたいなものだと感じられる。電報は読む時間の節約になるけれども、読んで面白いものではない。虫を自分で調べたいと思っている子どもたちには、大変に良い参考書になると思う。
『ジミな昆虫』の方はチョウやカブトムシやクワガタのような派手ではない虫を研究対象にしている、主に若手の研究者の報告である。五章からなっていて、それぞれ扱われている虫やテーマと書き手が違っている。第一章は鈴木紀之によるナミテントウとクリサキテントウの住みわけ。第二章は東樹宏和によるツバキシギゾウムシの長い口吻とツバキの実の殻の厚さとの関係、いわゆる軍拡競争、さらに村瀬香による植物アリとオオバギ属の植物とのコミュニケーション。第三章は塩尻かおりによるモンシロチョウと寄生蜂との関係、第四章は外来種が主題で、辻和希がヒアリ、アルゼンチンアリを、さらに田中幸一がブタクサハムシを扱う。第五章は桐谷圭治が農業害虫を農薬を中心に論じる。全体として主題は虫同士の関係、虫と環境との関係を扱う生態学である。こうした報告を読んでいて、著者たちが自然に対して感じているリアリティーは、現代人の大多数が映像画面を通して感じているものと全く違うのではないかと思ってしまう。子どもたちがなにに対して、どのようにリアリティーを感じるか、それが将来の社会のあり方を定める。それは教育内容の問題ではない。五感を通じた日常生活のあり方が基本であろう。
自然物を具体的に素直に観察するのは、老人であれだれであれ、飽きない行為である。ヒトの行為を私は対人と対物とに分ける。現代の社会生活では対人が主となり、対物はやや例外的である。しかしヒトが対人関係だけに没入するのは危険であろう。若い頃に私は対人関係が苦手だったから、臨床医学ではなく基礎研究への道を選んだ。対人関係は世間に出れば、どうせ連日イヤというほど訓練を受ける。そういう世界で、モノを見ながら一生を過ごせるのは、幸せなことかもしれないと思う。私はとくに人間嫌いではないが、時おり人間はもうたくさんだと感じたりする。現代社会とは、人間どうしがお互いのことばかり考えて、要するに人間の自家中毒ではないかと言いたくなる。小さな虫たちもこの地球上を三十数億年生き延びてきた同僚である。その間にありとあらゆる災厄を通り抜けてきたのだから、そう単純に生きているはずがない。
虫を調べていると、生態も形も、よくもまあここまで凝ったものだ、と感嘆することも多い。ここで取り上げた二冊からも、それは推測できると思う。いまさら虫の世界なんかに頭を突っ込む気がまったくない人でも、本書を子どもたちにプレゼントしたり、読むことを勧めてみてもいいのではないかと思う。この種の研究をしていると、実験室の科学者から「子どもの科学」とバカにされることがある。たしかに科学者は特殊な専門用語や概念を操る。化学では水はH2Oだが、子どもたちはHもOも知らない。しかし水もお湯も、雨も雲も水蒸気も知っている。知っていることだけを使って対物、つまりヒトではない外の世界を理解しようとすると、子どもの科学と言われてしまう。それがまさに子どものすることだからである。逆にそこからだれにでも理解できる科学が始まる。今では専門家会議が開かれて、あれこれ決まるが、お互い話が通じているのだろうかと疑問を感じているのは、私だけではあるまい。子どもの科学には、その心配は要らない。科学とは要するにものごとの当たり前の説明なのである。