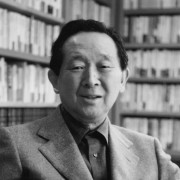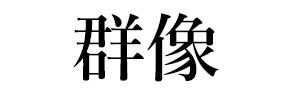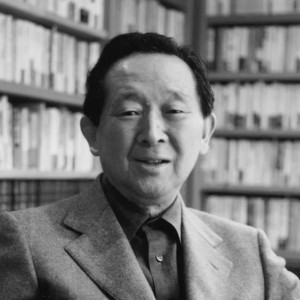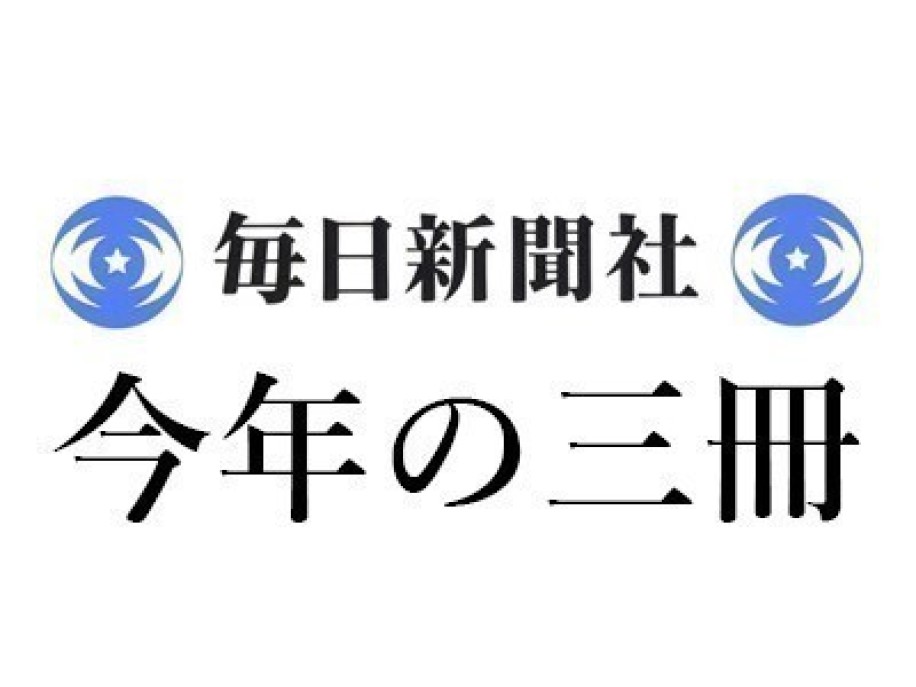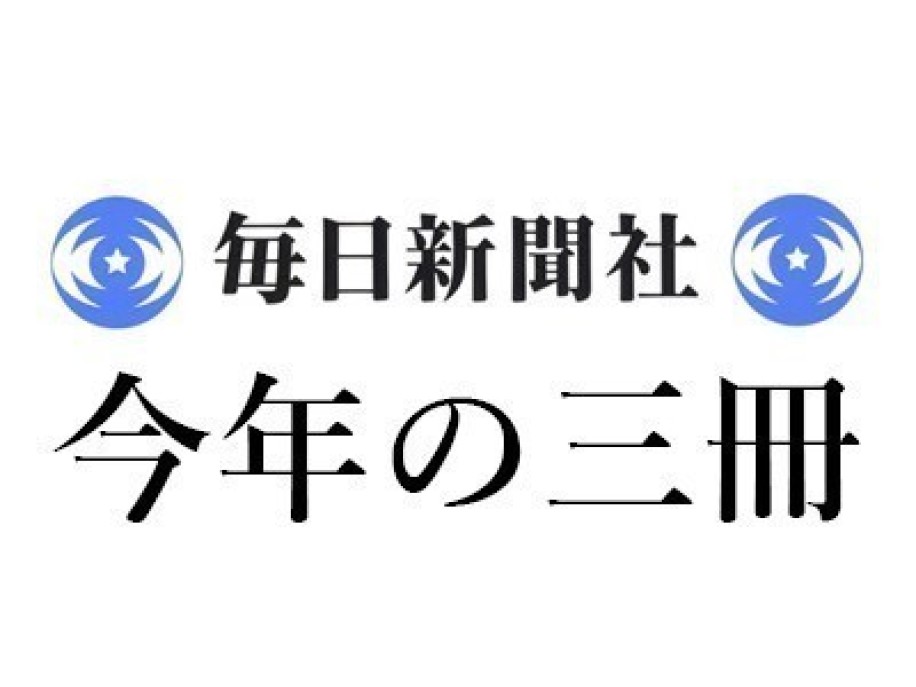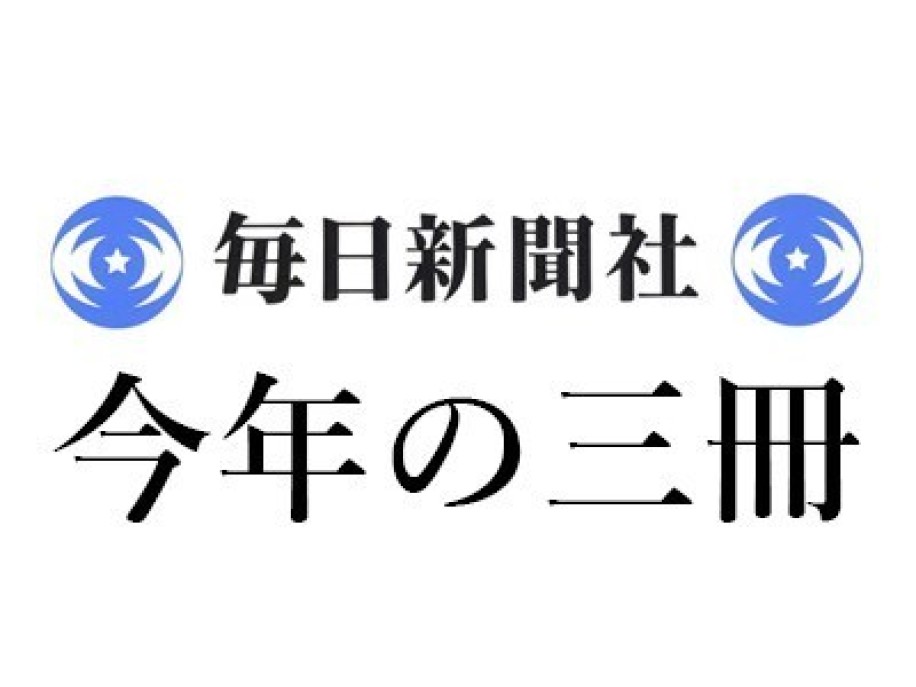書評
『天府 冥府』(講談社)
この作品は満洲(現中国東北部)の端、ソビエト(ロシア)国境に近い町佳木斯(ヂャムス)を中心に、日本が戦争に敗けてその地を追われるまでの著者の幼時の記憶が素材として使われている。
彼女の最初の人生の記憶は、両親(山本良郎と雪江)に連れられて新京(長春)から哈爾濱(ハルビン)へ汽車で行き、そこから松花江の流れに乗ってヂャムスに着くところからはじまっている。
おそらくこれらの地名、そして河の名前は主人公が成長するに従って記憶されるようになり、後年の知識で補強されたのであったろう。主人公の原体験としては、増水で河べりをはみ出し、見渡す限り泥の海になった流れに自分が漂っている光景なのではないか。その光景にリアリティを与えたのは、地図を調べて地名にピンで止めるように幼時体験を定着させた作業だったと思われる。著者は萩原朔太郎賞を受けた『烏有の人』という詩集のあとがきで、
と書いているが、この著者にとってはじめての小説をまとめる時、彼女もまた地誌的な正確さを求めたのだと思われる。
ということは、著者自身自分の体験を何かに定着させなければ危うく不確かな感じから脱け出られなかったのではないか。わけても満洲国という存在そのものは無理に観念で覆った虚構だったのだから。
そればかりではない。著者には彼女を取巻く父親と母親の関係、ヂャムスから開拓地へ長い出張をしている父親の留守中に母親の身の上に起ったこと、
「ヂャムスという土地は天府だよ」
と口癖のように言っていた父親の観念、その父親に珍らしく弟と一緒にボートに乗せてもらった記憶などが夢のまた夢のように浮んでくるのではなかったか。それは昔のことだからではない。
ソビエト軍が侵攻してくるという報せに避難の準備をしている彼女たちを見ながら、すっかり落着いている中国人のリュイ・ジャングイに向って、主人公が、
「避難しないの?」
と聞いた時、彼は、
「不(ブ)要(ヤオ)緊(ジン)」(大丈夫)
と答える。その瞬間、彼女は自分たち日本から来た者は彼ら現地人にとって一時的居留者に過ぎず、彼ははっきり日本人を差別している、と感じて涙があふれでてくるのだ。避難行のために呼び戻された離縁した妻を、
「雪江は妻ではない、女中として雇うので、子供の面倒をみるように言いつけてくれ」
と、父親がオバさんに指示する。その時主人公は「何なの? 大人の都合にうんざりする気持ちが芽生えていた」と著者は書く。
この作品で主人公が成長する過程は、大人たちが作っているものは、家庭も街も満洲国という国家さえも仮のものでしかないと認識してゆく道のりなのであった。
後半の『冥府』は、こうして佳木斯を脱出した主人公一家の運命を辿る。
ソ連兵の暴行から身を護るために主人公は髪を切って少年の恰好になる。収容所は不潔で、飢えで体力が落ちた日本人避難民のあいだには発疹チフスが発生し、父親はこの日本への敗走の旅のなかで病死する。
逃避行を続けながらも人々は生活しなければならない。少し成長した主人公と弟は中国人の乞食や物売りと交渉し、駆引を覚えて食料を手に入れる。そうして毎日、たくさんの人が死んでいく。いつの間にか主人公は死体を見ても驚かなくなる。生者と死者が共棲しているような環境のなかでも育ち盛りの主人公のなかに、
「死ねばヒトは汚いゴミで不快なだけだ。もういや! と声もなく叫んでいた。叫ばなければわたしは生きられない」
という感覚が育っている。そればかりではない。主人公は医学生でカリエスの娘を看ている千葉という青年医師に淡い恋心さえ抱くのだ。一方で敗戦の惨めさは日に日に深刻さを増してくる。高熱のために狂った父親は病床でロシア民謡をうたい始める。主人公は誇り高い開拓団の団長だった父親が、線路掃除夫を命ぜられ、ソビエト兵や中国公安に「掃き出せ、掃き出せ」と怒鳴られて働いていたことを知る。その父親が死んだ時、古くからの友人が「君は一代の風雲児であり愛国者であり人格者であった。まだ春秋のある身をここに失う」と送る言葉を述べてくれる。父親は四十三歳であった。
こうした、敗戦の光景を著者はいささかの思い入れもなしに綴る。赤ん坊が捨てられ、少し経ってその場に行ってみると何も残っていない。それを知って主人公は、
「赤ん坊を食べたのは野犬で、着物をもって行ったのは人間である」
と考える。その時、一切の情景描写は省略されている。それは著者の抑制にもよるが、より本質的には、素材が一切の形容を拒否しているからだろう。
僕はかつて詩集『烏有の人』を読んだあとで、
「この作品の背後には表現の技術や多彩なイマジネーションを超えた詩人としての恐さが潜んでいる。作者は、いわゆるヒューマンな感情などという、詩の外の価値を斥け、ひたすら実存を目指している」
という印象を持ったことを思い出した。また「人間という生き物への悪意が感じられる」という聞きようによっては評価の弁とは取ってくれないかもしれない感想を書いた。今回、この『天府 冥府』を読んでその時のことを再び胸中で反復していた。
読者の反響や誤解などを考えず、書かなければならないことだけを書いたこの小説は、その意味でコマーシャリズムに深く浸蝕されてしまった今日の文学の世界に投げて欲しかった石を投じた作品である。
【この書評が収録されている書籍】
彼女の最初の人生の記憶は、両親(山本良郎と雪江)に連れられて新京(長春)から哈爾濱(ハルビン)へ汽車で行き、そこから松花江の流れに乗ってヂャムスに着くところからはじまっている。
おそらくこれらの地名、そして河の名前は主人公が成長するに従って記憶されるようになり、後年の知識で補強されたのであったろう。主人公の原体験としては、増水で河べりをはみ出し、見渡す限り泥の海になった流れに自分が漂っている光景なのではないか。その光景にリアリティを与えたのは、地図を調べて地名にピンで止めるように幼時体験を定着させた作業だったと思われる。著者は萩原朔太郎賞を受けた『烏有の人』という詩集のあとがきで、
(安西)冬衛の詩の世界の虚構は、調べてみると地誌的にはきわめて正確である。ふしぎな臨場感はそこから来るのだろう。
と書いているが、この著者にとってはじめての小説をまとめる時、彼女もまた地誌的な正確さを求めたのだと思われる。
ということは、著者自身自分の体験を何かに定着させなければ危うく不確かな感じから脱け出られなかったのではないか。わけても満洲国という存在そのものは無理に観念で覆った虚構だったのだから。
そればかりではない。著者には彼女を取巻く父親と母親の関係、ヂャムスから開拓地へ長い出張をしている父親の留守中に母親の身の上に起ったこと、
「ヂャムスという土地は天府だよ」
と口癖のように言っていた父親の観念、その父親に珍らしく弟と一緒にボートに乗せてもらった記憶などが夢のまた夢のように浮んでくるのではなかったか。それは昔のことだからではない。
ソビエト軍が侵攻してくるという報せに避難の準備をしている彼女たちを見ながら、すっかり落着いている中国人のリュイ・ジャングイに向って、主人公が、
「避難しないの?」
と聞いた時、彼は、
「不(ブ)要(ヤオ)緊(ジン)」(大丈夫)
と答える。その瞬間、彼女は自分たち日本から来た者は彼ら現地人にとって一時的居留者に過ぎず、彼ははっきり日本人を差別している、と感じて涙があふれでてくるのだ。避難行のために呼び戻された離縁した妻を、
「雪江は妻ではない、女中として雇うので、子供の面倒をみるように言いつけてくれ」
と、父親がオバさんに指示する。その時主人公は「何なの? 大人の都合にうんざりする気持ちが芽生えていた」と著者は書く。
この作品で主人公が成長する過程は、大人たちが作っているものは、家庭も街も満洲国という国家さえも仮のものでしかないと認識してゆく道のりなのであった。
後半の『冥府』は、こうして佳木斯を脱出した主人公一家の運命を辿る。
ソ連兵の暴行から身を護るために主人公は髪を切って少年の恰好になる。収容所は不潔で、飢えで体力が落ちた日本人避難民のあいだには発疹チフスが発生し、父親はこの日本への敗走の旅のなかで病死する。
逃避行を続けながらも人々は生活しなければならない。少し成長した主人公と弟は中国人の乞食や物売りと交渉し、駆引を覚えて食料を手に入れる。そうして毎日、たくさんの人が死んでいく。いつの間にか主人公は死体を見ても驚かなくなる。生者と死者が共棲しているような環境のなかでも育ち盛りの主人公のなかに、
「死ねばヒトは汚いゴミで不快なだけだ。もういや! と声もなく叫んでいた。叫ばなければわたしは生きられない」
という感覚が育っている。そればかりではない。主人公は医学生でカリエスの娘を看ている千葉という青年医師に淡い恋心さえ抱くのだ。一方で敗戦の惨めさは日に日に深刻さを増してくる。高熱のために狂った父親は病床でロシア民謡をうたい始める。主人公は誇り高い開拓団の団長だった父親が、線路掃除夫を命ぜられ、ソビエト兵や中国公安に「掃き出せ、掃き出せ」と怒鳴られて働いていたことを知る。その父親が死んだ時、古くからの友人が「君は一代の風雲児であり愛国者であり人格者であった。まだ春秋のある身をここに失う」と送る言葉を述べてくれる。父親は四十三歳であった。
こうした、敗戦の光景を著者はいささかの思い入れもなしに綴る。赤ん坊が捨てられ、少し経ってその場に行ってみると何も残っていない。それを知って主人公は、
「赤ん坊を食べたのは野犬で、着物をもって行ったのは人間である」
と考える。その時、一切の情景描写は省略されている。それは著者の抑制にもよるが、より本質的には、素材が一切の形容を拒否しているからだろう。
僕はかつて詩集『烏有の人』を読んだあとで、
「この作品の背後には表現の技術や多彩なイマジネーションを超えた詩人としての恐さが潜んでいる。作者は、いわゆるヒューマンな感情などという、詩の外の価値を斥け、ひたすら実存を目指している」
という印象を持ったことを思い出した。また「人間という生き物への悪意が感じられる」という聞きようによっては評価の弁とは取ってくれないかもしれない感想を書いた。今回、この『天府 冥府』を読んでその時のことを再び胸中で反復していた。
読者の反響や誤解などを考えず、書かなければならないことだけを書いたこの小説は、その意味でコマーシャリズムに深く浸蝕されてしまった今日の文学の世界に投げて欲しかった石を投じた作品である。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする