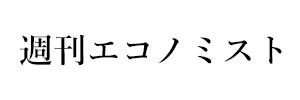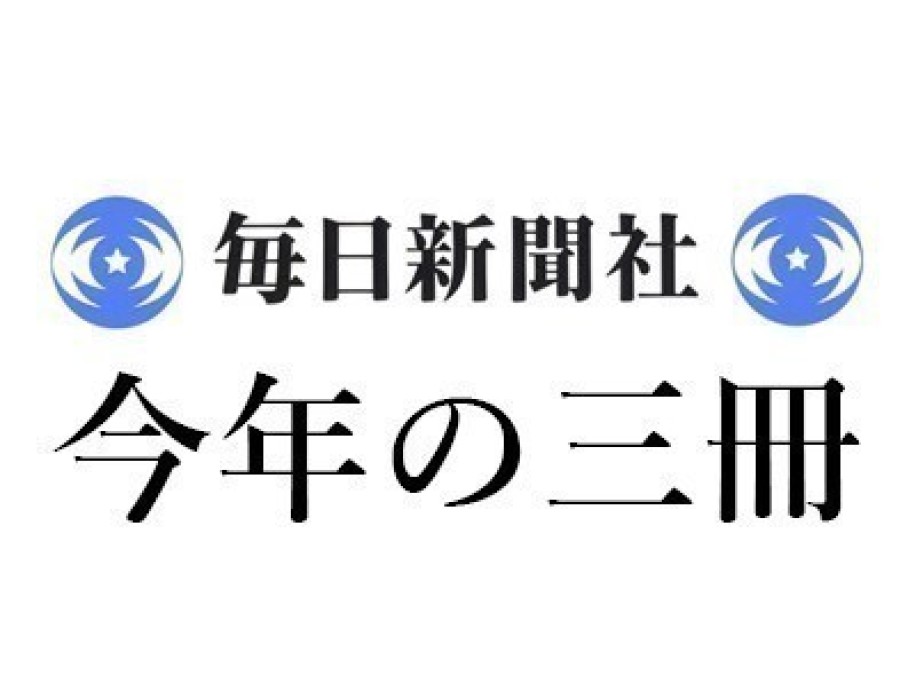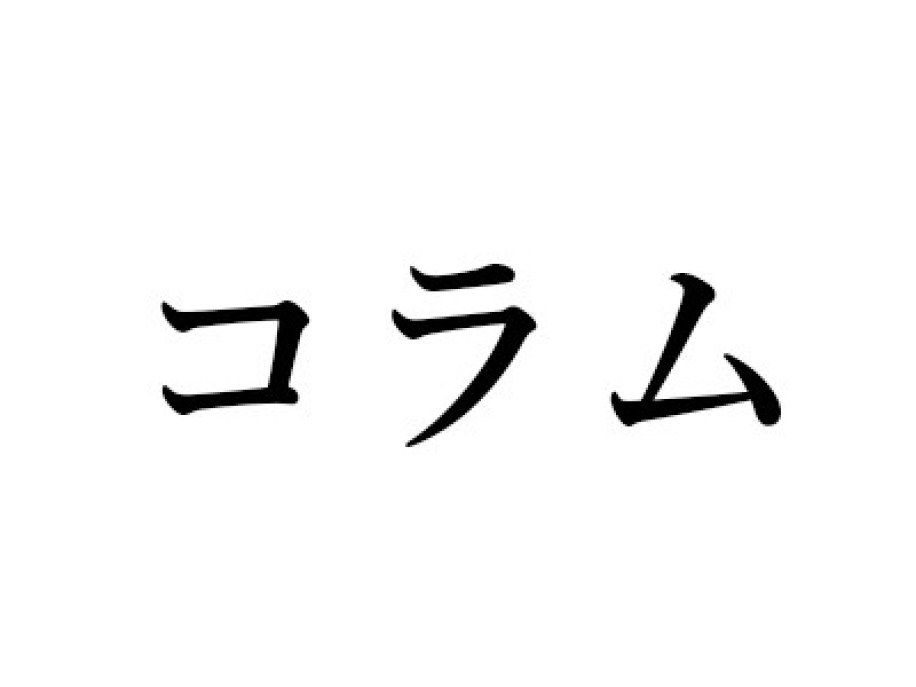書評
『ねこのほそみち ―春夏秋冬にゃー』(さくら舎)
「猫」句集に学ぶ自由気ままな鑑賞法
葛籠(つづら)の底から、むかし使っていたハーモニカが出てきた。それでついうかうかと吹奏して途端に噎(む)せた。内部にカビが発生していてこれをまともに吸い込んでしまったからである。周囲に人はおらなかった。なので、「うわー、カビ吸い込んでもおたやんけー」「あほやー」みたいなことを言うことによって惨事を笑いのうちに解消することができなかった。それで思ったのは。
もしかしたら人が短文投稿サイトに投稿したくなるのはこんなときなのかな、ということで、かかるとき人は、「押し入れから出てきたむかし使ってたハーモニカ吹いたらおもっきりカビ吸い込んだ、ゲホゲホ」といった文章を写真とともに投稿、そのことによって気持ちや思いを公的でも私的でもない、自分の物でも他人の物でもない領域にほうり投げ、誰かと一緒に眺めて共有して、有限の命を悲しみ愛おしむのかな。もしかしたら。と思ったのである。
と考えてじゃあインターネットがなかった頃はどうしていたのだろう、例えば私が子供の頃やなんかは、と考えて思い当たったのは俳句で、そういえばいまは殊更(ことさら)、イベント的に発表される、誰が選んでいるのかもよくわからない、「世相を表す言葉」なんてのも、俳句で自然に浸透していったように思う。降る雪や明治は遠くなりにけり、とか。
或(ある)いはこの曖昧な人格のバッファゾーンみたいなところにほうり投げるというのは政治家にとっては割と都合のよかったことで、いまはなにかというと、「認めて謝罪しろ」とか、「辞職しろ」と言われるが前方(まえかた)は俳句を詠めばみんなそれでなんとなく納得してそれ以上追及しなかった。俳句を詠んで、「明鏡止水の心境でございます」と言えば最強だったが、俳句なしの明鏡止水だけでは駄目で、俳句は必須だった。
というのはまあ我々一般庶民には関係のない話だが、そういうことからもわかるように、いろんな意味で個人の魂を救済するカは短文よりも俳句の方がはるかに強大で、私もハーモニカのカビを吸い込んで傷ついた魂を救うために俳句を作りたいと思い、何時間か考えて、阿呆(あほ)だよねハモニカの黴吸いにけり、とひねってみた。一応、けりとか言って俳句ぶってはいるが、もちろん駄句中の駄句である。
俳句鑑賞に正解なし
なんでそんなことになるかというとちゃんと俳句を鑑賞したことがないからで、そらそうだ、小説を読んだことがない人に小説は書けぬし、都々逸(どどいつ)を聞いたことがない人は都々逸が歌えない。なので俳句を作ろうと思ったら俳句を読まなければならない。という訳で手に取ったのが、『ねこのほそみち』(堀本裕樹・ねこまき著、さくら舎、1400円)で、どんな本かというと江戸時代から現代にいたるまでの猫が出てくる句から88句を俳人の堀本裕樹が選び、これに解説とも言えるし、随筆とも言えるし、或いは掌編小説とも言うべき文章を付したものに、さらにイラストレーターである、ねこまきが数コマのコミックを付したという本で、どうだったかというと、自分のような初心者にこれからなろうとする可能性をまだ捨てきれないなと思おうかなと思い始めることから始めてみようかな、と思っているものにとっては、ただ句だけが、ずらっ、と並んでいる句集に比べると激烈に読みやすく、また楽しく読むことができてよかった。なぜというに、まず猫という身近で親しみやすい題材が並んでいて、その分野特有の美意識を共有していなくても、その句の気持ちに容易に近づくことができるという点がよかったのと、それから、文章とコミックはまったく別個に書かれたらしく、ひとつの句に対して複数の解釈がなされていて、これを読むとき、句には国語の試験のような正解を追求するのではなく、そこに自分の精神や境涯を好きに滲(にじ)ませて自由な気持ちになることができた点が楽しかったからである。
よしこれでいくらカビを吸い込んでも大丈夫だ。これからはむしろ積極的にカビを吸って生きていこう。そして早死にしよう。そんな馬鹿なことすら俳味として乗り切る。そんな間違った学びを今日もしてよかったことなりと知る秋深し。
ALL REVIEWSをフォローする