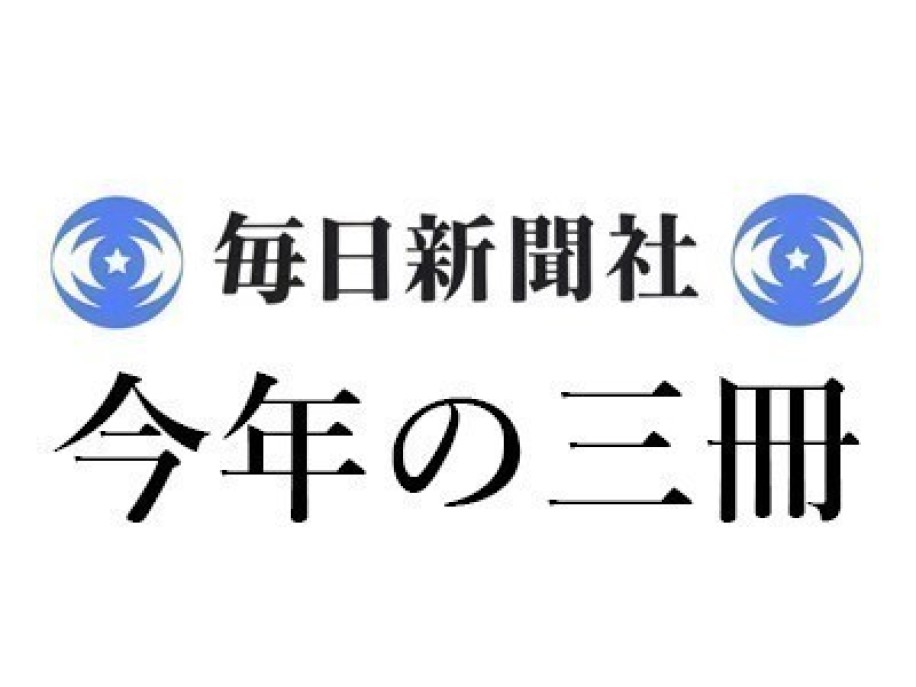書評
『さようなら、オレンジ』(筑摩書房)
書くことへの強い必然性
いま読んでいるこの小説はどんな人によって書かれたのか。全く気にならないという読者は少ないだろう。巻末の著者紹介に目を通すし、あとがきがあればまっ先に読んでしまう。ありがちだ。作者名でインターネット検索することだってある。多少後ろめたくはあるが、悪いことじゃない。しかし、作家の性別や国籍、年齢、容姿(!)など各種属性は作品評価に本来関係ないーはずだ。それでも、私たちは頭の片隅にメモする。作者にまつわる情報の束を。
本書の著者欄には「大阪生まれ」「単身渡豪」「業務翻訳業経験」「在豪二十年」とある。読者はなるほどと納得するだろう。まさに、"異言語"や"異国での生活"をめぐる小説だからである。
物語は主人公サリマの日常を中心に展開する。難民の黒人女性だ。アフリ力の内戦状態にある国からオーストラリア(らしき国)の田舎町へと逃れてきた。地域のコミュニティーにうまく溶け込めずにいる。言語の壁は大きい。早々に夫は失綜。生鮮食品加工の仕事で2人の息子を養っている。
学校にも通う。英語を習得するためだ。教室にはさまざまな背景と条件を抱えた生徒が共在する。職場と学校と家庭という三つの空間。それに言語と職能という二つの変数。そのレベルアップはサリマの内面と各所での人間関係に微妙な変化をもたらす。関係性の再編が彼女を前に進める。
人物描写が本作の最大の読みどころだ。どの登場人物にも少しずつ作者自身の体験や見聞が流し込まれていよう。それゆえ、読者は説得力を感じつつも、こんな違和感を抱くかもしれない。なぜ日本人がアフリ力人の話を書かねばならないのか、と。それも日本語で。ときに読者は書く資格や必然性を性急に求める。
そうした態度に応答するように、本作には構成上のトリックがーつ施されている。素朴な文体に比してその方法は大胆だ。危うくもある。成否は個々の目で判断してほしい。
初出メディア
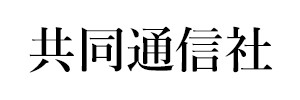
共同通信社 2013年9月26日
ALL REVIEWSをフォローする