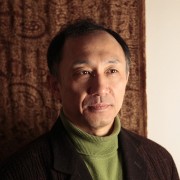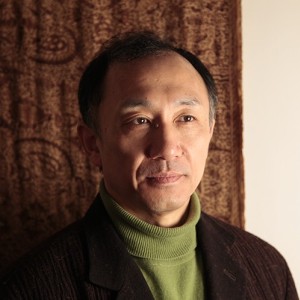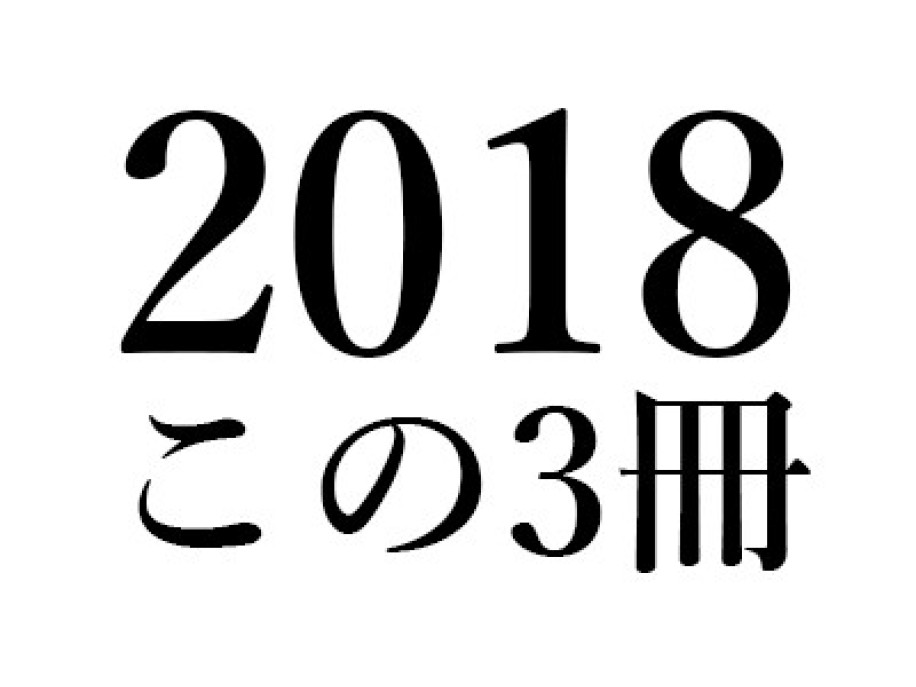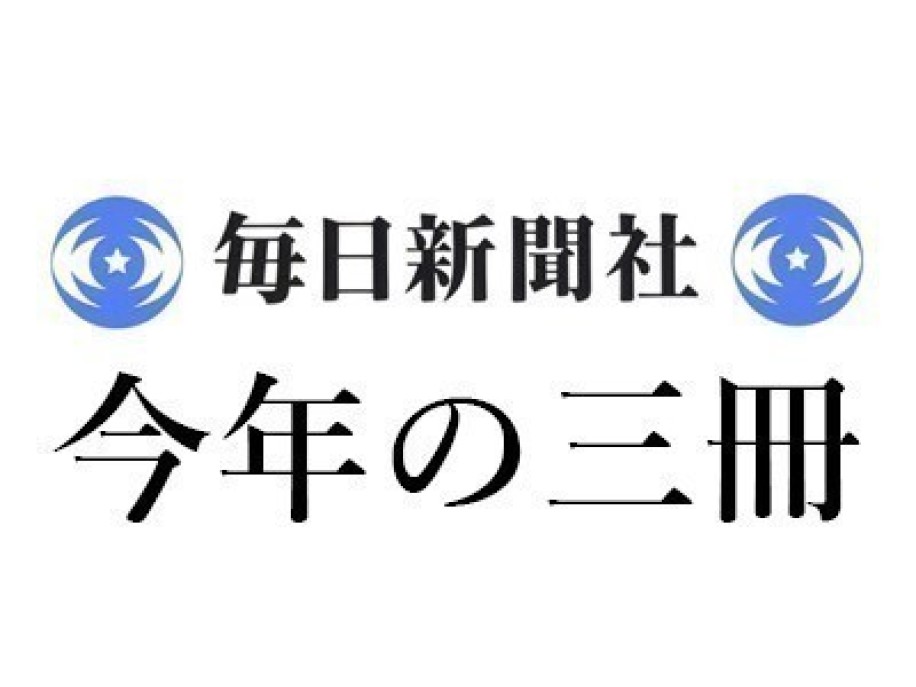書評
『神戸 闇市からの復興:占領下にせめぎあう都市空間』(慶應義塾大学出版会)
精密かつ大量の調査から描く
「闇市」といえば、スクラップ・アンド・ビルドで再開発されたビル群の隙間(すきま)を縫うようにして点在する路地を思い起こす。東京では藤木TDCの『東京戦後地図 ヤミ市跡を歩く』(実業之日本社)が活写したような、たとえば新宿駅沿いの「思い出横丁」(俗称・ションベン横丁)や吉祥寺駅北口前の「ハモニカ横丁」である。それらはいまなお店舗が営業中で、外国人観光客をも集めて活況を呈しているが、一方で渋谷の宇田川町のように名残りすら残さないものもある。対照的なのが神戸である。本書が注目する「闇市」は、そのものはたった一年間で失われた。それでいて、お洒落(しゃれ)な都市空間に亀裂のような痕跡を残したというのだ。それが終戦直後に現JR三ノ宮・元町間の一・二キロメートルにわたる鉄道高架下や南側舗道・緑地帯に出現し、「日本一」の盛況を誇った「三宮自由市場」である。著者はその成り立ちや消滅、その後のゆくえを精密に描いている。
本書は学術書であり、進駐軍(米第八軍の第一軍団と第九軍団)およびその指令を受けた兵庫県・警察といった行政が、生活者として角突き合わせていた日本人および諸外国人が換地を経て、いかに秩序を形成していったのかを、膨大な進駐軍関係の資料、神戸新聞記事、インタビュー、写真や図版をもとにその過程の全体を分析することをテーマとしている。けれどもそれ以上に面白いのが、闇市をなくすために換地を認められて移転し、長期間存続しながらものちに消滅した、神戸っ子ならば記憶に留めているだろう謎めいた地域の説明だ。
たとえば私は一九七〇年代の後半のある夜、現JR三宮駅にほど近いあたりを歩いていて、闇の中からぬっと現れた女性に「にいちゃん、ええ子おるでえ、遊んでいかへんか」と声をかけられ魂消(たまげ)たことがある。周辺は神戸の表玄関ともいえる地域で、そんな所の一角にバラックが建つ様は幻影のようだった。
私が目撃したバラックは「三宮国際マーケット」のうち雲井通六丁目だったらしい。朝鮮人系組織が二年間だけゴム製品の卸問屋として営業を許されながら、帰国事業等で空洞化し、そこに日本人が流入して麻薬や売春に手を染めた。それはようやく一九九○年に再開発され「サンシティ」として生まれ変わったという。また「三宮ジャンジャン市場」は目抜き通りであるセンター街のすぐ北にありながら港湾労働者や手配師、浮浪者で賑(にぎ)わう飲食店地域で、モナ・リザなる美人従業員に釣られた芸術家や、評論家の大宅壮一までもが出入りしたが、放火による火災後の市街地改造事業で、一九六五年に撤去されさんプラザが建設された。
著者は台湾系の「三宮高架商店街」も含めそれらの換地が、民族対立から死亡事件まで起こした「闇市」をたんに潰すだけでなく、そこに集まった人びとがそれぞれに自治組織を設けて棲(す)み分け、飲食店ならば衛生基準を満たすよう当局が誘導して成立したと指摘する。
神戸復興にかかわる最大の謎は、戦前に浅草と肩を並べる盛り場であった湊川新開地が、何故に戦後三宮・元町に客を取られ急激に衰退したかだろう。本書からすれば、復興街路計画が湊川新開地にも存在した闇市を誘導しつつ資本の誘致と両立させることに失敗したせいとなろうか。行政の思惑だけでは復興は成功しないのであり、災害に遭った都市の問題にも通じて、貴重な研究だ。
現在では忘れられた進駐軍の滞在地を特定したこと、戦後の神戸が闇市を掌握した朝鮮人に脅かされたという認識は間違いと指摘したことも特筆したい。
ALL REVIEWSをフォローする