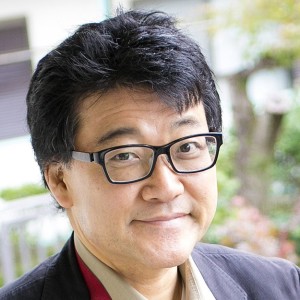書評
『ユニコーンを探して―サタジット・レイ小説集』(筑摩書房)
サタジット・レイ(Satyajit Ray 1921-1992)
インドの映画監督・作家・イラストレーター。広告会社でデザイナーとして働くかたわら、映画製作に打ちこみ、1955年に「大地のうた」を完成。翌年、カンヌ映画祭でベスト・ヒューマン・ドキュメント賞を受賞した。1992年にはアカデミー賞名誉賞に輝いている。小説を手がけるようになったのは1961年で、子どもむけ雑誌に読み物を書いたのきっかけだという。『ユニコーンを探して』は日本独自編集の短篇集で、ベンガル語からの翻訳。introduction
「世界文学」を読む! なんて威勢いいことを言っているぼくだが、そのじつヨーロッパや南北アメリカの小説が中心だ。アジア、中東、アフリカあたりはあまり視野に入ってこない。翻訳紹介の事情もあるけど、ぼく自身の問題もある。知らない小説を積極的に読んでやろうというチャレンジ精神が衰えている気がする。良くないことだ。そんなことだから、友人が教えてくれるまで残雪(ツァンシェエ)という途轍もない作家を知らなかったりする。慚愧と反省。サタジット・レイはインドの作家だ。ぼくは本屋でたまたま『ユニコーンの探して』という題名を目にして、この本を手に取った。ファンタジイだと思ったのだ。まあ、ファンタジイといえばそうなのだが、ちかごろ氾濫しているぞんざいな魔法ものとは、ひと味もふた味も違います。▼ ▼ ▼
古本屋には、じつにさまざまなものが集まってくる。書籍や雑誌といった出版物だけではなく、版画やポスター、絵ハガキやメンコ、切符、チラシ……。さらには直筆の手紙や日記までが流れつく。どこのだれとも知れぬ人の書いた日記など、なんの価値があるかと思うのだが、好んで集める人もいるようだ。年代や内容しだいでは、世相・風俗を知る資料となるという。なんにせよ、あまり高尚な趣味とは言いがたい。
他人の日記を商売のネタにするのは、日本の古本屋だけかと思っていたら、そうでもないらしい。サタジット・レイの作品で、古本屋で百三十年前の日記を格安で掘りだすという話がある。「幽霊」という短篇だ。
主人公は古書愛好家。銀行勤めだが、給料の半分以上を古書収集につぎこむというほどの筋金入り。しかし、ブックハンティングの武勇伝は、この小説の本筋ではない。店主が二十ルピーと言うところを、十二ルピーまでまけさせて買ったその日記は、ページのすべてが羽根ペンで綴られており、ジョン・ミドルトン・ブラウンの署名と、バンガロールの住所が書かれていた。
主人公は、当時インドに住んでいたイギリス人の生活に対する好奇心でページを開くのだが、読みすすむうち、サイモンという名前に惹きつけられていく。日記のなかにはブラウン氏とサイモンの間柄を知る手がかりは見あたらないが、氏のサイモンに対する並ならぬ愛情は伝わってくる。サイモンの知恵や勇気、いたずら、気まぐれ……彼のようすについての記述が随所にあるのだ。しかしサイモンに突然の死が訪れ、以降の日記は落胆と苦悩ばかりが綴られる。
サイモンの死から約一カ月後、不思議な事件がおこる。日が暮れて帰宅したブラウン氏は、居間でサイモンと出会う。お気に入りだった背もたれ椅子に座り、ブラウン氏に静かな視線をむけた姿は、かつてと少しも変りない。だが、部屋の明りをつけた瞬間、サイモンはふっと消えてしまう。それから毎日、ブラウン氏はサイモンの幽霊との逢瀬をつづける。日記の最後には、サイモンの愛――その生涯・死後を通じて、自分に注いでくれた――への感謝が記されていた。
いにしえの愛に感銘を受けた主人公は、バンガロールを訪れたおり、ブラウン氏が住んでいたロッジを探してみる。もしかすると、今もなお日暮れになると、サイモンの幽霊が現われるのではないか。はたせるかな、ロッジは当時のまま建っており、しかも居間には例の背もたれ椅子まで残っている。空家であるのをさいわい、主人公は友人とともに居間にあがりこみ、日暮れを待ちうける……。
結末は言うまでもないだろう。サイモンの幽霊はあらわれ、その意外な正体が明らかになる。もっともビアスやサキあたりを読みつけた読者なら、ブラウン氏とサイモンの関係は不明だというあたりで、どんなオチがつくのか予想できてしまうに違いない。トリッキーな物語としてみるなら、この作品はナイーブすぎるし、怪談としてもだいぶおとなしい。ただし、不思議な世界へ読者をすうっと引きこんでいく手さばきは、じつにみごとだ。主人公が、百三十年前の日記に惹きつけられていくのと同時に、読者もレイの語りに包みこまれてしまう。
短篇集『ユニコーンを探して』には、そんなレイの素直かつ巧みな語りの作品ばかり、いま紹介した「幽霊」も含めて十篇が集められている。そのなかで、幻想的な色彩のある作品は半分くらいだが、そうした区別はあまり意味はない。日常的な題材を扱っても、この作家は不思議な空間をやすやすと作りだしてしまう。
たとえば「見知らぬ人」という作品は、一度も会ったことのない叔父の突然の訪問に、あたふたする家族のようすが描かれる。叔父さんからの手紙をはさんで、夫婦が話をする。「うちの住所はどうしてわかったんだろう」「シトルおじさんから聞いたのかも」「シトルおじさんだって」「まあ、あなたってなにも覚えてないのね。私たちの結婚式で、お菓子を六十六個食べる賭けをして、本当に食べてしまったから、笑いが止まらなかったじゃない」「ああ、あのときの」……こんな会話をたどっていくうちに、読者はこの家族とおなじ空気を吸っている気分になってしまう。
偽者かもしれないという不安を抱きながら、家族は叔父さんを迎えるのだが、この叔父さんというのがまたつかみどころのない人物だ。いきなり「私が本当の叔父かどうか証明するものはなにもないわけだから、ひとりの年寄りに数日宿を貸してやると考えてくれないかな」などと言い、世界各地のコインを子どもへのお土産としてさしだす。逗留しているあいだはなにをするわけでもなく、ただ子どもたちにはとびきり面白い話を聞かせてくれた。そして十日間泊まるはずだったのが、五日目に突然「ひとつの場所に長くいるのは性にあわないから」といって去ってしまう。夫婦は狐につままれたような気持ちだが、なにも盗んだようすもないし、たとえ偽者だとしても害はなかったと思って、その年寄りを見送る。
それから数日して、シトルおじさんがやってくる。家族は彼の口から、泊まっていった叔父のことを聞くのだが、そのときまで叔父の名前を尋ねさえしなかったことに気づかない。彼は、家族にある贈りものを残していったのだが……。
レイは、日記、手紙、列車の旅、街の変わり者が語る与太話などを、物語の“きっかけ”に用いる。ただし、それは創作上の技巧というより、作者自身の肉声ともいうべきものだ。その心地よさに誘われて、読者は作品世界へと入りこんでいく。アイデアは真似できても、この語り口はなかなか真似できるものではない。
ぼくは他人の日記などさらさら興味はないが、サタジット・レイのそれならば読んでみたい。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする