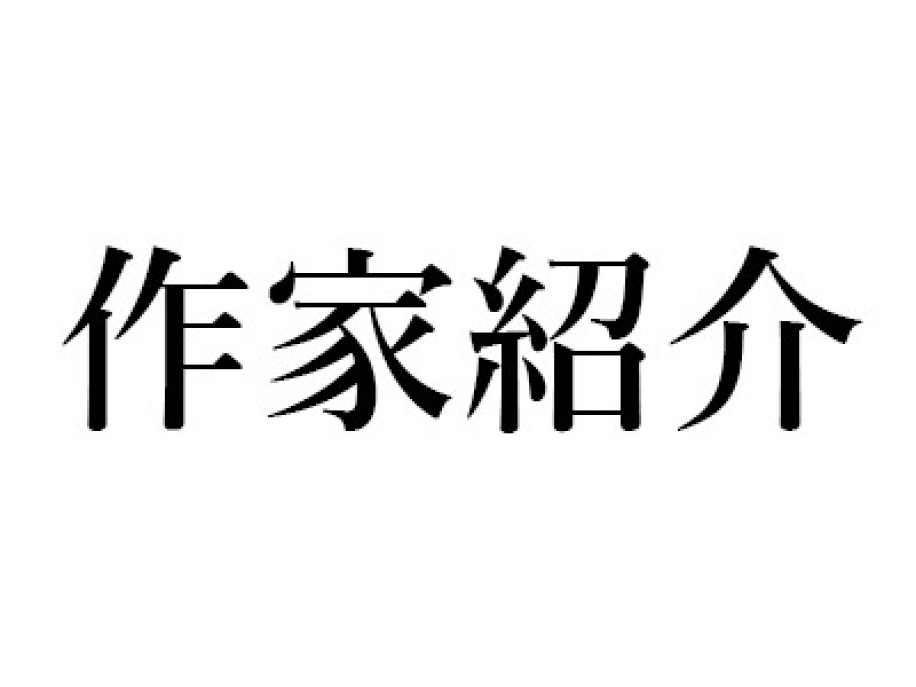書評
『高坂正堯外交評論集―日本の進路と歴史の教訓』(中央公論社)
古びない歴史へのまなざし
緑陰の読書の伴侶として、今夏はまことに得難い一冊に恵まれた(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1996年)。先頃急逝された高坂氏自選のこの二十五年の外交評論十九編をまとめた本書が、それである。本書を手にしながら、しかし一挙に読み進むというわけにはなかなかゆかず、少し読んではしばし物思いに耽ることを余儀なくされた。それはなぜか。著者の評論が難解だからでも、今ではもう古くなったからでもない。むしろその逆だ。きわめて説得的でわかりやすい文体であるがゆえに、発表当時は見すごしていた著者の歴史への奥深いまなざしや、評論としては意外なまでの射程距離の長さに、改めて気づかされるからである。
そしてこのことは、政治評論の運命について示唆を与えずにおかない。がんらい政治評論はその時論的性格ゆえに、多くの場合その場限りで後は顧みられないものだ。しかし一流の政治評論は、個々の事象についての予測があたったか否かにかかわらず、後から読み返してみた時、あたかも古典を繙(ひもと)くと同じように歴史の豊かな奥行きを見せてくれる。
著者もまたひそかにそのことを自覚していたに違いない。だからこそ、各論文に付された現時点でのコメントが生き生きとしてくるのだ。ニクソン・ショック、オイル・ショックを予見できなかったと正直に告白する著者は、同時に「ただ、誤った予測のために基本的問題を考えることができた面もある。そのとき考えた問題は今日も未解決である」との逆説的真実を語っている。その意味で一九七〇年代を前に書かれた本書冒頭の二つの論文は、その後の日米関係のズレを見事に考察している。
こうした考察を通じて著者の中に熟成されたのは「文明」という観念であった。「文明」に根ざす議論を明示し始めた一九八〇年代半ば以降の著者の評論は、好悪の感情を持ち出しながらも、「歴史の教訓」を求めてより・しなやかになった。「第二次世界大戦後、帝国主義が悪とされるに至ったことをわれわれは承認すべきだが、それと同時に、それ以前には帝国主義を悪とする原則が確立していなかったことにも留意しなくてはならない」と説く著者の複眼的思考に、なお学ぶ点は多いと思われる。
ALL REVIEWSをフォローする