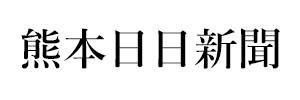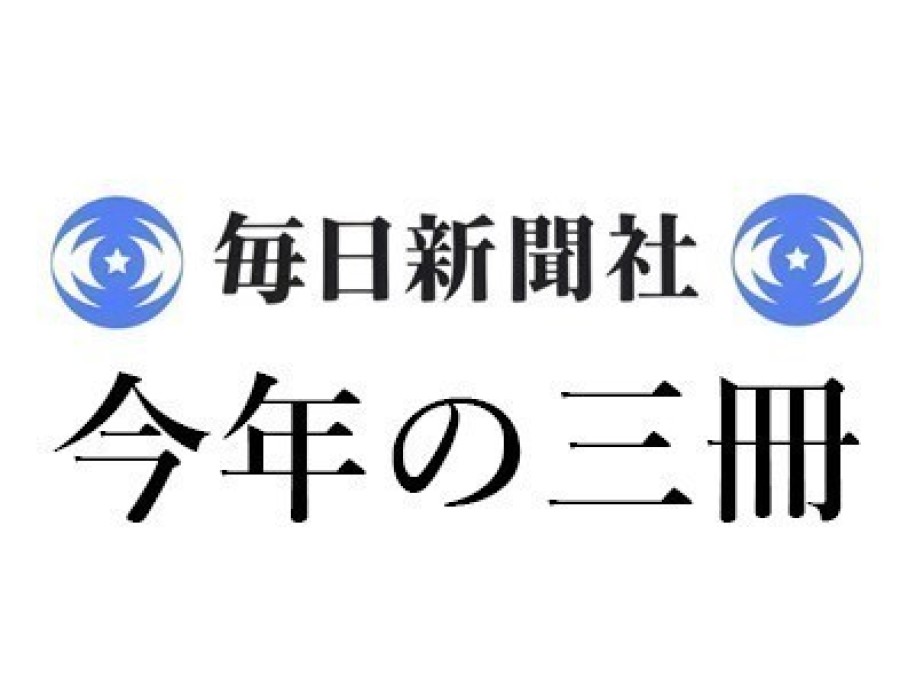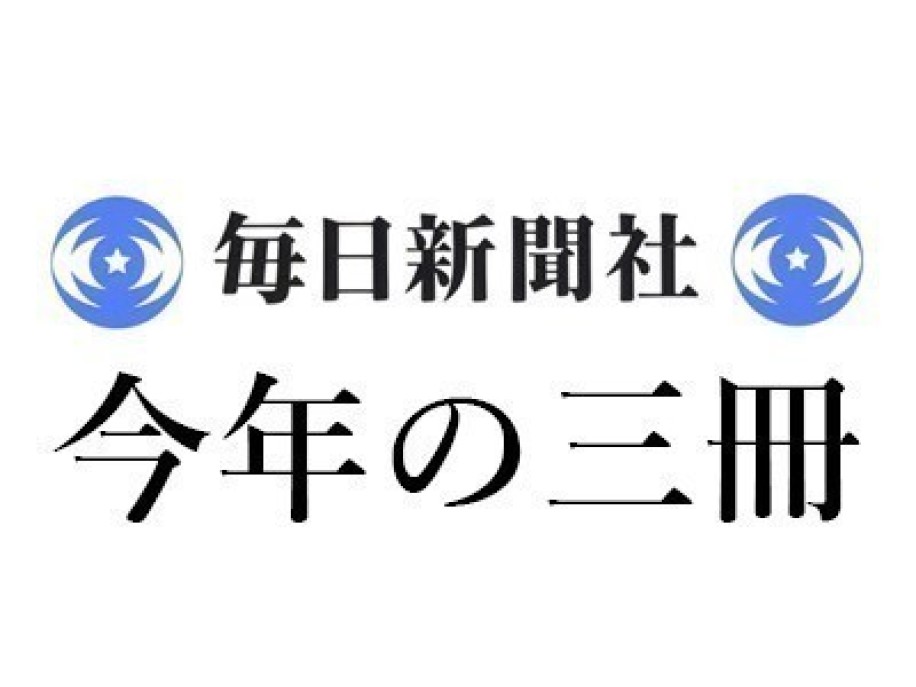書評
『家老の忠義: 大名細川家存続の秘訣』(吉川弘文館)
「御家」に尽くした松井父子
実力主義に基づく競争と抗争の戦国時代。上洛以来14年間を戦争に明け暮れた織田信長は、ついに宿老明智光秀に暗殺され、その光秀は同僚の秀吉に敗死する。だが秀吉は信長の権力を継承する地位を勝ち取るために光秀を討ったのであり、「織田家」のために敵を取ったわけではなかったのだと著者はいう。また、肥後加藤家の家老たちは自らの利益を追求して抗争し、おかげで同家の統治能力は地に落ちて、取潰(とりつぶ)しにつながったという。かくも流動的で不安定な社会状況は、一体いかにして克服され、江戸時代の長期平和と安定が実現されたのだろうか。その秘密を、本書は肥後細川家の筆頭家老、松井康之・興長父子の活躍を通じて解き明かす。
細川藤孝・忠興に仕えた康之は武功抜群の勇将で、秀吉からは大名として取り立てるとの打診さえ受けるが、これを断り、その才を細川家存続に捧(ささ)げた。そして興長は、4人の藩主に50年間にもわたって仕え、幾度もの難局を乗り切って、幕末まで続く細川家の基礎を確立した。
2人が追求したのは自分の栄達ではなく、千人もの武士によって構成される「御家」の組織の存続であった。しかし、それは主君への盲従(もうじゅう)を意味するわけではない。明君の誉れ高い細川忠利に対しても、その言動が御家の利益に反し、統治者として不適切だと判断されれば、興長は決然と諫言(かんげん)した。80歳で死去する直前の遺書でさえ、主君綱利への諫言であった。家老衆の合議を機能させ、八代城主としての自身の権力を抑止する制度まで策定していた興長。著者の描く興長像は、じつは組織人にこそ人格の自立と強靱(きょうじん)な主体性が求められることを教えてくれる。
長期内戦から平和への日本史上最大の転換期に生きた人々が、個人(競争)と組織(共生)との狭間で悩む私たちに発する多くのメッセージ。著者はそれを厖大(ぼうだい)な歴史資料から紡ぎ出していく。博物館学芸員として鍛えられた文体は平易にして明晰だ。専門性と一般性のバランス絶妙な快著である。
[書き手] 稲葉 継陽(いなば つぐはる・熊本大学永青文庫研究センター長)
ALL REVIEWSをフォローする