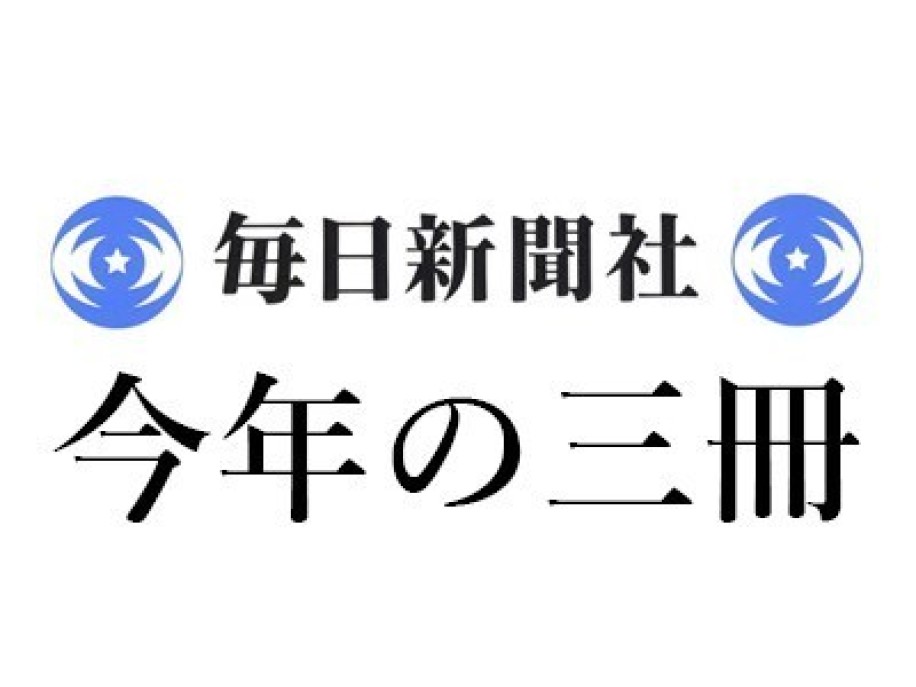後書き
『レーモン・クノー 〈与太郎〉的叡智』(白水社)
馬鹿げた話やデタラメな話を意味する「与太話」ということばは、古典落語にしばしば登場する「与太郎」から来ています。与太郎といえば、「世の中ついでに生きている」ような、のん気なお調子者、といったところでしょうか。深刻ぶったり難解ぶったりするのが大好きなフランス現代小説において、この与太郎キャラを描くのを得意とする異色の作家がいました。それが、レーモン・クノーです。本書著者の塩塚秀一郎さんに、クノーとの出会いから登場人物の魅力までを解説していただきます。
ピエロやヴァランタンも生産的な仕事はできないかわりに、たいした欲も持たず幸せそうにしている。まずはこういうキャラクターが好きになった。ところが、こういう一見ぼんやりした登場人物を生み出したクノーという人物は、膨大な知識を蓄え博識で知られる作家だったという。クノーのなかで、学問とか知識といったものに、いったいどういう意味づけがされているんだろう? そういう疑問を抱いていた頃、たまたま読んだ三輪秀彦さんのエッセーに、こんな一節を見つけた。「レーモン・クノーは、もしこういう表現が許されるなら、《正体が摑まえにくい》作家の一人だといえるだろう。いわゆる《難解な》作家とも少し違う。彼の詩や小説は、その俗語的使用法や言葉の遊技的側面を含めても、決して難解とはいえない。それでいて、彼の作品全体が、あるいは文学に対する彼の構えそのものが、いささかわれわれの文学的通念からはずれているのである」〔『集英社世界文学全集』第二三巻〕。この言い方を借りるなら「知に対する、通念からはずれたクノーの構え」が気になり始め、結局、大きな論文をひとつ書くまでになってしまった。
クノーは、『プレイヤード百科事典』企画時のパンフレットに、「噓と誤りについての巻」も用意するつもりだと書いている。結局この目論見は実現しなかったのだが、「真実」の集成であるはずの百科事典に「噓」や「誤り」まで含めようと考えるあたりに、知に対するクノーの独特な考え方がみてとれるだろう。クノーには、まことしやかな物言いや有無を言わさず押しつけられる真実への警戒感があるようなのだ。百科事典というものは、放っておけばみずから権威となり絶対的な規範になる危険をはらんでいるが、「噓と誤りの巻」にはそのような百科事典の病を中和する意図が込められていたとも考えられる。
本書では言及する余裕がなかったけれど、クノーは詩人としても知られており、結構な数の詩集が刊行されている。『運命の瞬間』所収の一編で、冒頭から詩人は「詩なんてまったくたいしたものじゃない」と言い放ち、続く行では「せいぜいアンティル諸島のサイクロンか/中国海のタイフーンといったところ」と巨大災害と比較することで、逆説的に「詩」の大きさを歌いあげている。「たかが文学、されど文学」といった言い方はいかなる分野についても意味をもつものだろうが、この両面のうち、「たかが」と言える羞じらいをもったフランス作家は思いのほか少なく、尊大で大仰な物言いばかりが目につくなかで、クノーのこうした姿勢は貴重である。
知に対する、あるいは文学に対する、クノーの特異なスタンスの象徴としても、ピエロやヴァランタンといった登場人物は気になる対象だったにもかかわらず、これまで彼らにまとまった文章を捧げる機会を持てずにいた。年を重ねるにつれ関心の在りかが拡散したこともあって、今さら取り上げるチャンスはないだろうと思っていたのだが、いっとき夢中で読んだ作家の、もっとも愛着のある作品群を捨て置くのも忍びなく、住居が変わったのをきっかけとして初心に戻って書き始めたのだった。
執筆中こそピエロを満たしたような幸福感に浸っていられたものの、校正中には「起きるはずがない」と考えられていた戦争の勃発によって冷や水を浴びせられることとなった。もとより世界情勢の帰趨を見定める千里眼など持たない私が「勝ったり負けたりしながら戦争は繰り返される」などと訳知り顔でいられるはずがない。
[書き手]塩塚秀一郎(東京大学教授・仏文学者)
異色の知性派作家が描く、「世の中ついでに生きている」魅力的なお調子者たち
レーモン・クノーとの出会いは、フランス語を習い始めて二、三年経った頃、ふと手にした『文体練習』原書のペーパーバックだった。辞書を細かく引いてというふうではなく、分かるところだけ読んだのだと思うが、大笑いさせられ、奇妙な作者のことが気になり始めた。その後どんな順番でクノーの作品を読んでいったのかはっきりしないが、とりわけ『わが友ピエロ』と『人生の日曜日』が好きになり、主人公のピエロやヴァランタンはまるで落語の与太郎みたいだと思った。与太郎はぶらぶらしているばかりで、生産的なことはおよそ何をやらせてもだめ。まわりからは愚か者だと思われているが、そうではないんだと喝破したのが立川談志である。いわく、「ありとあらゆる欲望を充たしてやるのが文明だと思い、信じ、正義とか正当とか称して、それに向って突き進んでいる人間社会に、与太郎は見事なまでに警告を与えている」〔『新釈落語噺』〕。人間は働くものだ、働かざるもの食うべからず、という世間の常識に潜む誤りや噓を与太郎は見抜いているのだ、だから与太郎が馬鹿なはずはない、と。ピエロやヴァランタンも生産的な仕事はできないかわりに、たいした欲も持たず幸せそうにしている。まずはこういうキャラクターが好きになった。ところが、こういう一見ぼんやりした登場人物を生み出したクノーという人物は、膨大な知識を蓄え博識で知られる作家だったという。クノーのなかで、学問とか知識といったものに、いったいどういう意味づけがされているんだろう? そういう疑問を抱いていた頃、たまたま読んだ三輪秀彦さんのエッセーに、こんな一節を見つけた。「レーモン・クノーは、もしこういう表現が許されるなら、《正体が摑まえにくい》作家の一人だといえるだろう。いわゆる《難解な》作家とも少し違う。彼の詩や小説は、その俗語的使用法や言葉の遊技的側面を含めても、決して難解とはいえない。それでいて、彼の作品全体が、あるいは文学に対する彼の構えそのものが、いささかわれわれの文学的通念からはずれているのである」〔『集英社世界文学全集』第二三巻〕。この言い方を借りるなら「知に対する、通念からはずれたクノーの構え」が気になり始め、結局、大きな論文をひとつ書くまでになってしまった。
クノーは、『プレイヤード百科事典』企画時のパンフレットに、「噓と誤りについての巻」も用意するつもりだと書いている。結局この目論見は実現しなかったのだが、「真実」の集成であるはずの百科事典に「噓」や「誤り」まで含めようと考えるあたりに、知に対するクノーの独特な考え方がみてとれるだろう。クノーには、まことしやかな物言いや有無を言わさず押しつけられる真実への警戒感があるようなのだ。百科事典というものは、放っておけばみずから権威となり絶対的な規範になる危険をはらんでいるが、「噓と誤りの巻」にはそのような百科事典の病を中和する意図が込められていたとも考えられる。
本書では言及する余裕がなかったけれど、クノーは詩人としても知られており、結構な数の詩集が刊行されている。『運命の瞬間』所収の一編で、冒頭から詩人は「詩なんてまったくたいしたものじゃない」と言い放ち、続く行では「せいぜいアンティル諸島のサイクロンか/中国海のタイフーンといったところ」と巨大災害と比較することで、逆説的に「詩」の大きさを歌いあげている。「たかが文学、されど文学」といった言い方はいかなる分野についても意味をもつものだろうが、この両面のうち、「たかが」と言える羞じらいをもったフランス作家は思いのほか少なく、尊大で大仰な物言いばかりが目につくなかで、クノーのこうした姿勢は貴重である。
知に対する、あるいは文学に対する、クノーの特異なスタンスの象徴としても、ピエロやヴァランタンといった登場人物は気になる対象だったにもかかわらず、これまで彼らにまとまった文章を捧げる機会を持てずにいた。年を重ねるにつれ関心の在りかが拡散したこともあって、今さら取り上げるチャンスはないだろうと思っていたのだが、いっとき夢中で読んだ作家の、もっとも愛着のある作品群を捨て置くのも忍びなく、住居が変わったのをきっかけとして初心に戻って書き始めたのだった。
執筆中こそピエロを満たしたような幸福感に浸っていられたものの、校正中には「起きるはずがない」と考えられていた戦争の勃発によって冷や水を浴びせられることとなった。もとより世界情勢の帰趨を見定める千里眼など持たない私が「勝ったり負けたりしながら戦争は繰り返される」などと訳知り顔でいられるはずがない。
[書き手]塩塚秀一郎(東京大学教授・仏文学者)
ALL REVIEWSをフォローする