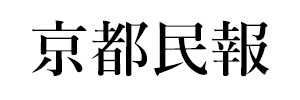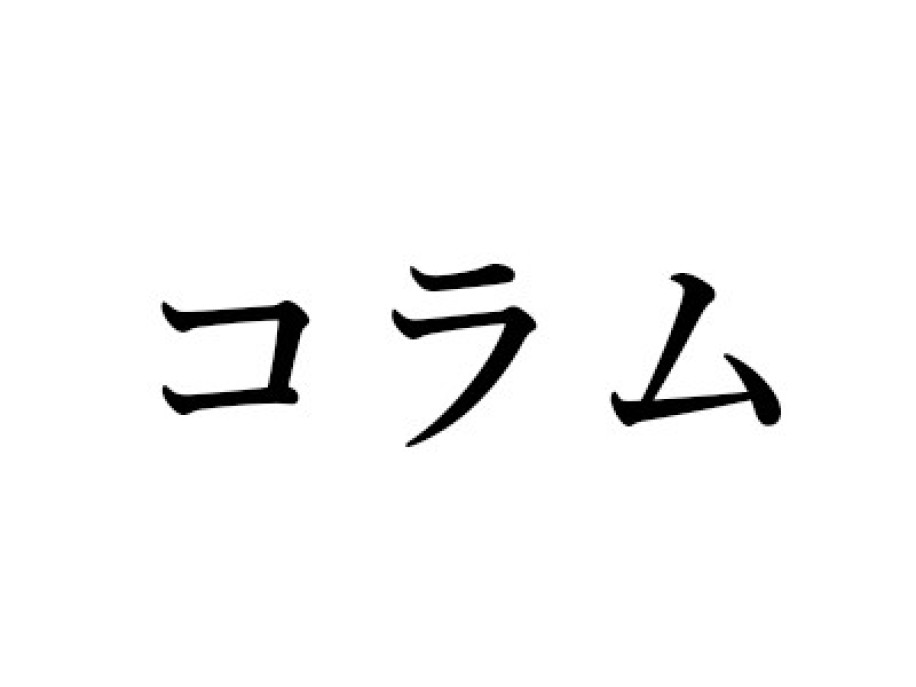書評
『列島を翔ける平安武士: 九州・京都・東国』(吉川弘文館)
古き中世武士像との決別
一所懸命、東国、鎌倉といった言葉から中世の武士を連想する人は多いだろう。京都から遠く離れた先祖伝来の地にしっかりと根を下ろし、文字通り一所懸命にそこを守り抜く存在。そんな中世の武士たちが、実は歴史の表舞台に登場した平安時代から日本列島を広く移動する存在だった。これが本書を貫くテーマである。かつて中世武士・武士団を論ずる際に、対象となる地域は東国が主流であった。その後、本書の著者らによる武士と京都との関係を重視する研究の盛行により、京都が武士論の重要な場として論じられるようになった。本書は、そうした視角の延長上に、これまで武士成立史の中であまり注目されてこなかった九州に焦点をあて、11~13世紀に京都・東国で生まれ、九州へと下向・土着し、そこで子孫が繁茂した武士たちを主役に据える。
11世紀以降、九州に下向・土着した武士たちは、大陸・南島との交易の拠点である南九州への進出をはかった。交易で得た輸入品をもとに貴族たちへの奉仕を行い、自身は九州と京都とを往来し、京都で様々なネットワークを形成していた。東国武士の代表的な存在の千葉氏は、鎌倉期に本領の下総以外に、九州・東北にも所領を獲得し、列島規模で活動する武士であった。それが平安期以来の武士のあり方として決して特殊でなかったことは、本書を読み進めればおのずと理解されるだろう。
著者は、タイトルの「平安武士」という言葉について、「鎌倉時代以前の武士という意味であり、特別な学術用語ではない」としながらも、京都の貴族社会がイメージされる「平安」と「武士」を一体化させることで、従来の東国中心の武士認識を相対化する意図で付けたと述べる。これこそが本書の真骨頂であり、旧来の中世武士像との決別を高らかに宣言するものである。その意図は、著者のこれまでの研究のエッセンスが余すところなく注がれた本書で、見事に達成されたといえるだろう。
[書き手] 生駒 孝臣(いこま たかおみ・関西学院大学非常勤講師)
ALL REVIEWSをフォローする