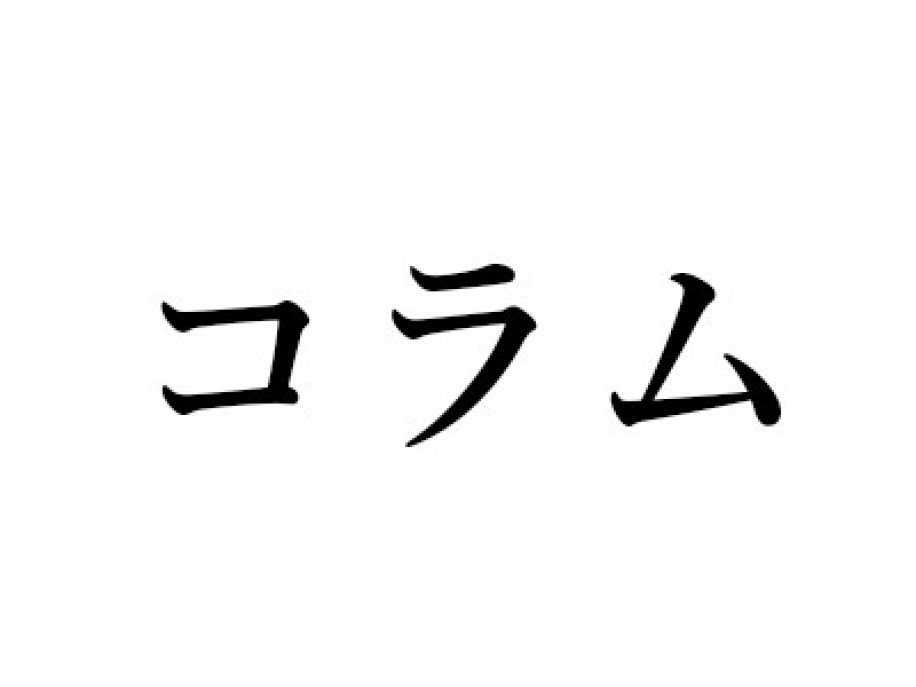自著解説
『論理学をつくる』(名古屋大学出版会)
書店の丸善名古屋本店では、地元・名古屋の大学の先生が選んだおすすめの人文書フェアを定期的に開催している。現在行われている第4弾の選書とコメントを担当したのは、『論文の教室』や『哲学入門』などの著作で知られる名古屋大学・戸田山和久先生だ(6階人文書フロアで11月末まで)。そのラインナップの中から、2000年に発売され今でも読まれ続けているロングセラー『論理学をつくる』と関連書2冊へのコメントをご紹介する。

アメリカの大学に滞在させてもらっていたときに、当地で使われていた教科書がみな分厚いのに刺激を受け、帰国してから興奮状態で書いてしまった本。いまから思うとよくこんな大きくて厚い本を出してくれたと出版会には感謝の言葉しかありませぬ。しかも、本書は私が名古屋大学出版会から出した初めての単著です。だから愛着があるのだ。
自分が論理学を勉強しはじめたときに、なぜこんな定義をしなけりゃならんのか、こんな証明をなぜ思いつけるのか、この定理にはどんなふうに説明していったら…、論理学を天下り式に覚えてもらうのではなく、なぜ様々な考え方や概念が必要になるのかをそのつど説明しながら、ゼロから論理学をつくっていくつもりで書いてみたら、どんな教科書になるだろうと思って執筆しました。練習問題をたっぷり用意して、すべてに解答を書いてあります。なので、先生を頼りにせず、初歩の論理学を読者が一人で学ぶことができる本になったと自負しています。
というわけで、これは過去の自分のために書いた教科書です。論理学や数学が非常にお出来になる勘のいい人には、ちょっとくどく感じられるかもしれませんが、self-containedな教科書、スローラーナーのための教科書もあってよいのではないかな。他の分野でももっとこういうのが書かれるといいのにな、と思います。
本書が出来上がったときに、同僚の数理論理学(集合論)の先生に差し上げたところ、「親切の国から親切を広めに来たような教科書」と褒めてくださいました。これは、落語のある名人の「くすぐり」のもじりですが、さて誰でしょう。これには答えはつけないでおきます。
詭弁(ヘリクツ)や論理パズル、パラドクスは、論理という現象に関心を抱くためのひとつの有力なしかただと思う。この本の初版が出たのは1976年、私が高校三年生のときだ。私と同世代の人たちには、この本で論理学への興味をかきたてられた人も多いはず。それ以来、版を重ねていまだに出版され続けているという事実だけとっても、本書のクオリティの高さは特筆に値する。
著者の大西琢朗さんは、論理学のめちゃくちゃできる哲学者。だからこの本も「正しい論理って何だ。そんなのあるのか」という哲学的関心をベースに書かれている。まずは最もスタンダードな古典論理とその拡張である古典様相論理にきっちり入門するのだが、続く第2部では、その古典論理が唯一正しい論理ではないのでは?という問題意識から提案されてきたさまざまな非古典論理(直観主義論理、多値論理、関連性論理など)が要領よく扱われる。論理学のワンダーランドを周遊するために最適の一冊。
[書き手]戸田山和久(1958年、東京都生まれ。哲学者。『論理学をつくる』のほか、『科学的実在論を擁護する』、『〈概念工学〉宣言!』、『科学技術をよく考える』、『誇り高い技術者になろう[第2版]』、ダニエル・C・デネット『自由の余地』など、著書・編著・訳書多数)
[初出]フェア図書リスト(2022年10月)

発売から23年目の自著紹介
今さらそんなことして、「あんた何考えてんの?!」と言う勿れ
アメリカの大学に滞在させてもらっていたときに、当地で使われていた教科書がみな分厚いのに刺激を受け、帰国してから興奮状態で書いてしまった本。いまから思うとよくこんな大きくて厚い本を出してくれたと出版会には感謝の言葉しかありませぬ。しかも、本書は私が名古屋大学出版会から出した初めての単著です。だから愛着があるのだ。
自分が論理学を勉強しはじめたときに、なぜこんな定義をしなけりゃならんのか、こんな証明をなぜ思いつけるのか、この定理にはどんなふうに説明していったら…、論理学を天下り式に覚えてもらうのではなく、なぜ様々な考え方や概念が必要になるのかをそのつど説明しながら、ゼロから論理学をつくっていくつもりで書いてみたら、どんな教科書になるだろうと思って執筆しました。練習問題をたっぷり用意して、すべてに解答を書いてあります。なので、先生を頼りにせず、初歩の論理学を読者が一人で学ぶことができる本になったと自負しています。
というわけで、これは過去の自分のために書いた教科書です。論理学や数学が非常にお出来になる勘のいい人には、ちょっとくどく感じられるかもしれませんが、self-containedな教科書、スローラーナーのための教科書もあってよいのではないかな。他の分野でももっとこういうのが書かれるといいのにな、と思います。
本書が出来上がったときに、同僚の数理論理学(集合論)の先生に差し上げたところ、「親切の国から親切を広めに来たような教科書」と褒めてくださいました。これは、落語のある名人の「くすぐり」のもじりですが、さて誰でしょう。これには答えはつけないでおきます。
『論理学をつくる』を読む前に読みたい1冊
野崎昭弘『詭弁論理学 改版』(中公新書)詭弁(ヘリクツ)や論理パズル、パラドクスは、論理という現象に関心を抱くためのひとつの有力なしかただと思う。この本の初版が出たのは1976年、私が高校三年生のときだ。私と同世代の人たちには、この本で論理学への興味をかきたてられた人も多いはず。それ以来、版を重ねていまだに出版され続けているという事実だけとっても、本書のクオリティの高さは特筆に値する。
『論理学をつくる』を読んだ後に読みたい1冊
大西琢朗『論理学(3STEPシリーズ)』(昭和堂)著者の大西琢朗さんは、論理学のめちゃくちゃできる哲学者。だからこの本も「正しい論理って何だ。そんなのあるのか」という哲学的関心をベースに書かれている。まずは最もスタンダードな古典論理とその拡張である古典様相論理にきっちり入門するのだが、続く第2部では、その古典論理が唯一正しい論理ではないのでは?という問題意識から提案されてきたさまざまな非古典論理(直観主義論理、多値論理、関連性論理など)が要領よく扱われる。論理学のワンダーランドを周遊するために最適の一冊。
[書き手]戸田山和久(1958年、東京都生まれ。哲学者。『論理学をつくる』のほか、『科学的実在論を擁護する』、『〈概念工学〉宣言!』、『科学技術をよく考える』、『誇り高い技術者になろう[第2版]』、ダニエル・C・デネット『自由の余地』など、著書・編著・訳書多数)
[初出]フェア図書リスト(2022年10月)
ALL REVIEWSをフォローする