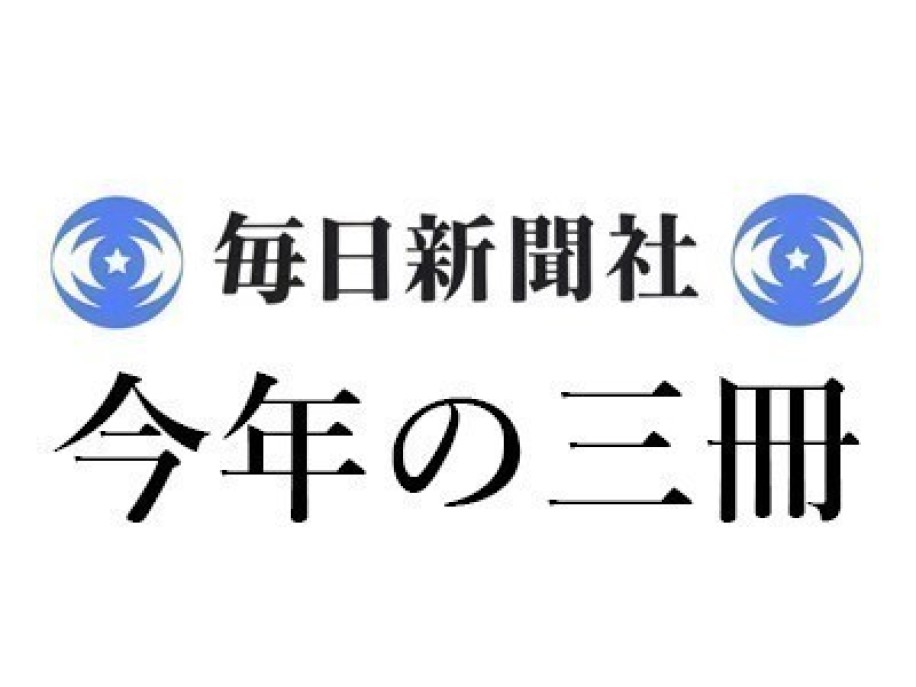書評
『高松宮日記〈第2巻〉 昭和八年〜十二年』(中央公論新社)
戦争時に貫いた複線的思考
「こんな事なら、話をし出さぬか、もつと話しの仕方があつたのだが、私としては、お上が、そんな、オズルイと云ふか、フミツケたなさり方をなさるとは夢想もしなかつた」――高松宮のそれでも怒りをおさえた日記の中での記述だ。日中戦争勃発(ぼっぱつ)直後、上海の戦線視察を申し出た高松宮に対し、一度は許可をした兄の天皇が宮相を通して、一途に負傷への心配から自発的辞退を求めてきた時のことである。ことはこれに止まらず、高松宮は天皇に対して、どうやらアンビバレントな感情を抱いていたようだ。国際連盟脱退に関してしかり、皇太子の教育に関してしかり。高松宮は天皇のやさしさが徒(あだ)になると心配している。
これと同様、「高松宮日記」第二巻(昭和八―十二年)の記述の中にはしばしば陸軍批判、戦争批判が出てくるが、それらを反軍とか平和主義といった単純な戦後的価値で読みとろうとした途端に、高松宮の持つ実に複線的な思考様式が見えなくなってしまう。すなわち高松宮は常に天皇の弟としての立場を積極的に捉(とら)え、皇族・華族の果たすべき役割に思いをめぐらしている。
一例をあげよう。戦時色濃くなった昭和十二年、英国大使館の午餐会(ごさんかい)で首相以下日本の大官が立ちならぶ中で、高松宮はあえて英語で乾杯の辞を述べる。そしてそのことを日記の中に、欧化全盛の時代には英国でも日本語で押し通したが、満州事変後国家主義的風潮になったから逆にこういう席では英語を使うことに意味がある旨を記し、自ら「ヒヨウヘンなり」と書いている。
したがって満州事変や日本の大陸政策についても、あっさりと割り切って判断しない。歴史の中を行きつ戻りつしながら、自分にとっての定点を見きわめようとする思考態度を貫こうとするのである。
また高松宮は好奇心旺盛(おうせい)で、多くの軍人・外交官・学者から情報を入手し、自分なりにまとめたところを記す。神ながらの道に近い筧克彦や平泉澄と会っても、決して無批判に同調はしない。
いずれにせよ、歴史の理解に深みがます資料に出会えたことを、まずは喜びたい。
ALL REVIEWSをフォローする