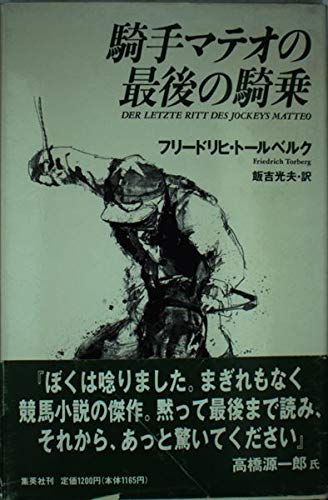書評
『詞華集 日本人の美意識』(東京大学出版会)
ひとことで言えば本書は、万葉の昔から近代に至るまでの「日本文学歳時記」である。
「万葉集」「古今集」「和歌と漢詩」「和漢朗詠集」「枕草子」「源氏物語」……と、時代を代表する文学作品から、それぞれ一月から十二月までの各月にピッタリくる一作品(あるいは一節)をとりあげ、解説が加えられている。
たとえば、第二巻のトップバッター「蕪村」の項を開くと、一月は「白梅や誰がむかしより垣の外」二月は「春雨やもの書(かか)ぬ身のあはれなる」三月は「日は日くれよ夜は夜明ケよと啼蛙」――という具合。一作品につき見開き二ページの解説が、ほどよい分量で、どれもわかりやすく、作品の理解を助けてくれる。
万葉びとの気分になって万葉集の一年を楽しみ、次は古今集の一年を味わう、という読み方がまずできるだろう。あるいは、八月なら八月のところをタテに読み進めて、さまざまな時代の八月を体験してみるのもいい。
「あらし吹く梢はるかに鳴く蝉の秋を近しと空に告ぐなる」という藤原定家の八月。「夏の河赤き鉄鎖のはし浸る」という山口誓子の八月。「ああ接吻海そのままに日は行かず鳥翔ひながら死せ果てよいま」という若山牧水の八月……。
『日本人の美意識』というタイトルを、読者として受身にとらえていると、この本の魅力は半減してしまうだろう。日本人の美意識について書かれたものではないし、右(事務局注:上)の八月の三例からもわかるように、「日本人の美意識とは何か」という問いに対してただ一つの答えを用意しようとしているわけでもない。
まさに歳時記のように、くり返しくり返しページをめくることによって、日本人の美意識の広がりと深さ、豊かさを感じとる――そういう能動的な読み方を、このタイトルは願っているように思う。
「歌合」「連歌」など、美意識のぶつかりあう場を、項目としてとりあげているのがまたおもしろい。その他にも「江戸漢詩」「歌舞伎」「落語」「翻訳詩」「近代詩歌」「近代詩」と幅広いジャンルにわたって、十ニヵ月が展開される。
国際化社会、ということが声高に言われる今日このごろ。自国の文化を知らずして、真の国際人にはなれないだろう。日本語の財産を知りたい人のための入門書としても、本書は役立つのではないかと思う。
【この書評が収録されている書籍】
「万葉集」「古今集」「和歌と漢詩」「和漢朗詠集」「枕草子」「源氏物語」……と、時代を代表する文学作品から、それぞれ一月から十二月までの各月にピッタリくる一作品(あるいは一節)をとりあげ、解説が加えられている。
たとえば、第二巻のトップバッター「蕪村」の項を開くと、一月は「白梅や誰がむかしより垣の外」二月は「春雨やもの書(かか)ぬ身のあはれなる」三月は「日は日くれよ夜は夜明ケよと啼蛙」――という具合。一作品につき見開き二ページの解説が、ほどよい分量で、どれもわかりやすく、作品の理解を助けてくれる。
万葉びとの気分になって万葉集の一年を楽しみ、次は古今集の一年を味わう、という読み方がまずできるだろう。あるいは、八月なら八月のところをタテに読み進めて、さまざまな時代の八月を体験してみるのもいい。
「あらし吹く梢はるかに鳴く蝉の秋を近しと空に告ぐなる」という藤原定家の八月。「夏の河赤き鉄鎖のはし浸る」という山口誓子の八月。「ああ接吻海そのままに日は行かず鳥翔ひながら死せ果てよいま」という若山牧水の八月……。
『日本人の美意識』というタイトルを、読者として受身にとらえていると、この本の魅力は半減してしまうだろう。日本人の美意識について書かれたものではないし、右(事務局注:上)の八月の三例からもわかるように、「日本人の美意識とは何か」という問いに対してただ一つの答えを用意しようとしているわけでもない。
まさに歳時記のように、くり返しくり返しページをめくることによって、日本人の美意識の広がりと深さ、豊かさを感じとる――そういう能動的な読み方を、このタイトルは願っているように思う。
「歌合」「連歌」など、美意識のぶつかりあう場を、項目としてとりあげているのがまたおもしろい。その他にも「江戸漢詩」「歌舞伎」「落語」「翻訳詩」「近代詩歌」「近代詩」と幅広いジャンルにわたって、十ニヵ月が展開される。
国際化社会、ということが声高に言われる今日このごろ。自国の文化を知らずして、真の国際人にはなれないだろう。日本語の財産を知りたい人のための入門書としても、本書は役立つのではないかと思う。
【この書評が収録されている書籍】
朝日新聞
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする