書評
『知のハルマゲドン』(幻冬舎)
片や週刊『SPA!』に連載の『ゴーマニズム宣言』で、新新宗教や差別問題、天皇制といった日本のタブーに挑戦、未踏の領域を切りひらいた小林よしのり氏。片や、『ニセ学生マニュアル』といった裏道から、「正攻法」で思想界に侵入、広汎な支持と共感を集めている浅羽通明氏。この両氏が日本のいまを縦横に語れば、ウィンブルドンのセンターコート並みの見応えあるラリーの応酬となるのは当然だ(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1995年)。
まず浅羽氏のファースト・サーヴ。氏は『ゴー宣』の大ヒットの理由を裏側から検証、そこに既成のオピニオン雑誌を舞台とする日本の知的言論の衰弱と頽廃をみる。《要するに彼らの論理が、私たちの等身大のところまでかみあって来なかった》(一一頁)(事務局注:本書評は単行本版・絶版へのもの)のだ。インテリが業界・仲間うちの言葉のやりとりにかまけているうちに、知は格闘技としての実質を失ってしまった、と浅羽氏は診断する。そうした状況に風穴を空けたのが『朝まで生テレビ』、さらにそれを越えたのが『ゴー宣』だという。
これに対し小林氏は、創作の舞台裏を率直に語り、読者との駆け引きを明らかにする。『ゴー宣』の強みは現実と同時進行でストーリーが展開、筆者自身(小林氏)も登場し、読者に生で訴えかけていくことだ。その昔、シネマ・ベリテといって、シナリオなしに現実を撮影してしまう映画があったが、現像→公開に時間がかかる映画には双方向性を望むべくもなく、成功しなかった。『ゴー宣』はさしずめ、マンガ・ベリテだが、週刊誌の利点を活かし、毎週、読者・現実とのフィードバックに成功している。『ゴー宣』はボレーやスマッシュといった、ネット際のプレーに強いのだ。
本書に通底するのは、知識人批判である。といっても、もはや死に絶えた戦後知識人ではない。中沢新一、西部邁、栗本慎一郎、島田裕巳、呉智英、田原総一朗といった、八〇年代以降のマスメディアに登場し、いわゆる知識人の枠をはみ出して読者・視聴者大衆と関わろうとした人びとである。オウム信者の何割かが中沢氏の読者だったという話からも明らかなように、九〇年代の読者・視聴者は、これら“ポスト知識人”を自分の知的形成の準拠点としているのだ。ここにどのような知の倫理が求められるべきか? 小林氏、浅羽氏は体験のなかから、それを示そうとしている。
“ポスト知識人”のポストたる所以は、その知的ポジションがメディア状況と密接不可分に決まっている点である。八〇年代以降のメディアは「権威崩し」をテーマにし、それをやりつくした。そこでは「外部性」(どこかアカデミズムをはみ出しているなあ、という感じ)が、タレントであることの要件になる。“ポスト知識人”たちは何らかの「外部性」を背景にしながら、知的権威になぐり込みをかけた。ほんとうは知的権威のかけらも残っていないのに、権威に異をとなえる“ポスト知識人”ばかりが氾濫するという、転倒した状況が当たり前になった。
そうした現在、小林氏のスタンスを、浅羽氏がこう的確に評している。《彼ら(ポスト知識人)は、……やはり完成した思想=真理を語るといったプライドから自由でないんだ。その点、小林さんはこの対極にあって思想を語り始めた。……ただ自分の良識のみを頼りにゴーマンをかましていくしかない。しかし、実はこの永遠の未完成の態度こそは、今もっとも有効でまた支持を集められる思想の方法ではなかったでしょうか》(三八頁)。いつ終わるとも知れぬ『ゴー宣』の連載形式こそが、本質的なのである。
いっぽう浅羽氏のスタンスの面白さは、かつて雑誌『ムー』に関わっていた“元オカルト青年”の経歴を背負いながら、異種格闘技戦である思想家(ポスト知識人)の闘いを「論評」するという、「公共」言論の場に登場した点である。浅羽氏は、オタク世代のダメさ加減も、そこへ追い込まれるしかなかったメディア状況の必然もよくわきまえている。だからこそ、そういう読者・視聴者に到達できるかを基準に、ポスト知識人の出来不出来を選別することができるのだ。
ポスト知識人が権威崩しと価値相対主義の産物だとすれば、いま問題はその先にある。どのように、知の権威、知の社会的機能を回復するか。
権威とは、正しさの基準。情報化が進展すると、戦後知識人の権威はもろく崩れた。彼らの海外のタネ本がつぎつぎ紹介されてしまったうえ、彼らが机上で描いた世界像が、現実とどう喰い違うのか即座にばれてしまうからである。しかし、権威のないところに、知識の社会的効力はない。ここまで進んだ情報化に踏みこたえる思想は、どういうかたちで可能なのか。
平凡であることを恐れるな、という小林氏のメッセージが、ひとつのヒントになる。メディアのなかでは、極端(だけ)がもてはやされる。その結果、読者・視聴者は平均値に押し込められる。そしてそれを、抑圧(なんて平凡な私!)と感じてしまう。これにめげるかどうかが、分岐点なのだ。《普通の日常が退屈で、彼岸ばっかり見て夢を馳せたくなる人間というのは……精神のバランスを崩した病にかかっとる……。快感マヒマヒ病》。これを浅羽氏は《まずは極めて私的なところから出発する。そこからどれだけ普遍性のある地点までたどれるかで、私の思索のほどが試されている》と受ける。
ポスト知識人たちの出番はもう終わったのかもしれない。そのあとを受けるのは、マスメディアと無縁のペースで自分の課題を掘り下げる知のプロと、読者・視聴者との、水平で双方向の協力関係となるはずだ。そうした課題の広がりを、『知のハルマゲドン』は見せてくれたのだった。
【この書評が収録されている書籍】
まず浅羽氏のファースト・サーヴ。氏は『ゴー宣』の大ヒットの理由を裏側から検証、そこに既成のオピニオン雑誌を舞台とする日本の知的言論の衰弱と頽廃をみる。《要するに彼らの論理が、私たちの等身大のところまでかみあって来なかった》(一一頁)(事務局注:本書評は単行本版・絶版へのもの)のだ。インテリが業界・仲間うちの言葉のやりとりにかまけているうちに、知は格闘技としての実質を失ってしまった、と浅羽氏は診断する。そうした状況に風穴を空けたのが『朝まで生テレビ』、さらにそれを越えたのが『ゴー宣』だという。
これに対し小林氏は、創作の舞台裏を率直に語り、読者との駆け引きを明らかにする。『ゴー宣』の強みは現実と同時進行でストーリーが展開、筆者自身(小林氏)も登場し、読者に生で訴えかけていくことだ。その昔、シネマ・ベリテといって、シナリオなしに現実を撮影してしまう映画があったが、現像→公開に時間がかかる映画には双方向性を望むべくもなく、成功しなかった。『ゴー宣』はさしずめ、マンガ・ベリテだが、週刊誌の利点を活かし、毎週、読者・現実とのフィードバックに成功している。『ゴー宣』はボレーやスマッシュといった、ネット際のプレーに強いのだ。
本書に通底するのは、知識人批判である。といっても、もはや死に絶えた戦後知識人ではない。中沢新一、西部邁、栗本慎一郎、島田裕巳、呉智英、田原総一朗といった、八〇年代以降のマスメディアに登場し、いわゆる知識人の枠をはみ出して読者・視聴者大衆と関わろうとした人びとである。オウム信者の何割かが中沢氏の読者だったという話からも明らかなように、九〇年代の読者・視聴者は、これら“ポスト知識人”を自分の知的形成の準拠点としているのだ。ここにどのような知の倫理が求められるべきか? 小林氏、浅羽氏は体験のなかから、それを示そうとしている。
“ポスト知識人”のポストたる所以は、その知的ポジションがメディア状況と密接不可分に決まっている点である。八〇年代以降のメディアは「権威崩し」をテーマにし、それをやりつくした。そこでは「外部性」(どこかアカデミズムをはみ出しているなあ、という感じ)が、タレントであることの要件になる。“ポスト知識人”たちは何らかの「外部性」を背景にしながら、知的権威になぐり込みをかけた。ほんとうは知的権威のかけらも残っていないのに、権威に異をとなえる“ポスト知識人”ばかりが氾濫するという、転倒した状況が当たり前になった。
そうした現在、小林氏のスタンスを、浅羽氏がこう的確に評している。《彼ら(ポスト知識人)は、……やはり完成した思想=真理を語るといったプライドから自由でないんだ。その点、小林さんはこの対極にあって思想を語り始めた。……ただ自分の良識のみを頼りにゴーマンをかましていくしかない。しかし、実はこの永遠の未完成の態度こそは、今もっとも有効でまた支持を集められる思想の方法ではなかったでしょうか》(三八頁)。いつ終わるとも知れぬ『ゴー宣』の連載形式こそが、本質的なのである。
いっぽう浅羽氏のスタンスの面白さは、かつて雑誌『ムー』に関わっていた“元オカルト青年”の経歴を背負いながら、異種格闘技戦である思想家(ポスト知識人)の闘いを「論評」するという、「公共」言論の場に登場した点である。浅羽氏は、オタク世代のダメさ加減も、そこへ追い込まれるしかなかったメディア状況の必然もよくわきまえている。だからこそ、そういう読者・視聴者に到達できるかを基準に、ポスト知識人の出来不出来を選別することができるのだ。
ポスト知識人が権威崩しと価値相対主義の産物だとすれば、いま問題はその先にある。どのように、知の権威、知の社会的機能を回復するか。
権威とは、正しさの基準。情報化が進展すると、戦後知識人の権威はもろく崩れた。彼らの海外のタネ本がつぎつぎ紹介されてしまったうえ、彼らが机上で描いた世界像が、現実とどう喰い違うのか即座にばれてしまうからである。しかし、権威のないところに、知識の社会的効力はない。ここまで進んだ情報化に踏みこたえる思想は、どういうかたちで可能なのか。
平凡であることを恐れるな、という小林氏のメッセージが、ひとつのヒントになる。メディアのなかでは、極端(だけ)がもてはやされる。その結果、読者・視聴者は平均値に押し込められる。そしてそれを、抑圧(なんて平凡な私!)と感じてしまう。これにめげるかどうかが、分岐点なのだ。《普通の日常が退屈で、彼岸ばっかり見て夢を馳せたくなる人間というのは……精神のバランスを崩した病にかかっとる……。快感マヒマヒ病》。これを浅羽氏は《まずは極めて私的なところから出発する。そこからどれだけ普遍性のある地点までたどれるかで、私の思索のほどが試されている》と受ける。
ポスト知識人たちの出番はもう終わったのかもしれない。そのあとを受けるのは、マスメディアと無縁のペースで自分の課題を掘り下げる知のプロと、読者・視聴者との、水平で双方向の協力関係となるはずだ。そうした課題の広がりを、『知のハルマゲドン』は見せてくれたのだった。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
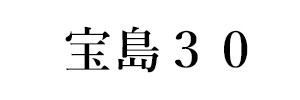
宝島30(終刊) 1995年9月
ALL REVIEWSをフォローする






































