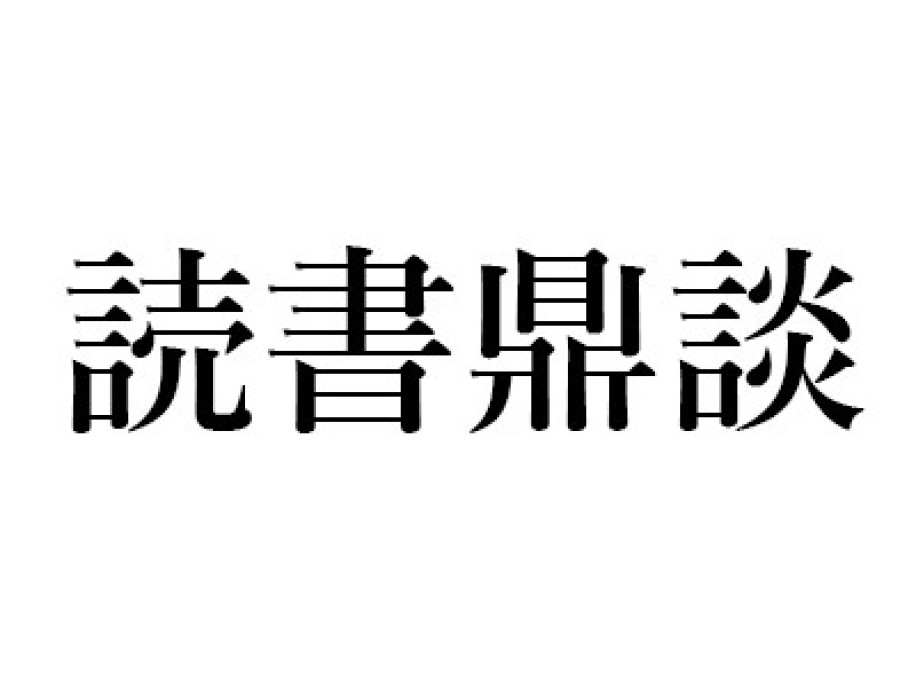書評
『日本の不平等』(日本経済新聞社)
格差論ブームの仕掛け
バブル経済がはじけたあと、ある経済学者が大雑把(ざっぱ)な統計データをもとに、日本はアメリカより不平等な経済格差社会だといいはじめた。それ以来、格差拡大論はブームになった。勝ち組・負け組論などの格差本ジャンルさえできている。小泉政権下でますます格差がひろがっています、という選挙用格差節もある。著者は、単純で、表面的な統計の利用ではなく、学歴や年齢などにカテゴリーを分解しながら、所得格差拡大説を追い詰めていく。たしかにみかけ上、世帯による所得格差は拡大している。しかし、学歴や年齢など同じカテゴリー内部での所得格差は拡大してはいない。この矛盾をどう解くかが著者の苦心したところである。勤労所得のない高齢者が独立世帯をもつことによって、世帯所得分布の見せかけの不平等化を大きくさせた、というのが著者による知見である。逆にいえば、かつて日本社会が平等にみえたのは、所得が比較的平等な若年世帯が多かったことによる。賃金格差についても、1980年代の格差は、労働者の高齢化によるもので、90年代以降は、格差はそれほど変化していない。米英で観察された急激な賃金格差の拡大は日本にはみられないという。
にもかかわらず、所得格差感情はひろがっている。著者の仮説は、人々の格差拡大意識は、賃金や収入の現実の格差拡大よりも、失業者やホームレスなどの増大がシグナルとなっているのではないか、というものである。データをひとつひとつ吟味し、いえること、いえないことを弁別していく著者の研究姿勢は実証研究の鑑(かがみ)である。
本書を読めば近年の格差拡大論ブームの仕掛けもうかびあがってくる。政治家や行政は解決すべき社会問題を、ジャーナリズムは危機を煽(あお)るトピックがほしい。これと学者たちの世にうけたい願望の共謀関係によるものではないかとさえおもえてくるのである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする