書評
『学歴・階級・軍隊―高学歴兵士たちの憂鬱な日常』(中央公論新社)
学歴社会崩壊がみえる
『学歴・階級・軍隊』を読む
かつて「学校出」「大学出」「帝大出」といった言葉がよく使われていた。出身階級以上に学歴が他者と自己を同定する属性だった。だから、学歴エリートには優越感、庶民には屈折した学歴ルサンチマン(憤懣)が生じた。
こうした優越感とルサンチマンの交差した場所が軍隊である。「此処(ここ)は学校じゃないんだ。もっと気合を入れろ」と、軍隊で高学歴兵士が庶民からいじめられ、殴られたという話を読んだり、聞いたりする。そこで本書(高田里惠子『学歴・階級・軍隊――高学歴兵士たちの憂鬱な日常』中公新書、二〇〇八年)は、高学歴兵士の帝国陸軍での経験を小説や映画、体験記から掬いあげる。
なるほど確かにとおもえることは多い。大正時代までは徴兵率が低く、インテリの中でも屈強な者が軍隊を経験した。ところが、昭和十年代は徴兵率が上がり、ひ弱な高学歴兵士が多くなったことが高学歴兵士いじめに関係しているという。また、昭和戦前期における平等感情の進展も関係しているという点。高学歴兵士の出身階級のハイカラな生活が庶民のねたみの対象になったからだ。「おれたちより楽しそうに暮らしていた、おまえたちが憎かった」というものである。
しかし、高学歴兵士が無垢かといえば、そうではない。師範出などの傍系学校出に対しては隠微な差別をしていたのだから。
帝国陸軍というフィールドによって日本人にとっての学歴の意味をあぶりだす着眼点が鋭い。同時に日本人の平等感情構造の指摘も大いに考えさせられる。日本人の平等感は「不幸の等分化」や「犠牲の平等」ではないか、というものである。ここらあたりは、丸山眞男が日本のデモクラシーを「引き下げ」デモクラシーと言っていることと通底する。
近年は一流大学でも、学部入試よりはるかに易しい編入や大学院入試によって簡単に入学できるという現実も生まれている。高学歴エリートから一流企業、官庁へという特権コースもほころびが見える。本書で摘出された学歴ルサンチマンが積もり積もったことによる「学歴社会破壊」ではないか、とおもえてくるのである。
初出メディア
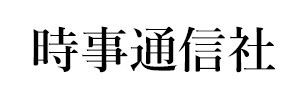
時事通信社 2008年8月17日ほか
ALL REVIEWSをフォローする



































